季語にならない季語?
せっかく俳句で季語を使ったのに、実はその言葉が季語として機能していない、ということがあります。
今回は、俳句初心者の方が見落としがちな、季語の「落とし穴」について探っていきましょう。
季語が「季語にならない」理由
俳句において、季語は「その季節にしか見られない、生きた風物」を指します。
そのため、季語が絵や写真、あるいは想像の中の存在になってしまうと、季節感が失われ、季語として機能しなくなってしまいます。
例えば、
| 〇 | 雪:冬の寒さや情景を伝える生きた季語。 |
| × | 雪の絵:一年中見ることができ、それ自体に季節感はありません。 |
同様に、以下のような例も季語にはなりません。
| 〇 | 梅:春の訪れを告げる梅の花。 |
| × | 梅のガム:一年中売られている、梅の香りのガム。 |
| 〇 | 熊:冬眠する熊や、自然の中で生きる熊。 |
| × | 熊のおもちゃ:季節を問わず存在するおもちゃ。 |
| 〇 | 桜:春の日本を代表する花。 |
| × | 桜の写真:写真に写っている桜は、作者がその場で見た「生きた桜」ではない。 |
これらのように、季語が持つ「生きた季節感」を失ってしまった言葉は、季語として成立しないのです。
「雛の絵」という例外
ただし、中には例外もあります。
例えば、ひな祭りの季語である「雛の絵」は、絵でありながら季語として成立します。
これは、「雛の絵」が単なる絵ではなく、ひな祭りの時期にだけ掛け軸などに描いて飾られる、行事の一部だからです。
このように、季語には「なぜ季語になるのか」という、言葉の背景にある理由があります。
季語を選ぶことは、言葉の奥深さを知る旅です。言葉の持つ意味だけでなく、その裏に隠された文化や、言葉のルールを理解することで、あなたの俳句はもっと楽しく、豊かなものになるでしょう。
ひなの絵については、こちらで詳しく解説しています。


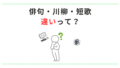
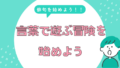
コメント