「おーいお茶俳句に入選するコツ」「選ばれるために注意したいこと」「応募の方法」などについて記事にしています。
7回応募をして、4回入選している実体験からアドバイスします。
これは良さそう、と思ったことを真似てもらえれば、と思います。
入選しやすい俳句の6つの傾向
最終的に選ぶのは選考委員会の人たちです。
それぞれの好みがあるので、絶対にこういう作品にするべき、ということは言えませんが、過去の入選作品1万句以上をみて感じた、入選しやすい傾向を書きます。(あくまで、わたしが感じたことです)
① 自分の体験したこと
② 自分の心境や感じたこと
③ ほっとするような作品
④ 分かりやすい俳句
⑤ 年齢にあった俳句
⑥ 面白い視点
このような俳句が、入選する傾向の高いように感じます。
それぞれを具体的に説明していきます。
① 自分の体験したこと
「①自分の体験したこと」というのは、例えばお祭り、凧揚げ、雪合戦、初詣など、自分の体験を伴うことを作品にすることです。
別の言い方をすると、作品の中に作者が感じられる、そんな作品です。
そのような作品が、多く入選しています。
俳句の世界では、花の様子をそのまま詠んだり、月の様子をそのまま詠むことが良しとされることがあります。
もちろん、そのような作品も入選はしているのですが、花の様子をそのまま詠んだり、月の様子をそのまま詠むのでしたら、せめてそこで作者が何をしたのか、という体験が入っていたほうが良いと感じます。
② 自分の心境や感じたこと
「②自分の心境や感じたこと」というのは、例えば、夢や目標、恋心などでもいいでしょうし、学校、家の中、友達、仕事場といった場所で感じたことなどを詠みます。
その人自身の心境や感じたことというのは、その人にしか詠めないものです。
鑑賞する立場になっても共感できる作品になりやすくなります。
③ ほっとするような作品
「③ほっとするような作品」というのは、例えば、ちょっとクスッとするような出来事、友達とのこと、家族との思い出などがあると思います。
そのような俳句を作ります。
おーいお茶を買って、一口飲む前に俳句を読みますが、そのときにほっと出来たらいいですよね。
お茶もよりおいしく感じられます。
おそらく、そういった作品を主催者も望んでいるのではないでしょうか。
仮にですが、パッケージに病気、政治、人の中傷、社会風刺といった俳句ばかりが掲載されていたら、いやな気分になりますよね。
わたしがおーいお茶の購入者だったら、二度と買わなくなります。
ですので、読者(おーいお茶の購入者)がほっとするような、心温まるような題材を俳句にすると、良いと感じます。
④ 分かりやすい俳句
「分かりやすい俳句」というのは、小学生にも分かるような俳句です。
おーいお茶の購入者は子供からお年寄りまで様々です。
そうであれば、誰にでも分かる俳句のほうが掲載の可能性は高いはずですし、実際に入選句の多くは分かりやすい俳句です。
俳句というと、小難しい言葉を使っているイメージがある、という人は多いのではないでしょうか
そのため、初心者の中には、普段使わないような言葉を使って俳句を作る人がいるのですが、これはやめた方がよいでしょう。
多くの場合、他の人にも理解できない句を作ってしまうことになるでしょう。
他の人に理解できない、つまり選ぶ人達も理解できない句ですから、入選からは外れるでしょう。
俳句が小難しい言葉と感じるのは、言葉や仮名の使い方などが昔のものを使う傾向があるため、俳句に慣れていない人は、小難しいように感じるだけです。
ただ、この部分を今の言葉に直して俳句を読むと、ほとんどの俳句は、難しいことは何一つ言っていません。
ですから「俳句は小難しいもの」という思い込みで、小難しい言葉を使って俳句を作るのは、やめた方が無難です。
なるべく分かりやすい言葉で、分かりやすい内容の俳句を作るように心がけましょう。
「分かりやすい俳句」を作ろう、に通じることですが
おーいお茶俳句大会で集まってくる俳句の数は200万句です
400字詰めの原稿用紙に一行一句書くと、5万枚分
小説などの文芸書の170冊分の量です
考えてみてください。
もしあなたが選ぶ側の立場だとして、200万句の中から2千句(1000句に1句)の入選句を選ぶのだとしたら、絶対条件として、一瞬で意味の分かる句を、選ばざるを得なくなるはずです。
ですから
理屈っぽい句
頭で考えさせるような句
専門用語を使った句
理智に訴えかけるような句
このような句は、作った本人は満足できるのかもしれませんが
結果的には、ほとんどの人が一瞬では理解できない俳句になることが多く、選ばれる確率はかなり低くなると思います。
おーいお茶俳句の動画では、受賞のコツのようなものも載っていて
「普通の言葉で良い、立派な言葉でなくて良い」 金田一秀穂
「俳句できどりたくなっちゃう言葉を、素直な言葉で書くといい」 いとうせいこう
と言っています。
⑤ 年齢にあった句を作る
おーいお茶俳句大会では、年齢を記入する欄が設けてあります。(虚偽の年齢が発覚した時は、入選は取り消されます)
年齢を記入する以上、年齢に合った俳句を作った方が良いとも言えます。
小学生であれば、友達と遊んだこと、夏休みの宿題など
中高生であれば、受験や、初恋のこと
成年であれば、結婚や、子供のこと
など、それぞれの年齢ごとに、相応しい出来事や物の見方があると思いますので、それらを踏まえて、句を作ったほうが鑑賞した人の共感を得るはずです。
あまり良くないのは、過去を振り返って俳句にすることです。
俳句では、過去のことも今現在、今目の前で起こっていることのように詠みますので、仮に40歳の人が、過去を振り返って初恋の句を詠んだとすると、その人が、今まさに初恋をしているように取られてしまいます。
これでは、たとえその句が良い句だったとしても、違和感を強く感じます。
もしどうしても、昔のことを思い出して句を作るのだとしたら
今の年齢でその体験をしても、不自然ではない題材を選んだほうが良いと言えます。
例えば、小学生の時に感動した体験
「満天の星空を見た」
「山で茸採りをした」
という題材を詠むのでしたら
40歳でも、80歳でも同じように感動するはずですので、良いと思います。
詠んだ句が、いまの年齢に合っているのか、提出の前に確認をしたほうがよいでしょう。
⑥ 面白い視点
「⑥面白い視点」は、人が感じないような視点で俳句を作るということです。
人が感じないような視点で作れれば、当然入選確率が高まりますが、それができないから、多くの人が悩むわけです。
いままで挙げた中で、一番難しいことではあります。
ちなみに、審査員の方の言葉に、作るときのヒントがありましたので紹介します。
「オリジナリティとリアリティを大事に」「あまり見たことのない表現で」 夏井いつき
「日常の切り取りの妙を競うのが大事」 いとう せいこう
この言葉を参考に、作ってみてください。
ひとこと
入選しやすいと思われる6つの題材・視点を挙げました。
同じ題材で俳句を作っても、100人いれば100通りの俳句ができます。
後は、その作品のセンスがいいか、選考委員会の人たちの好みに合うかなど、いろいろなものが合わさって入選するかしないかが決まるのでしょう。
題材選びや、実際の作品作りは少なからずセンスもあると思いますが、これから紹介するものはセンスとは関係のないことを紹介します。
実践しないより、したほうが入選確率は高まることを紹介していきます。
選ばれるために出来る4つのこと
選ばれるために出来る5つ紹介します。
ここに書くことは、俳句作りのセンスとは関係のないことで、誰もがやろうと思えばできることです。
入選確率は少しでも高まるはずですので、実践してください。
①必ず6句応募すること
②できれば多めに句を作る
③見直しの期間を用意すること
④応募する句を選ぶ
これらを実践すると、こういった俳句が入選する傾向が高いように感じます。
それぞれを具体的に説明していきます。
①必ず6句応募すること
おーいお茶に投稿できる句は、一人最大6句です。
ですので、必ず6句提出しましょう。
自信のあるのが1句しかない、と思っても、必ず6句提出します。
自分が良いと思う句と、選ぶ人が良いと思う句は違います。
自信がないと思った句が入選することもありますので、6句提出することです。
6句も作れない、と言う人もいると思いますが、何が何でも6句作って提出します。
1句しか提出しない場合と、6句提出した場合では、6倍入選する確率は高まります。
②できれば多めに句を作る
1回の大会で、最大6句まで投稿できるのですが、できればもう少し多めに作りましょう。
6句だけ作って、その6句を提出するのも良いのですが、それよりも
10句作って、その中の自信作の6句を選んだ方が良いでしょう。
結局提出する俳句の数は同じなのですが、提出するまでに自分の中で一選考して選ばれた6句の方が、入選する確率は高まるはずです。
③見直しの期間を用意すること
おーいお茶俳句大会の応募期間は、11月から翌年の2月末までです。
期間はかなり長くありますので、投稿する予定の俳句を見直しする期間を設けましょう。
一度、投稿する予定の6句が決まったら、一カ月間その句を見ないで過ごしましょう。
一カ月後に新しい気持ちで見直してみると、違和感を感じる部分が必ずあると思うので
その部分を直して投稿するようにしましょう。
まったく違和感がなければ、そのまま投稿します。
俳句は、ベテランの人でも、自分の句を客観的に見ることが難しいものです。
誰でも、作ったばかりの句は、上手く作れたたように感じてしまいます。
ですから、一ヶ月くらい期間をおいて、他人の句を読むような気持で、句を見直してみましょう。
すると、作ったばかりの時には気が付かなかった粗が、目につくはずです。
自分が気づいた粗は、他の人にはもっと気が付くので、そのままにせず、必ず直して投稿するようにしましょう。
④応募する句への問いかけ
おーいお茶俳句の応募上限である6句よりも多く俳句が作れた場合
その中から応募する句を選ぶ必要があります。
この時に多くの人は、どの句を出せば良いのか迷うと思います。
「これにしよう」と最初は思っていても、見返してみると「やっぱりこっちが良いかな・・・」と判断に迷ってしまうのです。
一度応募してしまった句は、後からは交換ができないのですから、迷うのは当然です。
私の経験ですが
このように迷ったときは、ひとつの問いかけをしてみてください。
「この句は詩だろうか?」という問いかけです。
この問いかけをしながら句を見返すと
「詩ではないかもしれない」と思う句が混じっているものです。
そのような句は、応募しないことです。
「こちらの方が詩だ」と思えるものを応募した方がよいでしょう。
詩ではないかもしれない、と思った俳句の多くは、説明文のような俳句だったり
誰もが考える当たり前のことを言っていたりします。
句を選別するときに使える問いかけですので、試してみてください。
おーいお茶俳句のいろいろな情報
おーいお茶俳句のホームページ
過去の入選作品
おーいお茶俳句で、どのような作品が入選するの?と感じている方は、過去の作品集を実際に見たほうが良いと思います。
そこから感じられることはたくさんあるはずです。
第34回おーいお茶俳句の過去作品集 >>>
入選倍率・応募総数
入選倍率は0.36%
第34回は1,921,404句の応募総数で、入選したのは7,000句でした。
入選倍率は低いですが、応募しなければ入選しないので、応募しましょう。
字余り、季語なしはどうなる?
おーいお茶俳句は「新俳句」で、少しの字余りや季語なし俳句でも気にせずに作ってくださいと言っています。
字余りでもあなたの気持ちがストレートに表現できるのでしたら、そちらを優先してよいと言えます。
結果はいつ
おーいお茶俳句の入選結果は11月下旬にホームページでされます。
申し込み用紙
大谷翔平の俳句
お~いお茶グローバルアンバサダー 大谷翔平の俳句です。
いつの日も 僕のそばには お茶がある
良い俳句ですね。
最後に
未経験でも大丈夫
入選の確率はみな平等です。
俳句経歴が無い人も30年の人も、平等です。
あとは自分の作った句を信じて応募するだけです。
あなたの作った句が入選することを祈ってます。
小学生の俳句の作り方
おーいお茶は小学校単位で応募もできます。
本サイトでは、小学生の俳句の作り方(指導案)も記事にしていますので、よければ参考になさってください。
小学生の俳句の作り方(指導案) >>>
入選した作品を集めた句集
何度ご応募されても、なかなか俳句大会での入選の栄誉に恵まれないというお悩みを抱えていらっしゃる方もいると思います。
本ブログの運営者は、これまでに俳句大会で入選した作品だけを集めた句集を出しています。
全国の俳句大会や、全国紙など様々な大会の入選句が掲載されているので、入選作品に共通する傾向や、選者の着眼点など、ご自身の作品作りにおいて参考になれば幸いです。
関連記事
- 「NHK俳句」の放送時間・応募方法など徹底解説!
- おーいお茶俳句に入選するコツ
- 俳句の腕試し!応募できる俳句コンクール情報サイトまとめ
- 俳句大会では「季節のルール」がある
- 俳句大会で目にする「入選、入賞、優秀賞、第一席」の違い
- 俳句大会の「落選句」は「既発表」?「未発表」?
- 俳句大会の情報を紹介している本
- 俳壇の入選確認の簡単な方法
- 全国の俳句大会
- 天下布句 岐阜俳句大会に入選!巨大な「のぼり」を見に行きました
- 新聞の俳壇で入選確率を上げる方法
- 読売や朝日新聞へ、俳句を投句する方法
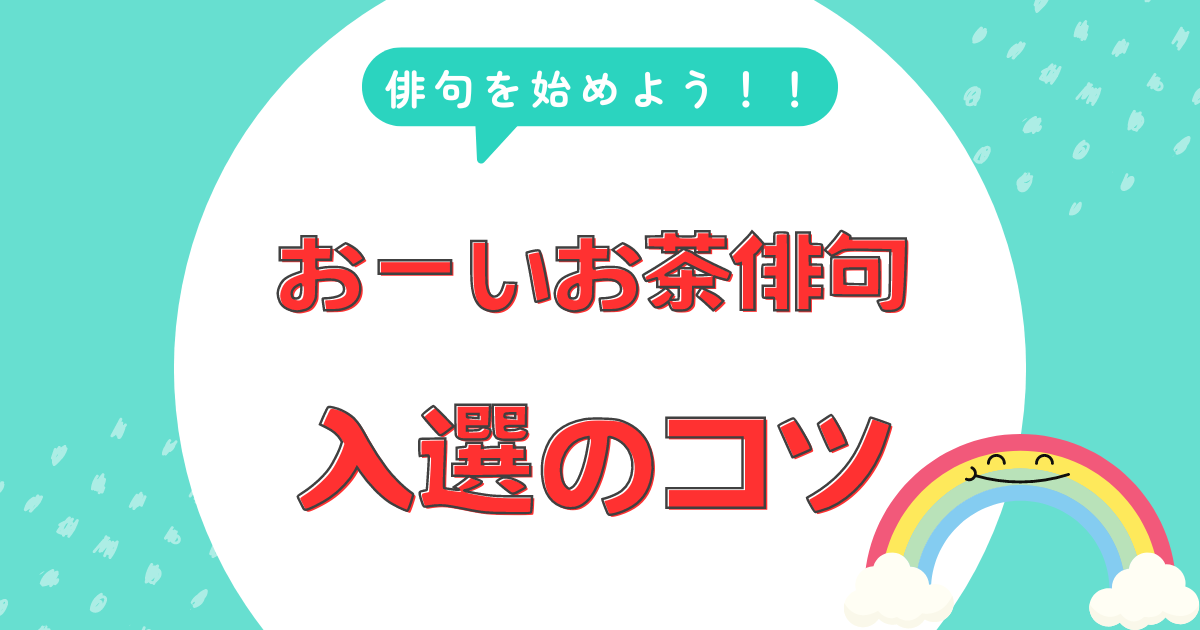

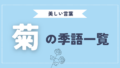
コメント