季語の中には、子季語として歳時記に掲載されているものもありますが、その意味が詳しく説明されていない場合もあります。子季語の意味を知ることで、より良い俳句を作ることができるので、今回はよく使われる主季語と子季語の意味をまとめてみました。
「秋」の季語
下の表では、一番上の「秋」が主季語、その下に並んでいるものが子季語になります。
子季語は、主季語の関連語、という考えで大丈夫です。
《 秋 》
| 秋(あき) | 夏の次の季節。立秋から立冬の前日まで。わが国では俗に九・十・十一の三か月。 |
| 白秋(はくしゅう) | 五行説において、秋の色は「白」であることから、「秋」の異称が「白秋」となった。 |
| 白帝(はくてい) | 五行説で、白を西・秋にあてるところから。西方の神。秋をつかさどる神。 |
| 素秋(そしゅう) | 秋のこと。「素」は白の意。五行説で白色を秋に配するところから。 |
| 高秋(こうしゅう) | 秋は晴れ渡って空の高く見えることから。 |
| 商秋(しょうしゅう) | 中国の音楽で使われる階名は、五音 (ごいん) の 宮(きゅう)、商(しょう)、角(かく)、 徴(ち)、 羽(う)からなるが、「商」は四季では秋にあたる。 |
| 金秋(きんしゅう) | 五行 (古代中国に端を発する自然哲学の思想) 。万物は火・水・木・金・土の5種類の元素からなり、金が季節では秋にあたるところから。 |
| 凛秋(りんしゅう) | 秋のこと。「凜」は、字義として「寒い、すずしい」という意味がある。 |
| 爽節(そうせつ) | 秋のこと。空気が澄明で気持ちの季節のこと。 |
| 収成(しゅうせい) | 秋のこと。秋の取り入れ。秋の収穫の意味がある。 |
| 三秋(さんしゅう) | 秋季の3か月。 |
| 九秋(きゅうしゅう) | 秋の90日間のこと。 |
秋について
歳時記を開くと、「秋」を表す言葉がたくさん並んでいますね。「白秋」「素秋」「金秋」「九秋」など、美しい言葉が並びますが、これらは単に「秋」という意味だけでなく、それぞれが微妙に異なるニュアンスを持っています。
例えば、「九秋」は秋の90日間を指し、時間の経過を強調する言葉です。「金秋」は、古代中国に端を発する自然哲学の思想から生まれた言葉です。このように、それぞれの言葉には、漢字一つ一つに意味があり、作者の想いをより深く表現するための道具として使われています。
これらの言葉が生まれた背景や、使われる状況を理解することで、あなたの俳句は、より奥深く、豊かなものになるでしょう。例えば、「高秋」と「爽節」はどちらも秋を表しますが、「高秋」は澄んだ秋の大気をイメージし、「爽節」はさわやかな秋の季節をイメージします。このように、言葉の選び方一つで、全く異なる情景が浮かび上がってくるのです。
季語は、単なる言葉の羅列ではありません。自然の美しさや、人の心の動きを表現するための、繊細な道具なのです。ですから、季語を使う際には、必ず辞書や歳時記で意味を調べ、その言葉が持つイメージをしっかりと掴むようにしましょう。
『四季を語る季語』は、全ての子季語の意味を網羅した本ですので、季語選びの強い味方になるはずです。
「秋」関連の俳句
「秋」を使った俳句にはこのようなものがあります。俳句作りの参考になさってください。
「秋」の例句
| 「生きている」自分を探す秋の景 佐古澄江 | - |
| 「革命」のピアノ鳴りやまずホテルの秋 川崎幸子 | - |
| あざやかに昃るを秋の喪としたり 松澤昭 | 松澤昭の句集(Amazon) >> |
| 秋の句をしるしての筆なよやかに 能村登四郎 | 能村登四郎の句集(Amazon) >> |
「白秋」の例句
| 白秋の風の筋目に橋をおく 村井和一 | - |
「九秋」の例句
中世の秋やひとりのけものみち 藤原月彦
秋の句をしるしての筆なよやかに 能村登四郎
季語探しの強い味方『四季を語る季語』
季語を選ぶ際には、様々な要素を考慮する必要がありますが、従来の歳時記には子季語の意味が詳しく記載されていないため、適切な季語を選ぶのが難しいという課題がありました。
『四季を語る季語』は、全ての子季語の意味を網羅することで、この課題を解決し、よりスムーズな季語選択を可能にします。
↓↓下の本がそうです。
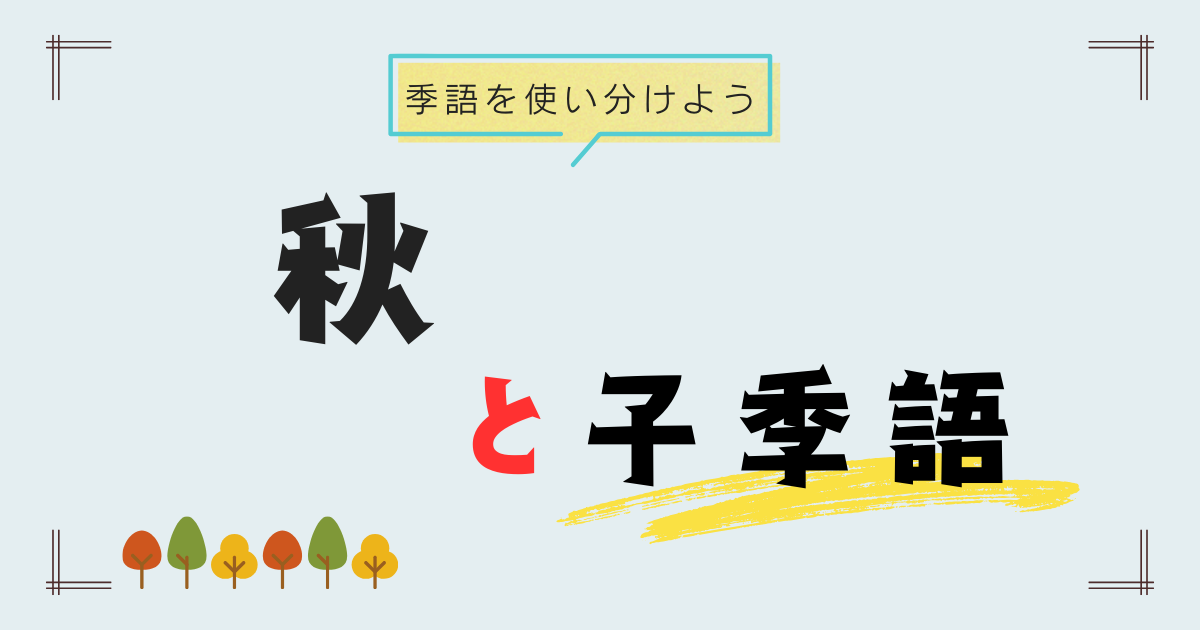

コメント