「こおる」という言葉を漢字で書く場合、「氷る」と「凍る」の2種類があります。これらの漢字にはそれぞれ異なるニュアンスがあり、特に俳句の世界ではこの使い分けが重要になります。
ここでは「氷る」と「凍る」の違いのほかに、「氷る・凍る」に関連する言葉を紹介します。
「氷る」と「凍る」の意味の違い
- 氷る(こおる):「水」が固体になり「氷」になることを指します。水そのものが凝固する様子を表す際に用いられます。
- 凍る(こおる):「水」だけでなく、水以外のものや、空気、感情などが冷え固まる様子全般を指します。より広範な事象に対して使われるのが特徴です。
季語に見る使い分け
この違いは、俳句の季語を見るとよくわかります。
「氷」のつく季語
「氷瀑(ひょうばく)」「厚氷(あつごおり)」「氷湖(ひょうこ)」など、「氷」のつく季語は、いずれも水が凍ってできた「氷」の状態を具体的に示しています。
「凍」のつく季語
一方で、「凍滝(いてだき)」「凍土(いてつち)」「凍雀(いてすずめ)」などは、水だけでなく、大地や生き物など、さまざまなものが寒さで冷え固まった様子を表します。
例外的な「氷る」の使い方
しかし、中にはこの使い分けの原則から外れているように見える季語も存在します。 たとえば、「月氷る(つきこおる)」や「鐘氷る(かねこおる)」です。
- 月氷る:澄み切った冬の空に、鏡のようにくっきりと浮かぶ月の様子を指します。月そのものが凍っているわけではなく、大気の冷え切った様子を「氷る」という言葉で表現することで、その清冽な寒さを際立たせています。
- 鐘氷る:冬の澄んだ空気の中を、寒々と響く鐘の音を指します。鐘の音が凍るという比喩的な表現によって、冬の厳しい冷気を伝える季語です。
これらの季語は、水分を含む大気を通して見える月や、響く音に「氷る」という言葉をあてることで、より感覚的に寒さや静寂を表現していると言えます。
「氷る・凍る」について
「氷る・凍る」の文語
口語の「氷る(こおる)・凍る(こおる)」は、文語形では、読み方が変わり「氷る(こほる)・凍る(こほる)」になります。
文語「氷る・凍る(こほる)」の活用
氷る・凍る
四段活用
| 未然形 | 連用形 | 終止形 | 連体形 | 已然形 | 命令形 |
| -ら | -り | -る | -る | -れ | -れ |
「氷る・凍る」を使った俳句
氷る
| いつもかすかな鳥のかたちをして氷る 対馬康子 | 対馬康子の句集(Amazon) >> |
| 傘を刺す地の茫々と氷る前 松澤昭 | 松澤昭の句集(Amazon) >> |
凍る
| クロイツェル・ソナタ折り鶴凍る夜 浦川聡子 | 浦川聡子の句集(Amazon) >> |
| 今年また山河凍るを誰も防がず 細谷源二 | - |
俳句作品は、『歳時記』という本に多く掲載されています。作品を学びたい方は、ぜひ購入を検討してみてください。
Amazonで歳時記を見る >>
「凍」の関連語
「凍」という漢字は、「こおる」以外にも様々な関連語があります。
- 凍る(こおる):送り仮名は「る」。
- 凍てる(いてる):送り仮名は「てる」。
- 凍える(こごえる):送り仮名は「える」。
- 凍みる(しみる):送り仮名は「みる」。
これらの言葉は、同じ「凍」という漢字を使いますが、それぞれ異なる意味やニュアンスを持っています。
送り仮名を正しく使うことで、読み手の誤解を防ぎ、意図した通りの情景や感情を伝えることができます。
「凍る・凍てる・凍える・凍みる」の意味
| 言葉 | 意味 |
| 凍る(こおる) | 特に水が低温のため凝結して固体の状態になる。 |
| 凍てる(いてる) | こおる。こおりつく。 |
| 凍える(こごえる) | 寒さのために、からだが冷えきって固くなり、自由がきかなくなる。 |
| 凍みる(しみる) | 寒さが厳しくて、こおるように感じる。 |
「凍る・凍てる・凍える・凍みる」の文語と活用
| 言葉 | 文語 | 活用 |
| 凍る(こおる) | 凍る(こほる) | 四段活用 |
| 凍てる(いてる) | 凍つ(いつ) | 下二段活用 |
| 凍える(こごえる) | 凍ゆ(こごゆ) | 下二段活用 |
| 凍みる(しみる) | 凍む(しむ) | 上二段活用 |
文語の「凍る・凍つ・凍ゆ・凍む」を使った俳句
| 文語 | 例句 | 補足 |
|---|---|---|
| 凍る(こほる) | 凍る日の陣痛の皺鶏卵に 小檜山繁子 | 「凍る」の連体形 |
| 凍つ(いつ) | 帆を固く閉ざして帆立貝凍つる 山本一糸 | 「凍つ」の連体形 |
| 凍ゆ(こごゆ) | 凍えたる子の手が包む寒卵 木幡忠文 | 「凍ゆ」の連用形 |
| 凍む(しむ) | 快晴の糸張つてゐる凍み渡り 清水逍径 | 「凍む」の連用形 |
俳句作品は、『歳時記』という本に多く掲載されています。作品を学びたい方は、ぜひ購入を検討してみてください。
Amazonで歳時記を見る >>
関連記事
この記事で言葉の違いを学んだように、俳句には他にも似て非なる言葉が数多くあります。
あなたの句をさらに磨き上げるために、他の言葉の使い分けをぜひチェックしてみてください。
- 俳句における「ある・おる・いる」の使い分け
- 俳句における「とき」「時」の使い分けから、「時間」の言葉まで
- 俳句における「上る・上がる・上げる」の使い分け
- 俳句における「出る・出来る」の使い方
- 俳句における「初」「始」の使い分け
- 俳句における「去ぬ」「去る」について
- 俳句における「合う・会う・逢う・遭う」の使い分け
- 俳句における「変わる・変える」の使い分け
- 俳句における「川・河・江」の使い分け
- 俳句における「影・陰・蔭・翳」の使い分け
- 俳句における「日・陽」の使い分け
- 俳句における「暖かい・温かい」の使い分け
- 俳句における「氷る・凍る」の使い分け
- 俳句における「答える・応える」の使い分け
- 俳句における「聞く・聴く・訊く」の使い分け
- 俳句にみる「咲かぬ」「咲きぬ」の違い
- 俳句にみる「来ぬ(こぬ)」と「来ぬ(きぬ)」の違い
間違えやすい言葉について書かれた本
今回は、わずかな違いで意味が変わる言葉について解説しました。
ここで紹介する本は、同じ読み方なのに意味が違う漢字を、用例を交えながらわかりやすく解説しています。
一冊手元にあるだけで、俳句創りの表現力が豊かになるのを感じられるはずです。
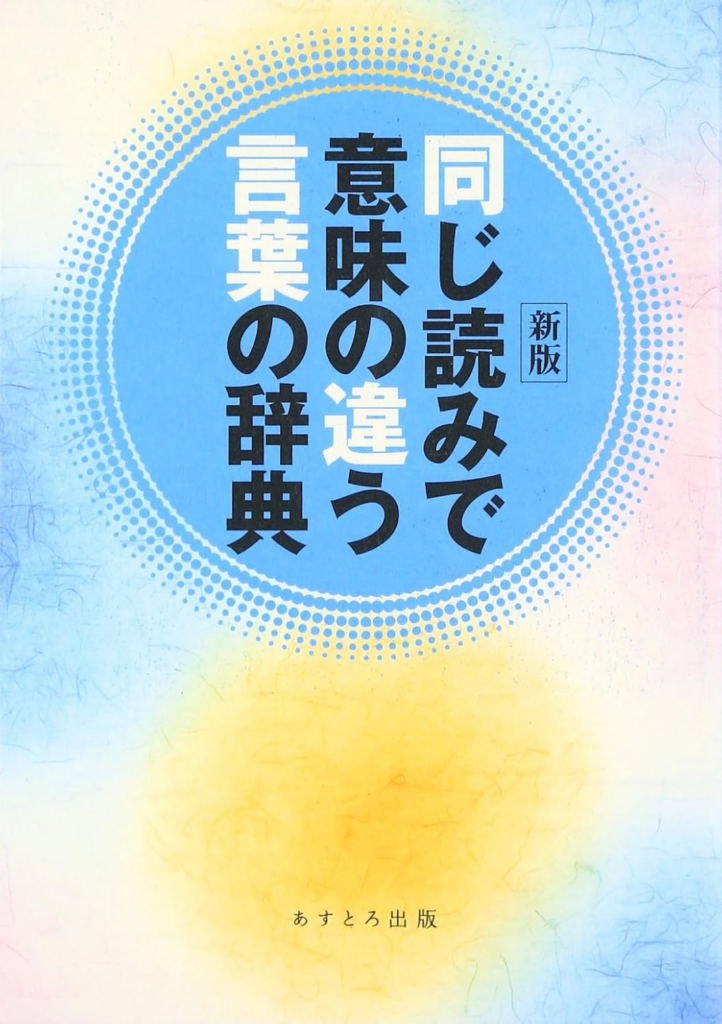


コメント