俳句では、言葉一つひとつが持つニュアンスを大切にすることで、句に込められた情景や心情がより深く伝わります。
「ある・おる・いる」も、私たちが日常的に使う言葉ですが、俳句の世界ではその使い分けに独特なルールがあります。
ここでは、それぞれの言葉が持つ意味や、俳句で使う際の注意点を分かりやすく解説します。
「ある・おる・いる」の漢字
「ある・おる・いる」は一般的に平仮名で表記されますが、漢字表記を知っていると、それだけで何となく意味が分かります。
- ある(在る)
- おる(居る)
- いる(居る)
「ある・おる・いる」の文語と意味
「ある・おる・いる」は、俳句の世界では文語に置き換えて表現されることが一般的です。
| 口語 | 文語 | 意味と使い分け |
| ある | あり | 「その存在」を表す。物体や事象が存在することそのものに焦点が当たります。 |
| おる | をり | 「ある状態が継続している」ことを表す。時間の経過とともに状態が続いている様子を強調します。 |
| いる | ゐる | 「ある状態が変化せず安定している」ことを表す。動きがなく、その場にじっと留まっている状態を表現するのに適しています。 |
これらの細かなニュアンスの違いを意識して使い分けることで、一句の奥行きがぐっと深まります。
たとえば、「水流れあり」「水流れをり」「水流れゐる」の3つの表現を比べてみましょう。
- 水流れあり:単純に「水の流れがある」という事実を述べています。
- 水流れをり:水の流れが「ずっと継続している」様子を伝えています。
- 水流れゐる:水の流れが「変わらずそこにある」という安定した状態を表しています。
このように、どの言葉を選ぶかで、作者が見ている風景や感じている時間が異なってくるのが面白い点です。
文語「あり・をり・ゐる」の活用
「あり・をり・ゐる」を俳句で使うときは、活用にも注意が必要です。
| 文語 | 活用 |
| あり | ラ変活用(ら・り・り・る・れ・れ) |
| をり | ラ変活用(ら・り・り・る・れ・れ) |
| ゐる | 上一段活用(ゐ・ゐ・ゐる・ゐる・ゐれ・ゐよ) |
「ゐる(居る)」の連用形が名詞化した「ゐ(居)」も、そこに居ることや座ることを意味する言葉として使われることがあります。
文語「あり・をり・ゐる」の俳句
実際に「あり」「をり」「ゐる」がどのように使われているか、例句を見てみましょう。
「あり」の例句
| かなかなや昔一揆のありし里 池田暎子 | 池田暎子の句集(Amazon) >> |
| 驚きは真夜中にあり恋の猫 佐藤邦子 | 佐藤邦子の句集(Amazon) >> |
「をり」の例句
| 清水のむかたはら地図を拡げをり 高野素十 | 高野素十の句集(Amazon) >> |
| かたつむり黙って墓を守りをり 中嶋秀子 | 中嶋秀子の句集 (Amazon) >> |
| 庭寂し今はドクダミ咲いてをり 篠田清美 | 篠田清美の句集(Amazon) >> |
| 春夕焼砂場のシャベル光りをり 小河原節子 | 小河原節子の句集(Amazon) >> |
「ゐる」の例句
| おいと肩押されて桃の咲いてゐる 大石雄鬼 | 大石雄鬼の句集 (Amazon) >> |
| うつろの心に眼が二つあいてゐる 尾崎放哉 | 尾崎放哉の句集 (Amazon) >> |
| 錆びてゐる開かずの門の花茨 堺玲子 | 堺玲子の句集(Amazon) >> |
俳句作品は、『歳時記』という本に多く掲載されています。作品を学びたい方は、ぜひ購入を検討してみてください。
Amazonで歳時記を見る >>
文語「あり・をり・ゐる」の表現例
「あり」「をり」「ゐる」を使った、表現例も見てみましょう。
「あり」の表現例
- 〜ありき(〜があった) 過去
- 〜ありし(〜がある!) 強意
- 〜ありて(〜があって、それから) 継起
- 〜ありにけり(〜があったのだ) 気づき・詠嘆
- 〜ありけり(〜があるのだ) 気づき
- 〜ありぬ(〜が確かにあった) 強意
- 〜ありぬべし(〜がきっとあったに違いない) 推量
「をり」の表現例
- 〜をりし(〜いる!) 強意
- 〜をりて(〜いて、それから) 継起
「ゐる」の表現例
- 〜ゐし(〜いる!) 強意
- 〜ゐて(〜いて、それから) 継起
- 〜ゐたり(〜している) 存続
これらの使い分けを理解することで、一句一句が持つ時間の流れや情景をより繊細に表現できるようになります。ぜひ、あなたの俳句づくりに活かしてください。
関連記事
この記事で言葉の違いを学んだように、俳句には他にも似て非なる言葉が数多くあります。
あなたの句をさらに磨き上げるために、他の言葉の使い分けをぜひチェックしてみてください。
- 俳句における「ある・おる・いる」の使い分け
- 俳句における「とき」「時」の使い分けから、「時間」の言葉まで
- 俳句における「上る・上がる・上げる」の使い分け
- 俳句における「出る・出来る」の使い方
- 俳句における「初」「始」の使い分け
- 俳句における「去ぬ」「去る」について
- 俳句における「合う・会う・逢う・遭う」の使い分け
- 俳句における「変わる・変える」の使い分け
- 俳句における「川・河・江」の使い分け
- 俳句における「影・陰・蔭・翳」の使い分け
- 俳句における「日・陽」の使い分け
- 俳句における「暖かい・温かい」の使い分け
- 俳句における「氷る・凍る」の使い分け
- 俳句における「答える・応える」の使い分け
- 俳句における「聞く・聴く・訊く」の使い分け
- 俳句にみる「咲かぬ」「咲きぬ」の違い
- 俳句にみる「来ぬ(こぬ)」と「来ぬ(きぬ)」の違い
間違えやすい言葉について書かれた本
似ているようで全く違う言葉の機微を理解することは、創作の幅を広げる鍵となります。
そんな言葉の探求を助けてくれる本が、『同じ読みで意味の違う言葉の辞典』です。
一冊手元にあるだけで、俳句創りの表現力が豊かになります。
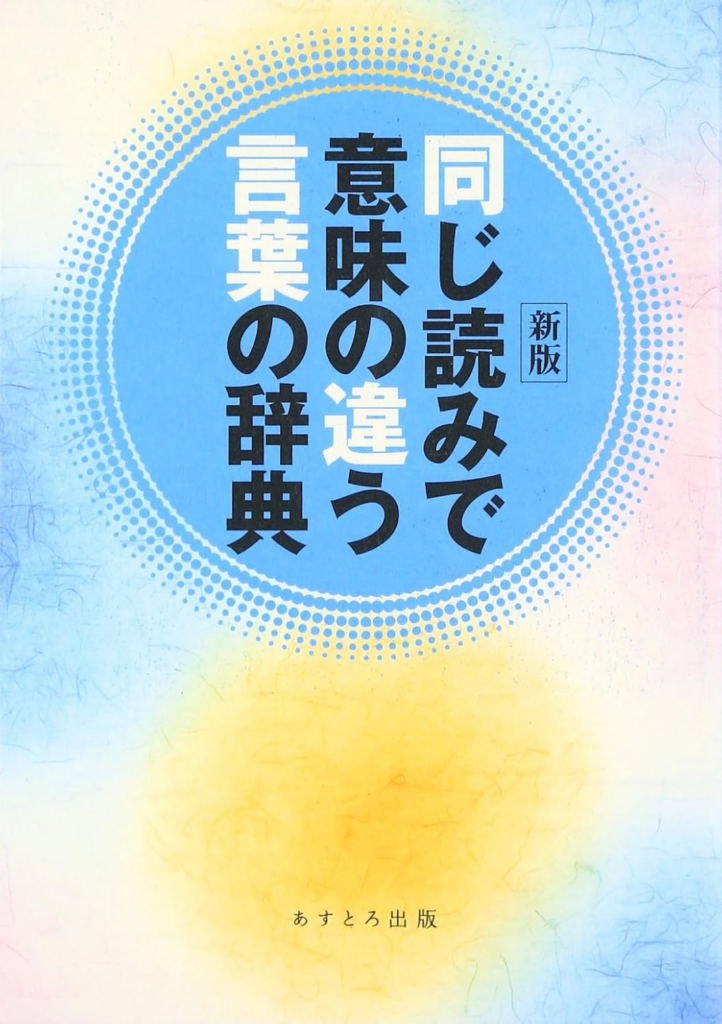


コメント