俳句や文章を書く際、「とき」と「時」のどちらを使うべきか迷ったことはありませんか? この二つの表記は、それぞれ異なるニュアンスを持っています。
この記事では、その使い分けを解説するとともに、俳句で使われる「時」を含む言葉や、昔の時間の呼び方についてもご紹介します。
「とき」「時」の使い分け
まず基本的な使い分けから見ていきましょう。
- 「とき」:「場面」や「状況」を表す場合にひらがなで表記します。
- 例:「ケガをしたときは安静にしましょう」
- 例:「急ぐときはタクシーを使います」
- 例:「彼女が来たときは案内してください」
- 「時」:「時間」や「時期」といった具体的な概念を表す場合に漢字で表記します。
- 例:「今がまさに買い時だ」
- 例:「時の権力者」
- 例:「昨日会った時は元気だった」
「とき」と「時」を使った俳句
「とき」
| あお向きしとき月ありぬ一つの月 金子兜太 | 金子兜太の句集 (Amazon) >> |
| あるときは船より高き卯浪かな 鈴木真砂女 | 鈴木真砂女の句集 (Amazon) >> |
「時」
| 一人居の雛を飾りて時たぐる 堺玲子 | 堺玲子の句集(Amazon) >> |
| あの時のあの顔のまくわうり らふ亜沙弥 | らふ亜沙弥の句集 (Amazon) >> |
| 時の日の来し方思案今日を過ぐ 堺玲子 | 堺玲子の句集(Amazon) >> |
俳句で使われる「時」を含む言葉
俳句の世界で使われる言葉の中には、「時」という漢字を含むものが多くありします。
これらの言葉が持つ意味を感じながら使うことで、一句の情景がより豊かに、そして繊細に表現できます。
- 目借り時(めかりどき):春の季語。農作業が本格的に始まる時期。猫の目のように忙しいことから、少し休む間を「猫が目を借りる」と言ったことに由来するともいわれています。
- 木の芽時(きのめどき):春の季語。春になって木々の芽が一斉にふくらみ始めるころ。
- 花時(はなどき):春の季語。桜の花が咲く盛り。
- 黄昏時(たそがれどき):秋の季語。「誰そ、彼(たそかれ)」と、夕暮れで顔が見分けられない時間帯を意味します。
- 田植時(たうえどき):夏の季語。田植えの時期。
- 夕暮れ時(ゆうぐれどき):特定の季節に限定されない季語(傍題によっては冬の季語)。日が暮れて薄暗くなる時間帯。
- 雀色時(すずめいろどき):秋の季語。スズメの羽色のような、くすんだ赤茶色に染まる夕暮れ時。
どれも、「時間」や「時期」を指す、美しい言葉ですね。
俳句で「時(時刻)」を表現する言葉
昔の俳句を鑑賞していると、現代の「午前・午後」や「1時・2時」とは違う、独特な時間の呼び方に出会うことがあります。こうした言葉の意味を知ることで、作者が詠んだ時間帯の情景に深く感情移入できるようになります。
下の表は、昔から使われている時間の言葉をまとめたものです。今でも使える言葉はあります。
ぜひ、鑑賞するときだけでなく、俳句を創るときにもご利用ください。
空の明るさの変化を表す言葉
表の右上にある「暁(あかつき)、東雲(しののめ)、曙(あけぼの)、朝朗(あさぼらけ)」は、正確な時間があるわけではなく、空の明るさの変化によって名前が刻々と変わっていきます
- 暁(あかつき):夜半過ぎから夜明け近くの、まだ暗い頃。
- 東雲(しののめ):夜が明ける直前で、東の空がわずかに明るくなり始めた頃。
- 曙(あけぼの):夜がほのぼのと明け始め、明るさが広がっていく頃。
- 朝朗(あさぼらけ):夜が明けて、物がようやくはっきりと見え始める頃。
これらの言葉は、時間だけでなく、その時間特有の雰囲気や情感を伝えるのに役立ちます。
「子(ね)の刻」や「暁9つ」といった言葉は、昔の俳句を鑑賞する際に目にするので役立ちます。こうした言葉の意味を理解することで、作品の背景にある時代や文化にも思いを馳せることができるでしょう。
関連記事
この記事で言葉の違いを学んだように、俳句には他にも似て非なる言葉が数多くあります。
あなたの句をさらに磨き上げるために、他の言葉の使い分けをぜひチェックしてみてください。
- 俳句における「ある・おる・いる」の使い分け
- 俳句における「とき」「時」の使い分けから、「時間」の言葉まで
- 俳句における「上る・上がる・上げる」の使い分け
- 俳句における「出る・出来る」の使い方
- 俳句における「初」「始」の使い分け
- 俳句における「去ぬ」「去る」について
- 俳句における「合う・会う・逢う・遭う」の使い分け
- 俳句における「変わる・変える」の使い分け
- 俳句における「川・河・江」の使い分け
- 俳句における「影・陰・蔭・翳」の使い分け
- 俳句における「日・陽」の使い分け
- 俳句における「暖かい・温かい」の使い分け
- 俳句における「氷る・凍る」の使い分け
- 俳句における「答える・応える」の使い分け
- 俳句における「聞く・聴く・訊く」の使い分け
- 俳句にみる「咲かぬ」「咲きぬ」の違い
- 俳句にみる「来ぬ(こぬ)」と「来ぬ(きぬ)」の違い
間違えやすい言葉について書かれた本
俳句の奥深さは、言葉のわずかな違いが表現を大きく変える点にありますよね。
そんな言葉の探求を助けてくれる本が、『同じ読みで意味の違う言葉の辞典』です。
一冊手元にあるだけで、より豊かな俳句創りができるはずです。
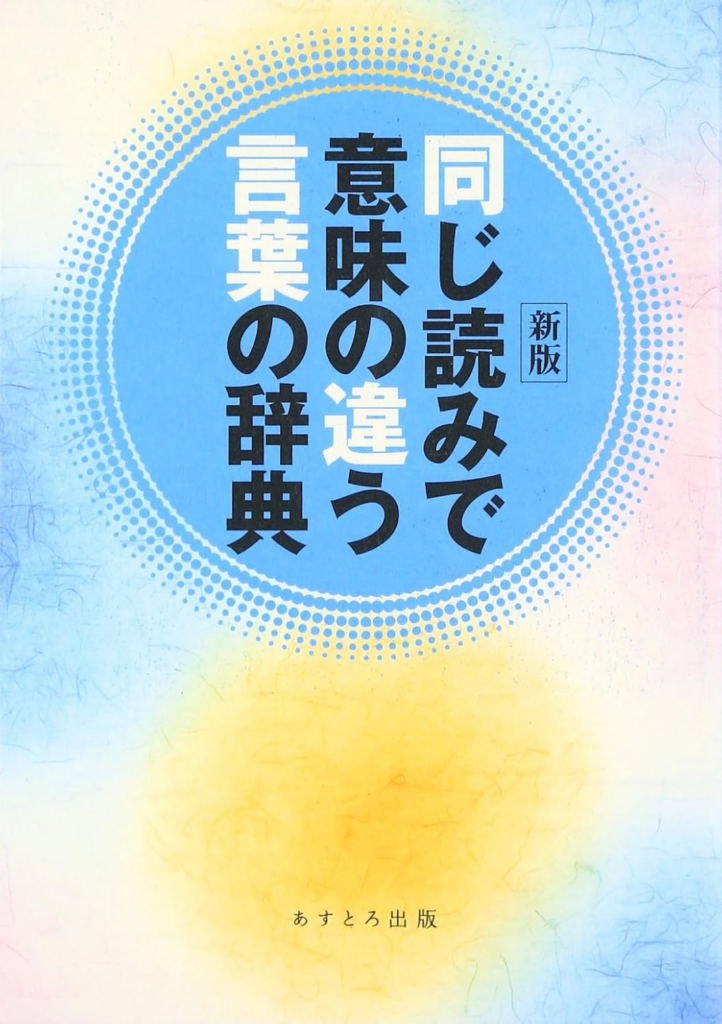


コメント