俳句や短歌を鑑賞していると、「咲かぬ」「咲きぬ」という言葉を目にすることがありますね。
一文字違いですが、その意味はまったく異なります。
誤解なく作品を味わうために、この二つの言葉の正しい意味と使い方を解説します。
「咲かぬ」の意味
「咲かぬ」は、花が咲いていない状態を表します。現代語の「咲かない」と同じ意味です。
これは、「咲く」という動詞の未然形「咲か」に、打消しの助動詞「ず」の連体形「ぬ」が接続してできた形です。
- 構造: 「咲か(未然形)」+「ぬ(打消しの助動詞「ず」の連体形)」
- 意味: 咲かない
- 使い方:
- 名詞を修飾する:「咲かぬ花」のように、直後にくる名詞を打ち消す形で使われることが多いです。
- 文の終わりで使う:文の結びとして使うときは「花が咲かず。」のように、打消しの助動詞「ず」をそのまま使います。
「咲かぬ」を使った俳句
| 桐まだ咲かぬ山国山人と酔うて 金子兜太 | 金子兜太の句集(Amazon) >> |
| 戯れには咲かぬ茄子をじつとめづ 清塚和風 | |
| 大輪は咲かず小菊の数多彩 中西明子 | 中西明子の句集 (Amazon) >> |
これらの句では、「桐の花はまだ咲かない」や「気軽には咲かない茄子の花」「大輪の花は咲かないものだ」といった、花が咲いていない様子が表現されています。
「咲きぬ」の意味
一方、「咲きぬ」は、花がすでに咲いた状態を表します。現代語の「咲いた」と同じ意味です。これは、「咲く」の連用形「咲き」に、完了の助動詞「ぬ」が接続してできた形です。
- 構造: 「咲き(連用形)」+「ぬ(完了)」
- 意味: 咲いた
- 使い方:
- 主に文の結びで使われます。「花が咲きぬ。」のように、花が咲き終わったことを強調します。
「咲きぬ」を使った俳句
| かたくりや希望は別の名で咲きぬ 五十嵐秀彦 | 五十嵐秀彦の句集 (Amazon) >> |
| 手拭を噛めどあやめの濃く咲きぬ 鳴戸奈菜 | 鳴戸奈菜の句集 (Amazon) >> |
これらの句では、希望が「別の名で咲いた」と表現されたり、あやめが「濃く咲いた」と描写されており、花が咲いたことを感動とともに伝えています。
まとめ
二つの言葉を混同してしまうと、作者が伝えたかった情景を正しく読み取ることができません。
- 咲かぬ → 咲かない(打消し)
- 咲きぬ → 咲いた(完了)
このように、「ぬ」の直前の形(「咲か」か「咲き」か)を意識して読むだけで、俳句の世界がより深く楽しめるようになります。
ぜひ、ご自身の俳句作りや鑑賞に役立ててみてください。
「旧仮名・文語・文法を勉強したい」あなたへ
このページでは、「咲かぬ」「咲きぬ」の違いを紹介しました。
著書『1週間でマスター!俳人のための旧仮名・文語入門』では、俳句を「昔の言葉」で作れるように、手順を紹介しています。
「文語・旧仮名・文法」をマスターする最短のルートです。
ぜひ、こちらも参考になさってください。
関連記事
この記事で言葉の違いを学んだように、俳句には他にも似て非なる言葉が数多くあります。
あなたの句をさらに磨き上げるために、他の言葉の使い分けをぜひチェックしてみてください。
- 俳句における「ある・おる・いる」の使い分け
- 俳句における「とき」「時」の使い分けから、「時間」の言葉まで
- 俳句における「上る・上がる・上げる」の使い分け
- 俳句における「初」「始」の使い分け
- 俳句における「去ぬ」「去る」について
- 俳句における「合う・会う・逢う・遭う」の使い分け
- 俳句における「変わる・変える」の使い分け
- 俳句における「川・河・江」の使い分け
- 俳句における「影・陰・蔭・翳」の使い分け
- 俳句における「日・陽」の使い分け
- 俳句における「暖かい・温かい」の使い分け
- 俳句における「氷る・凍る」の使い分け
- 俳句における「答える・応える」の使い分け
- 俳句における「聞く・聴く・訊く」の使い分け
- 俳句にみる「咲かぬ」「咲きぬ」の違い
- 俳句にみる「来ぬ(こぬ)」と「来ぬ(きぬ)」の違い
間違えやすい言葉について書かれた本
俳句の奥深さは、言葉のわずかな違いが表現を大きく変える点にありますよね。
そんな言葉の探求を助けてくれる本が、『同じ読みで意味の違う言葉の辞典』です。
一冊手元にあるだけで、より豊かな俳句創りができるはずです。
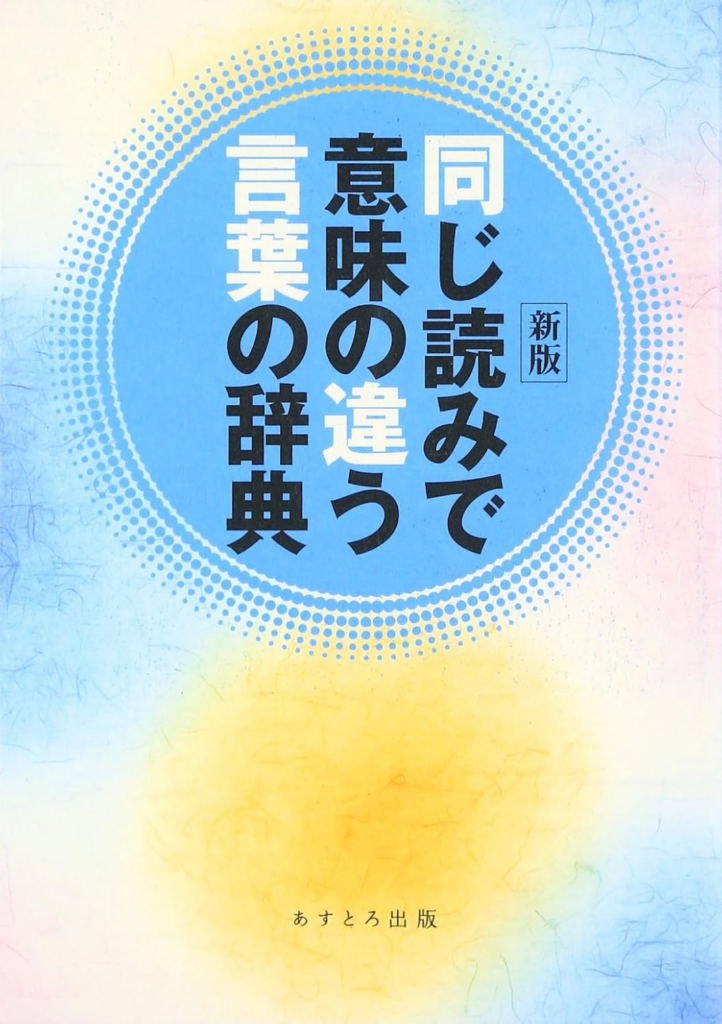

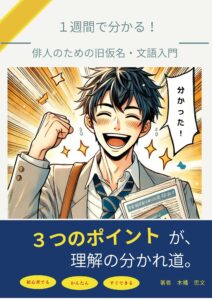

コメント