「句会」と聞くと、少し難しそうに感じるかもしれませんね。でも、難しく考える必要はありません。句会は、俳句を通じてみんなで楽しく交流する、昔から続く日本の文化です。
ここでは、「句会って一体何?」「何をするの?」といった、誰もが最初に抱く疑問にお答えします。
句会って何だろう?
句会とは、俳句を作った人たちが集まって、お互いの作品を読み合い、感想を言い合う集まりです。
一人で俳句を作って楽しむのも良いですが、句会に参加することで、あなたの俳句を他の人がどう感じるのかを知ることができます。また、色々な人の作品に触れることで、「こんな表現方法があったんだ!」と、新しい発見がたくさん見つかります。
初心者の方にとっては、俳句の経験者からアドバイスをもらったり、自分の作品の良い点を見つけてもらったりする、とても良い機会になります。
句会の種類を見てみよう
句会にはいくつか種類があり、それぞれ違った楽しみ方があります。
- 投句(とうく) 一番一般的な形式です。事前に俳句をいくつか作って持ち寄り、作者の名前を伏せた状態で提出します。提出する句の数は、その句会によって様々です。
- 吟行(ぎんこう) 公園や名所旧跡など、自然の中にみんなで出かけて、その場で見た景色や感じたことを俳句に詠みます。五感を使って俳句を作るので、その場の雰囲気をより楽しめます。
- 題詠(だいえい) 「桜」や「海」など、あらかじめ決められたテーマ(題材)に合わせて俳句を作ります。同じお題でも、人によって全く違う表現が生まれるのが面白いところです。
句会の一般的な流れ
初めて句会に参加する方でも安心して楽しめるよう、当日の流れを追ってみましょう。この流れを頭に入れておけば、きっとスムーズに句会に参加できます。
- 開会 司会の方が会の始まりを告げます。
- 自己紹介 初参加の方がいる場合は、軽く自己紹介をします。自己紹介といっても、堅苦しいものではありません。お互いの顔と名前を知って、リラックスした雰囲気を作るための時間です。
(句会の中では「これは○○さんの作品です」というように、参加者の名前が頻繁に出るので、自己紹介の時に参加者の名前を紙に書いておくと便利です。) - 投句(とうく) 事前に作ってきた俳句を提出します。句の数は句会によって違いますが、だいたい5句前後です。
- 清記(せいき) 提出された俳句は、作者の名前がわからないように書き直されます。誰がどの句を作ったか、誰も知らない状態で選ぶのが句会のルールです。
- 選句(せんく) 清書されたすべての句の中から、自分の心に響いた句をいくつか選びます。
- 講評(こうひょう) 選ばれた句が読み上げられ、選んだ人が「なぜこの句を選んだのか」を説明します。この時間が句会の醍醐味!他の人の視点や感性から、たくさんの発見があるはずです。
(初めての時は、何を言えばよいのか分からないと思います。下に簡単な鑑賞のポイントを紹介しているので、参考になさってください。) - 閉会 最後に、その日の句会を振り返り、感想などを共有して終了となります。
句会ってどんな雰囲気? 初めて参加するあなたへ
「句会」と聞くと、なんだか難しそう、堅苦しそう…そんな風に思っていませんか?ご安心ください。句会は、俳句が好きという共通の思いを持つ仲間が集まる、とても温かい雰囲気の場です。
よくある不安にお答えします
- どんな人が参加してるの? 年齢も職業も様々です。プロの俳人から初心者まで、いろいろな方がいます。みんな「俳句が好き」という気持ちで集まっているので、和気あいあいとした雰囲気です。
- どんな服装で行けばいい? 服装に決まりはありません。普段着で大丈夫です。着物でなければいけないのでは?と心配する方もいますが、ほとんどの方が普段着で参加しています。
- 何を持っていけばいい? ノートと筆記用具は必須です。加えて、季語を調べたり、難しい言葉を調べたりするのに役立つ歳時記や電子辞書、またはスマートフォンがあると便利です。
珍しい季語では、歳時記や辞書にも意味が載っていないことがあります。そんな時は、こちらの「季語検索ページ」で「平仮名」で検索をすると、大抵の季語の意味は調べられます。
句会で役立つマナー
句会を気持ちよく楽しむために、少しだけ意識しておきたいことがあります。
- 時間厳守 句会は開始時間が決まっているので、遅れないようにしましょう。
- 携帯電話はマナーモード 句会中は、携帯電話の電源を切るか、マナーモードに設定しておきましょう。
- 人の話を丁寧に聞く 他の人が話しているときは、話を遮らず、最後まで聞きましょう。
句会でよく聞く言葉
句会でよく使われる、覚えておくと便利な言葉をまとめました。
| 言葉 | 意味 |
| 投句(とうく) | 自分の作った句を提出すること。 |
| 清記(せいき) | 作者名が分からないように、句を書き写すこと。 |
| 選句(せんく) | 他の人の句の中から、自分が良いと思う句を選ぶこと。 |
| 披講(ひこう) | 句会で提出された作品を、読み上げること。 |
| 講評(こうひょう) | 他の人の句について、自分の意見や感想を述べること。 |
| 季題(きだい) | 季語を題材にした句のこと。 |
| 兼題(けんだい) | 句会のテーマとして指定されたお題。特定の季語やテーマに基づいて俳句を作成します。 |
| 自由題(じゆうだい) | 句会で特定のお題や季語が決まっていない自由なテーマで作る俳句。 |
まれに「雑詠・題詠・当季雑詠・兼題・席題・属目」といった言葉も出ます。これらの意味はこちらで紹介しています。
句会に参加するメリット
句会は、俳句を通じて新しい発見や成長を促す場です。得られるメリットは沢山あるので紹介します。
俳句の腕を磨ける
- 多様な意見が聞ける: 自分の作品について、参加者から、様々な角度からの意見が聞けるので、勉強になりますし、その意見を参考に俳句を作ることで表現の幅が広がります。俳句はわずか17音に収めるため、言いたいことが他の人に伝わらないことがよくあります。こういう表現は伝わらないのか、と「どこが伝わらなかったか」を意識して意見を聞くと、より自身の勉強になります。
- 添削してもらえる: 経験豊富な人に添削してもらうことで、より良い作品になります。ただ、添削はあくまでも添削をしてくれた先輩の力です。最終的には自分自身で最も良い作品を作れるようにならなければいけません。ここでポイントは、「作品のどこに問題があり、どのような手順で直したのか、直したことでの作品への効果は何か」を聞くことです。作品のビフォーアフターを見るだけでなく、先輩の思考過程を身につけましょう。
- 新しい表現方法を発見できる: 他の人の作品から、新しい言葉の選び方や表現方法を学べます。もし、作品の中に良い表現があれば、どのようにしてその言葉を探したのか、を作者に聞いて自身の作品づくりに生かしましょう。本人に作り方を聞かず、ただ作品を見るだけで終わるのであれば、歳時記や句集で作品を読んでいれば良いということになります。歳時記や句集では、良い作品に出合っても作者に作り方を聞くことはできません。句会であれば、目の前に作者がいるので聞けます。このチャンスは逃さないようにしましょう。
- 違う角度の視点を得られる:句会では、同じ季語を用いて、参加者全員が作品を詠むことがあります。 同じ季語を使った他の人の句を見ることで、自分では思いつかなかった角度からの季語の捉え方や、意表を突く表現、新しい言葉の組み合わせなどを発見することができます。
俳句仲間ができる
- 共通の趣味を持つ仲間と出会える: 俳句を通じて、同じ趣味を持つ仲間と出会うことができます。一人で俳句を作り続けるよりも、仲間がいたほうが俳句に対するモチベーションが高まります。俳句の技術向上はもちろん、仲間との絆を深めることも大切にしてください。
- 情報交換ができる: 句会や俳句に関する情報交換をすることで、俳句の世界をより深く知ることができます。
他の人の俳句を鑑賞するヒント
「良い句」ってどうやって見つけるんだろう?と迷うかもしれませんね。難しく考える必要はありません。まずは、自分の「心が動いた句」を見つけることから始めましょう。
以下のポイントを参考にすると、さらに俳句の面白さが広がります。
- どんな「季節」を感じる? 「桜」や「雪」などの季語が、どんな風景や情感を描き出しているかを感じ取ってみましょう。
- リズムは心地よい? 「五七五」という限られた音の中に、どんな音の響きやリズムが生まれているかを感じてみてください。声に出して読んでみるのもおすすめです。
- どんな「情景」が浮かぶ? 句を読んだときに、心の中にどんな景色や場面が思い浮かぶか、想像を膨らませてみましょう。
- 「ハッとする」表現はある? 「こんな言葉の組み合わせがあったのか!」と驚くような、作者独自の視点や言葉の選び方を見つけてみましょう。
- 作者の気持ちは? 句の中にどんな感情が込められているのか、作者の気持ちを想像してみるのも面白いですね。
これらのポイントは、句会で自分が良いと思った句について感想を伝えるときにも役立ちます。「この季語の使い方が素敵でした」や、「この情景が目に浮かびました」など、自分の言葉で伝えてみましょう。
句会での発言のポイント
句会では、自分が良いと感じて選んだ作品にたいして、選んだ理由を発表して意見を交わします。
これが句会のよいところで、他の人の視点や表現を学べる機会になっています。
参加した句会を、より有意義なものにするために、発言のポイントを10個ご紹介します。
良い発言
- 相手の句を尊重する
発言の際は、作者の思いや努力を尊重し、批判的ではなく前向きな言葉を心がけましょう。そして、その句の良い点や素晴らしいところを見つけて伝えましょう。 - 自分の感想を率直に述べる
難しく考えすぎず、自分が感じたことを素直に言葉にするのが大切です。「この句を読んで○○を思い出しました」「情景が目に浮かびます」など。 - 具体的な箇所に触れる
句のどこが特に良かったかを具体的に伝えます。「この言葉の選び方が○○なので好きです」など。具体的に良かった場所や根拠を、自分の言葉でまとめられるようになると、今後の自分の作品作りにも生かせるようになります。 - 学びを伝える
他の人の句を読んで学んだことを伝えます。「この句の○○から新しい視点を学びました」など。 - 質問をする
「この句の〇〇の部分は、どういう意味ですか?」「なぜこの季語を選んだのですか?」など、疑問に思ったことを積極的に質問しましょう。
悪い発言
- 自身の作品の背景を長々話す
句会では、作者が作品の背景を説明する時間があります。作者の表現したかったことは何なのかを、確認するためです。このとき、作品を詠んだときの状況を理解してもらいたいあまりに、何分も話をしてしまいますが、句会の時間は限られています。30秒以内に要点をまとめて説明しましょう。「○○の背景があり、このような考えでその表現をえらびました」など、簡潔に述べましょう。 - 否定的な意見を言う
忌憚のない意見交換は、俳句の創作活動にとって非常に有益です。しかし「否定的な意見」は、伝え方によっては、相手を傷つけ、場の雰囲気を悪くしたりする可能性がありるので、注意しましょう。
ちなみに、否定と反論は違います。建設的な意見交換を行うための反論は大切ですので、両者を混同しないようにしましょう。
反論では、相手の意見に対して反対の意見を言いますが、そのとき、角が立たないように柔らかな印象で言うコツがあるので紹介します。
反論のコツ
反論の方法としては、以前「イエスバット法」というものがありました。相手の意見を肯定した後に、「しかし」と接続して自分の意見を述べる方法です。
この方法は、相手の意見を尊重しつつ、自分の考えを伝える上で有効ですが、「しかし」という言葉が少し硬く感じられる場合もあります。
そこで、より柔らかく、建設的な意見交換を促すために、「イエスアンド法」「イエスイフ法」「イエスハウ法」「イエスワット法」「イエスソーザット法」といった方法が考え出されました。これらの方法は、「しかし」の代わりに、肯定的な言葉や接続詞を使うことで、よりスムーズな反論を可能にします。句会でも議論を活発にする際に使えます。
| イエスアンド法 | 相手の意見を肯定した後に、「それなら」「実は」といった肯定的な接続詞で自分の意見を繋げます。 例: 相手の意見「この句の場合、この季語が良いと思います。」 自分の意見「なるほど確かに。それなら、この季語だとどうですか?また違った表現になるかもしれません。」 |
| イエスイフ法 | 相手の意見を肯定した後に、「もし~ならば」「~という状況だと」という仮定を投げかけます。 例: 相手の意見「このAの表現が良いです。」 自分の意見「確かに、Aの表現は良いですね。ちなみに、もしこれがBの表現だったらどうですか?」 |
| イエスハウ法 | 相手の意見を肯定した後に、「どうすれば」「どんな方法で」という方法を問いかけます。 例: 相手の意見「この表現は問題があるのでは?」 自分の意見「確かにこの表現は問題があります。それでもこの表現で作るには、どうすれば良いですか?」 |
| イエスワット法 | 相手の意見を肯定したうえで、「何?」と、分からない部分を尋ねます。 例: 相手の意見「季重なりはダメだと思う。」 自分の意見「確かに季重なりはダメですよね。ちなみに、季重なりの何が一番問題になりますか?」 |
| イエスソーザット法 | 相手の意見を肯定した後に、「しかし(but)」を「だからこそ(so that)」に置き換えます。 例: 相手の意見「Aの表現は良いですね。」 自分の意見「確かにAの表現は良いですよね。だからこそ、この部分をもっと練ると更によくなる気がしませんか?」 |
各方法のメリット
- 相手への配慮: 否定的な言葉を使わないため、相手に攻撃的に感じさせません。
- 建設的な議論: 肯定的な言葉を使うことで、より建設的な議論に繋がりやすいです。
- スムーズなコミュニケーション: 柔らかな言葉遣いにより、スムーズなコミュニケーションが可能になります。
どの方法を選ぶべきか?
- 相手の意見の反対を述べる場合: イエスアンド法、イエスイフ法
- 相手の意見を発展させたい場合: イエスハウ法、イエスワット法、イエスソーザット法
句会での失敗と成功談
失敗談
句会は、俳句愛好家が集まり、お互いの作品を発表し、意見交換をする場です。誰でも最初は初心者。失敗談や成功談を参考に、より充実した句会にしてください。
- 準備不足で俳句が浮かばない
句会の前に余裕をもって俳句を準備しておらず、ぎりぎりで作ったけれどうまくいかず、納得のいく句が作れなかった。
これは、私も何度かしてしまいました。中途半端な作品を出してもたいていは良い評価は得られないのですが、それ以上に悪いのが、中途半端な気持ちで作った俳句にアドバイスを受けたとしても、頭に残らないということです。何度もねり返して何時間もかけて作った作品に対してアドバイスがあると、「あぁ、そういう視点があったのか!なんで気が付かなかったんだろう!」と感じ、記憶に鮮明に残ります。全力で出したものの方が、得られるものも大きいと感じます。 - 意見を聞き入れられなかった
自分の句への意見を素直に受け止められず、反論してしまった。
一生懸命作った俳句の問題点を指摘されると、その意見を素直に受け止められないものです。ただ、後から振り返ると、大概は先輩の言っていたことが正しいと気が付くものです。問題点の指摘を受けたら、「同じ間違いをしないために、どのように注意をすればよいですか」など、前向きな発言をしましょう。 - 自分の句の発表で緊張
自分の句の背景を発表する際に緊張して声が震え、伝えたいことがうまく伝わらなかった。
わたしも初めての時は、机の下で手のひらに「人」の文字を何度も書いた記憶があります。深呼吸をする、水を飲むなど、あなたに合った方法で心を落ち着かせましょう。この緊張も、2~3回出席すれば、なくなるので心配ありません。 - 季語を間違えて使う
季語として使った言葉が、今の季節にふさわしくないものだった。
句会の暗黙の了解なのですが、提出する俳句は、句会の行われる季節のものを選ぶのが一般的です。3か月以上ずれた季節の季語で俳句を作ると、季節感がずれてしまうのでなるべく避けましょう。
成功談
- 他の参加者の作品から学びがあった
他の人の俳句の言葉遣いや表現方法から、新しい発見があった。
作品を鑑賞する際は、意識して、どこが良いのか、どこが自分と違うのかを探すことで、必ず新しい発見はあります。単に参加しているだけ、ではなく、積極的に何かを学び取るという気持ちで参加しましょう。 - 思い切って質問して理解が深まった
句会中に、俳句の表現方法について思い切って質問し、深い理解を得ることができた。
質問に対する答えは学びになります。自分のした質問が浅いものであった場合、家に帰った後で自分のした質問を反省することになります。「こう言えばよかった」「もっと、こう聞けばよかった」と思います。ただ、その反省の繰り返しが学びになって、質問力につながります。質問することはとても緊張しますが、どんどん質問をしましょう。
オンライン句会の参加方法とポイント
最近ではオンラインで句会ができる環境がたくさんあり、とても盛んになってきています。この記事では、オンライン句会について、参加方法や注意点、対面句会との違いなど、基本的な情報を分かりやすく解説します。
オンライン句会とは?
オンライン句会とは、インターネットを通じて行われる句会のことです。場所や時間に縛られずに、全国、はたまた世界中の俳句愛好家の方々と交流しながら、俳句を楽しむことができます。
オンライン上に投句や選句ができるサービスがあり、それを利用して行う句会もありますし、ZoomやGoogle Meetなどのビデオ会議ツールを使用して行う句会もあります。
参加方法
参加方法は、主催する句会によって異なりますが、一般的には、以下の流れで参加することになります。
- 句会を探す: 俳句のウェブサイトやSNSで、自分に合ったオンライン句会を探す。
- 参加申し込み: 句会の主催者に連絡し、参加の意思を伝える。
- 投句: 締め切りまでに、自分の作った句を主催者に送る。
- 選句・講評: 他の参加者の句を読み、選句や講評を行う。
必要なツール
オンライン句会に参加するために必要なツールは、インターネット環境とパソコンまたはスマートフォンです。また、句会によっては、ビデオ会議アプリ、マイクが必要な場合もあります。
注意点
- 通信環境: 安定したインターネット環境が必要です。
- 時間厳守: オフラインの句会と同様に、時間厳守は大切です。
- マナー: オンライン上でも、対面での句会と同様に、礼儀正しい言動を心がけましょう。
- 個人情報: 個人情報は適切に管理しましょう。
- マイクの確認:参加前にマイクやカメラが正しく動作するか確認しておきましょう。
- マイクスイッチ:加者の発表中にはマイクをミュートにしておくなどの配慮しましょう。
オンラインならではの利点
- 場所や時間に縛られない: 自宅にいながら、句会ができます。移動の時間や手間もかかりません。
- 参加しやすい: オンラインにつながる環境さえあれば、気軽に参加できます。
- 記録が残る: オンライン上の記録が残るので、自分の成長を振り返ることができます。作品だけでなく、参加者の発言を振り返るのも、簡単にできます。
- 多様な意見: 様々なバックグラウンドを持つ人々と交流して、多様な意見に触れることができます。意見だけでなく作品の種類も、オンラインの方が多様な印象を持ちます。
オンライン句会と対面句会の違い
| 項目 | オンライン句会 | 対面句会 |
|---|---|---|
| 場所 | どこでも | 会場 |
| 時間 | 自由な時間 (平日の夜でもできる) | 決まった時間 (皆が集まりやすい土日の昼が多い) |
| 交流 | チャットや掲示板など | 直接対面 |
| 料金 | 無料が多い | 千円~二千円くらい (場所代・プリント代など) |
| 雰囲気 | 個人的で自由 ビデオで行う場合は、対面に近い感じ 掲示板で行う場合は、淡泊 | 対面でのコミュニケーションで、和気あいあいの感じがある |
最後に
初めての句会は緊張するかもしれませんが、気負わず、自分のペースで俳句を楽しんでください。
他の人の句に触れたり、感想を共有することで、俳句の新しい魅力や発見が待っています。大切なのは、俳句を通して感じたことを素直に表現することです。
句会を通じて、俳句の楽しみを深めてください!
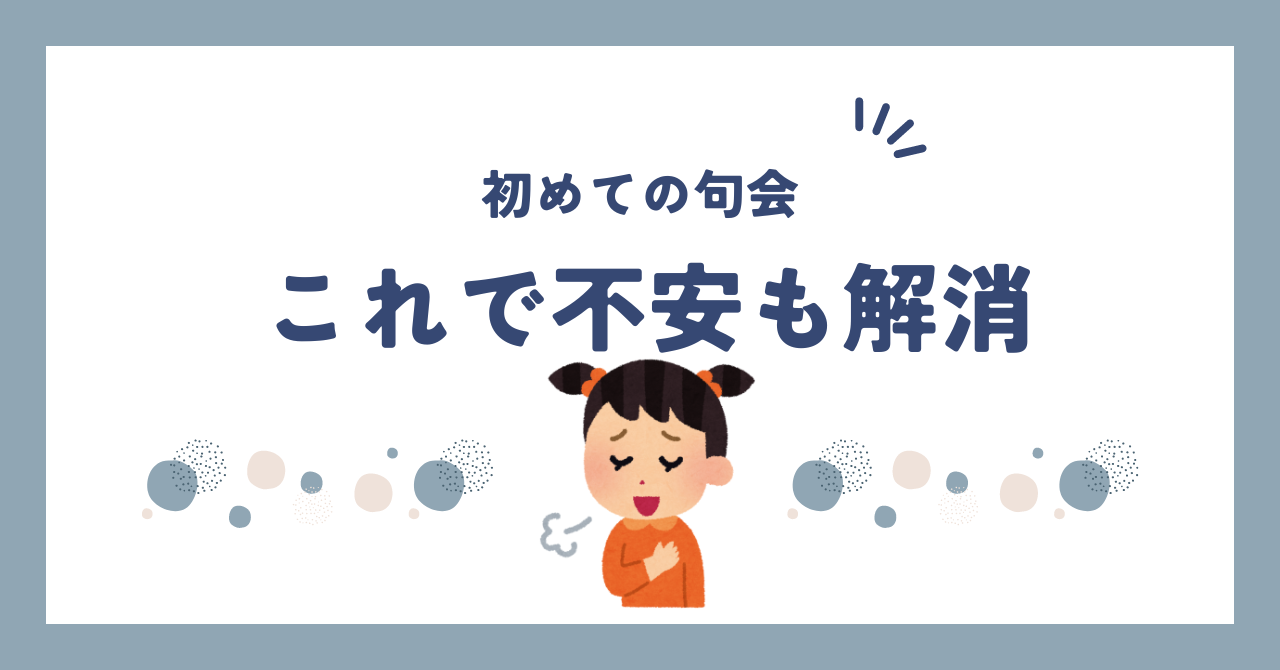
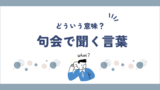

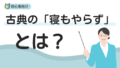
コメント