言葉を巧みに使って、情景や感情を美しく表現する方法に「比喩(ひゆ)」があります。
この記事では、俳句で比喩を使うことのメリット・デメリット、比喩の種類、実際に比喩が使われている俳句の例などを、初心者にも分かりやすいように解説します。
比喩とは?
比喩とは、ある物事や概念を、似た性質を持つ別の物事にたとえて表現する言葉の技法です。
【例】
- 「あの先生はゴリラのようだ」
- 「この雨は涙のようだ」
このように、聞いた人がすぐにイメージできるように、別のものにたとえて説明することで、物事をより具体的に、いきいきと伝えることができます。
比喩の役割とメリット
比喩を使うと、俳句がより豊かで魅力的なものになります。主なメリットを3つ紹介します。
表現の幅が広がる
比喩は、言葉に新しい命を吹き込みます。たとえば、人間以外のものを人間のように表現する「擬人化」も比喩の一種です。
「花が揺れている」という客観的な表現を、「花が笑っている」と表現することで、春の訪れの喜びをより強く、鮮やかに伝えることができます。
オリジナリティが生まれる
ありきたりな表現から抜け出し、あなただけの視点で世界を捉え直すことができます。
「花が揺れている」という表現はありふれていますが、「花が笑う」「花が悲しむ」といった表現にすることで、独自の視点が生まれ、読み手の心に深く残る俳句になります。
感情を豊かに表現できる
比喩を用いることで、自分の感情を直接的に言うだけでなく、より複雑で繊細な気持ちを表現できます。
「秋晴れは気持ちがいい」と言うよりも、「秋の晴天に心も晴れわたる」という表現の方が、単なる喜びだけでなく、心が解放されていくような感覚まで伝わってきます。
比喩のデメリット
比喩は素晴らしい表現技法ですが、使い方によってはデメリットもあります。特に俳句を作る際には、次の2点に注意しましょう。
ありきたりな表現になりやすい
過去にたくさんの人が使ってきた比喩は、新鮮さがなく、読者の心に響きにくいことがあります。例えば「涙のような雨」や「綿菓子のような雲」などは、多くの人が思いつく比喩です。
比喩を使うときは、「誰もが知っている定番の表現」ではなく、あなただけの新しい発想を見つけることが大切です。
理解されない可能性がある
比喩は主観的な表現なので、人によっては意味が伝わらなかったり、意図しない解釈をされたりすることがあります。
たとえば「花が笑う」と聞いて、「笑うって具体的にどんな状態?」と考えてしまう人もいるかもしれません。俳句は短い言葉で情景を描写する芸術なので、比喩を使う際には、読み手が共感できるかどうかがとても重要です。
比喩の種類
比喩にはさまざまな種類がありますが、ここでは俳句でよく使われる代表的なものと、そのほかの比喩を紹介します。
代表的な比喩
- 直喩(ちょくゆ): 「〜のようだ」「まるで〜」のように、比喩であることを示す言葉を使って直接たとえる方法です。
- 例: 彼の心は氷のようだ。
- 隠喩(いんゆ): 「〜のようだ」といった言葉を使わず、「AはBである」のように断定する形でたとえる方法です。
- 例: 彼の心は氷だ。
- 擬人化(ぎじんか): 人間以外のものを、人間のように表現する方法です。「活喩(かつゆ)」とも呼ばれます。
- 例: 風が歌い、木々が踊る。
- 擬物化(ぎぶつか): 擬人化の反対で、人間を、人間以外のもので表現する方法です。
- 例: 彼は石のように無表情だ。
- 例: 彼は石のように無表情だ。
その他の比喩
- 諷喩(ふうゆ): たとえられたものだけを提示し、本来の意味を読み手に推測させる方法です。ことわざや慣用句に多く見られます。
- 例: 「砂漠に水をまくようなものだ。」(→無駄な努力だという意味)
- 提喩(ていゆ): 全体の一部で全体を表したり、類全体で個を表したりする方法です。
- 例: 「パンのために働く。」(→「パン」が食料全体、ひいては生活を指す)
- 換喩(かんゆ): ある物事と密接な関係にある別のものを用いて、本来の物事を表す方法です。
- 例: 「ペンは剣よりも強し。」(→「ペン」は言論を、「剣」は武力を指す)
- 例: 「ペンは剣よりも強し。」(→「ペン」は言論を、「剣」は武力を指す)
俳句での比喩の作り方
ここでは、先ほど紹介した代表的な比喩の作り方を見ていきましょう。
直喩の作り方
直喩は「AはBのようだ」という形で表現します。
- 表現したい物事(A)を決めます。
- 例: 「顔」の様子を表現したい。
- その物事の特徴や性質を挙げます。
- 例: 「恐ろしい」
- 同じ特徴を持つ別の物事(B)を探します。
- 例: 「鬼」
- 「AはBのようだ」という形で組み合わせます。
- 完成: 「顔が鬼のようだ」
直喩はシンプルで分かりやすい反面、説明的になりがちです。ありきたりな表現にならないよう、誰も思いつかないような意外な組み合わせを探してみましょう。
直喩を使った俳句の例
- いつか届く手紙のやうに種を蒔く (神田ひろみ)
- しゃぼん玉ほどの影です癌告知 (宮沢子)
- 雪うさぎみたいに豆電球を見る (吉川真実)
直喩表現のための言葉
直喩は「のようだ」「まるで」といった言葉で表現されますが、他にも、次の言葉を使って表現をすることができます。
「のごとく」「ほど」「ばかり」「めき」「を似て」「たとえば」「さながら」「みたい」
それぞれの言葉をつかった俳句を紹介します。
| のようだ (のやうだ) | いつか届く手紙のやうに種を蒔く 神田ひろみ | 神田ひろみの句集(Amazon) >> |
| まるで | 満開のまんさくまるで枯れてをり 照井翠 | 照井翠の句集(Amazon) >> |
| のごとく | 身をよぢる如くに束ねられ紫苑 川崎展宏 | 川崎展宏の句集(Amazon) >> |
| ほど | しゃぼん玉ほどの影です癌告知 宮沢子 | 宮沢子の句集(Amazon) >> |
| ばかり | まぼろしの鹿はしぐるるばかりなり 加藤楸邨 | 加藤楸邨の句集(Amazon) >> |
| めき | きりぎしや朝霧はやまとことばめき 児玉悦子 | 古川京子の句集(Amazon) >> |
| を似て | 水と雲秋声をもて語り合ふ 郷正子 | 郷正子の句集(Amazon) >> |
| たとえば | 大綿のたとえば母の寝息かな 青木栄子 | |
| さながら | 大年の机上さながら海漂ふ 松澤昭 | 松澤昭の句集(Amazon) >> |
| みたい | 雪うさぎみたいに豆電球を見る 吉川真実 |
隠喩の作り方
隠喩は「AはBだ」と断定する表現方法です。直喩で作った「AはBのようだ」の「ようだ」をなくすだけで作ることができます。
- 直喩を作る
- 例: 「顔が鬼のようだ」
- 「ようだ」を消す
- 完成: 「鬼の顔」
直喩に比べて創造的で、読み手の想像力を掻き立てる効果があります。ただし、あまりにもかけ離れた比喩だと意味が伝わらなくなってしまうので、読者が共感できるような表現を心がけましょう。
隠喩を使った俳句の例
| 春水にあばたの鐘を撞き鳴らす 川崎展宏 | 川崎展宏の句集(Amazon) >> |
| 金剛の露ひとつぶや石の上 川端茅舎 | 川端茅舎の句集(Amazon) >> |
| 風雪にたわむアンテナの声を聴く山口誓子 | 山口誓子の句集(Amazon) >> |
擬人化の作り方
擬人化は、人間以外のものに人間の感情や行動を持たせる方法です。
- 表現したい対象を選びます。
- 例: 「冬木」
- その対象の様子から、人間らしい部分を探します。
- 例: 一本で「孤独に立っている」ように見える。
- 二つを組み合わせて表現します。
- 完成: 「冬木が孤独に立っている」
擬人化を使った俳句の例
| 菜の花がしあはせさうに黄色して 細見綾子 | 細見綾子の句集(Amazon) >> |
| 海に出て木枯らし帰るところなし 山口誓子 | 山口誓子の句集(Amazon) >> |
| 戦争が廊下の奥に立つてゐた 渡辺白泉 | 渡辺白泉の句集(Amazon) >> |
擬物化の作り方
擬物化は、人間を人間以外のものとして表現する方法です。
- 表現したい対象を選びます。
- 例: 「彼の意志」
- その対象の様子から、物(無生物)らしい部分を探します。
- 例: 鉄のように固い。
- 二つを組み合わせて表現します。
- 完成: 「彼は鉄のような意志をもっている」
擬物化を使った俳句の例
| いつか届く手紙のやうに種を蒔く 神田ひろみ | 神田ひろみの句集(Amazon) >> |
| さざなみのやうに集まり螢狩 岩淵喜代子 | 岩淵喜代子の句集(Amazon) >> |
| 寒凪やはるかな鳥のやうにひとり 清水径子 |
俳句に比喩は向かない?
俳句の世界には、比喩表現を好まない人もいるのが事実です。その主な理由は、以下の通りです。
- 俳句に比喩は合わない: 比喩を使うと、情景をありのままに描く「写生」から離れてしまうという考え方があります。
- 説明的になる: 比喩は「AをBにたとえる」という行為のため、鑑賞者に説明しているように感じられることがあります。
- 主観にすぎない: 比喩は作者の個人的な感覚に過ぎず、読み手と共感できない可能性があると見なされることもあります。
- 理屈っぽく見える: 比喩は頭の中で考えられた機知的な表現に見えるため、純粋な感動から生まれた句ではないと受け取られる場合があります。
特に、目にしたものをそのまま俳句にする「写生」を重んじる俳人は、比喩をあまり使いません。
大切なのは「あなたが作りたい俳句」
しかし、これらの意見はあくまでも一部の考え方です。 比喩を使った素晴らしい俳句はたくさん存在し、読み手に強い印象を与える力を持っています。もしあなたが比喩を使いたいと思ったなら、周囲の意見に臆することなく、どんどん挑戦してみてください。
俳句は、あなたが感じたことを自由に表現する芸術です。他の人の意見を第一に考えるのではなく、まず「あなたが作りたい俳句」を大切にすることが何よりも重要です。
有名な俳人の中にも、与謝蕪村や山口誓子のように、比喩を多用して傑作を生み出した人がいます。比喩俳句に挑戦してみたいという方は、彼らの句集を読んで、その表現方法を学ぶのも良いでしょう。
比喩は難しい表現方法ですが、それだけに新しい境地が眠っているかもしれません。果敢に挑戦し、あなただけの比喩俳句で、俳句界に新しい風を吹き込んでみてはいかがでしょうか。
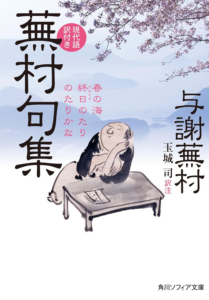
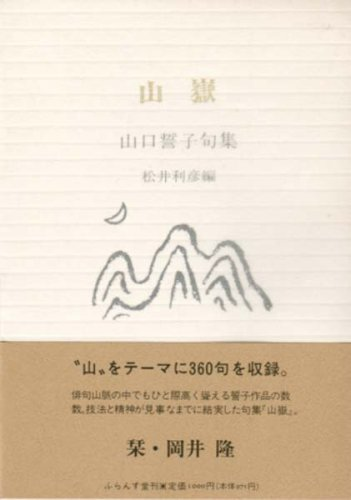
比喩での言葉探しのヒント
「誰も思いつかないような比喩を、どうすれば作れるのだろう?」と悩む方もいるかもしれません。簡単に作ることは難しいですが、一つの方法として、「連想ゲーム」のように言葉を広げていくやり方があります。
たとえば「雲」を比喩に使いたい場合、次のように単語を広げてみましょう。
- まず、「雲」から連想される単語を5つ挙げます。(例:白、綿、羊、空、雨)
- 次に、1で挙げたそれぞれの単語から、さらに5つの単語を連想します。
こうして合計25個の単語の中から、一番「新鮮で比喩になりそうな単語」を選ぶのです。
最初の5つの単語は誰でも思いつくようなものになりがちですが、そこからさらに連想した単語は、「雲」に近すぎず、かといって遠すぎない、絶妙な距離感の言葉になることが多いです。この方法で、ありきたりでもなく、まったく理解できないわけでもない、ちょうど良い比喩が生まれやすくなります。
「25個も単語を考えるのは大変だ」という方は、「連想類語辞典」のようなサイトを使ってみるのも良いでしょう。一瞬でたくさんの連想語が表示されるので、その中からピンとくる言葉を選んでみるのも一つの手です。
「連想類語辞典」はこちら >>
さまざまな比喩表現が掲載された本
こちらの本は、これまでの多くの作家の比喩の使い方が、実例で紹介されています。
自分一人では想像できなかった表現が載っているため、俳句作りの表現の幅が大きく広がります。
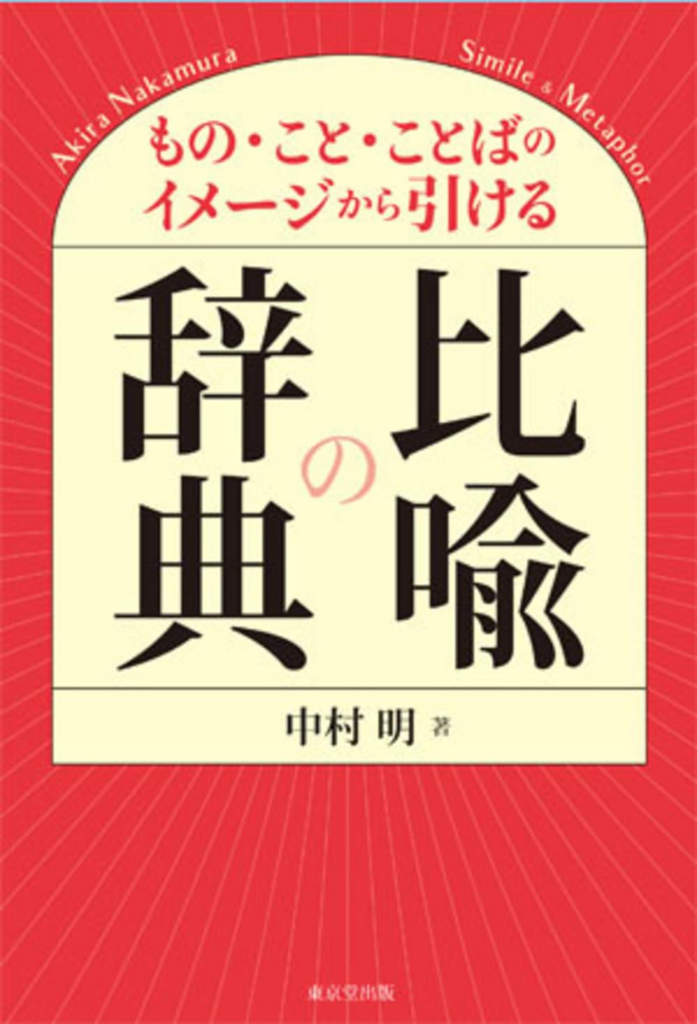
最後に
比喩を使うと、思いもよらない意外な発想や、想像力豊かな面白い俳句が生まれます。
比喩を批判的に捉える人もいますが、もし俳句の世界から比喩が消えてしまったら、その魅力は大きく損なわれるでしょう。
大人になると、論理的な思考が優位になり、子どもの頃のように自由な発想をしにくくなります。しかし、比喩をうまく使うことで、雲を「綿あめみたい」と感じた幼い頃の豊かな感性を取り戻せるかもしれません。
俳句は、自分の心を自由に表現する芸術です。比喩の成功率は決して高くありませんが、臆することなく果敢に挑戦してほしいと思います。あなたにしか作れない、新しい風を俳句の世界に吹き込んでくれたら、とても嬉しく思います。
ぜひ、あなただけの心に残る比喩俳句を目指してみてください。

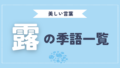
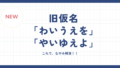
コメント