 俳句を作る
俳句を作る 俳句での7つの省略方法
俳句はいかに省略できるか、と言われます 省略すれば音数を節約できるし、表現もすっきりします 表現がすっきりすれば、読者の印象にも強く残ります なので、初心者でも簡単にできる省略の場所をあげてみます ① 「ごとき」「ような」を消す 雪のような...
 俳句を作る
俳句を作る  俳句を作る
俳句を作る  俳句を作る
俳句を作る  俳句を作る
俳句を作る  俳句を作る
俳句を作る  俳句を作る
俳句を作る  俳句を作る
俳句を作る 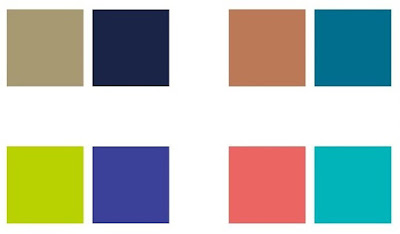 俳句を作る
俳句を作る  俳句を作る
俳句を作る  俳句を作る
俳句を作る