 季語のいろいろ
季語のいろいろ ショウブ、アヤメ、カキツバタの違い
ショウブ、アヤメ、カキツバタは、いずれもアヤメ科アヤメ属の植物で、初夏の水辺を彩る美しい花々です。しかし、俳句の世界では、これらの花を詠み分けることで、情景や季節感をより細やかに表現します。ここでは、それぞれの違いと、俳句における特徴を解説...
 季語のいろいろ
季語のいろいろ  季語のいろいろ
季語のいろいろ  季語のいろいろ
季語のいろいろ  季語のいろいろ
季語のいろいろ  季語のいろいろ
季語のいろいろ  季語のいろいろ
季語のいろいろ  俳句を作る
俳句を作る 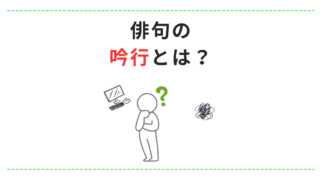 俳句の疑問
俳句の疑問  俳句の疑問(作り方)
俳句の疑問(作り方)  俳句を作る
俳句を作る