 俳句の疑問(作り方)
俳句の疑問(作り方) 俳句で字余りは上五が良いと言われる理由は?
「俳句では字余りや字足らずをしないこと」「字余りをするならなるべく上五ですること」俳句を始めたばかりの人は先輩から、「字余り」について一度はこのようなことを言われているのではないでしょうか一体ここで言う「字余りをするなら上五でしなさい」とい...
 俳句の疑問(作り方)
俳句の疑問(作り方)  俳句を作る
俳句を作る  俳句の疑問(作り方)
俳句の疑問(作り方)  俳句の疑問(作り方)
俳句の疑問(作り方) 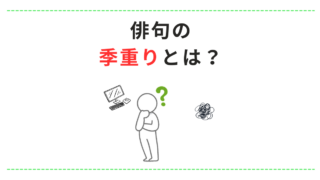 俳句の疑問
俳句の疑問 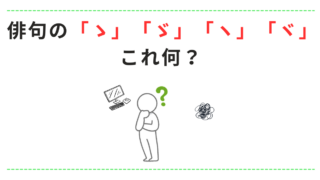 俳句の疑問
俳句の疑問 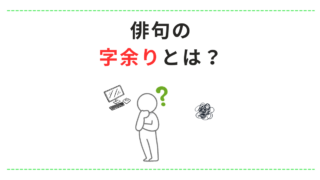 俳句の疑問
俳句の疑問  俳句の疑問
俳句の疑問 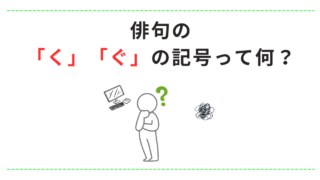 俳句の疑問
俳句の疑問  俳句の疑問
俳句の疑問