 四季で見られる季語
四季で見られる季語 「薔薇」の季節ごとの季語
俳句では薔薇は夏の5月頃の季語です。ただ、春や秋にみられる薔薇も季語となっているので、季節ごとの季語と意味を紹介します。
 四季で見られる季語
四季で見られる季語 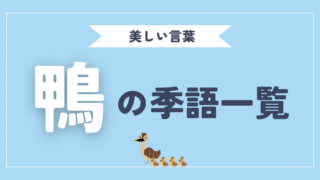 四季で見られる季語
四季で見られる季語  四季で見られる季語
四季で見られる季語 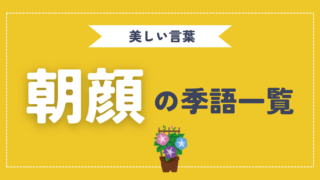 四季で見られる季語
四季で見られる季語  四季で見られる季語
四季で見られる季語 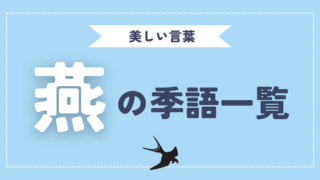 四季で見られる季語
四季で見られる季語 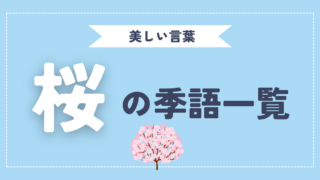 四季で見られる季語
四季で見られる季語  四季で見られる季語
四季で見られる季語  四季で見られる季語
四季で見られる季語 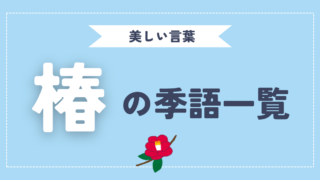 四季で見られる季語
四季で見られる季語