「俳句・川柳・短歌」という言葉があるけれど、具体的にどのように違うのか分からない、という人のために、それぞれの違いを解説していきます。
俳句・川柳・短歌の読み方
「俳句・川柳・短歌」のそれぞれの読み方は次の通りです。
俳句(はいく)
川柳(せんりゅう)
短歌(たんか)
俳句・川柳・短歌の違い
俳句 (5・7・5)
| 文字数 | 五七五の十七音 |
| 内容 | 自然や季節感を大切にし、景色の裏に思いを込めて余韻をつくるのが特徴 |
| 季語の有無 | 季語を入れることが必須 |
| 表記方法 | 書き言葉で表記します |
川柳 (5・7・5)
| 文字数 | 五七五の十七音 |
| 内容 | 人間社会を風刺したり、ユーモアを交えたりしながら、人生の機微を軽妙に詠みます |
| 季語の有無 | 季語は不要で、普段使う話し言葉で詠むのが特徴 |
| 表記方法 | 話し言葉で表記します |
短歌 (5・7・5・7・7)
| 文字数 | 五七五七七の三十一音 |
| 内容 | 俳句・川柳に比べて文字数が多く、人間の感情や叙情を豊かに表現することに向いています |
| 季語の有無 | 季語の制約はありません |
| 表記方法 | 書き言葉で表記します |
俳句の文字数は「五七五の十七音」ですが、音数の数え方はこちらで記事にしています。
https://haiku.kohata.site/category/haikuhajime/575housoku
俳句には、その季節を表す言葉である季語を入れることが必須です。それぞれの季節の季語は、こちらでご確認いただけます。
俳句・川柳・短歌の作品を見比べる
「俳句・川柳・短歌」の違いを表にしましたが、実際に作品を見た方が分かりやすいと思います。
| 俳句 | 菜の花や 月は東に 日は西に (なのはなや つきはひがしに ひはにしに) ※季語(菜の花)が入っていて、自然を詠んでいます |
| 川柳 | 増えるのは 妻の贅肉 国の税 (ふえるのは つまのぜいにく くにのぜい) ※季語はなく、社会や周りの様子を面白く詠んでいます |
| 短歌 | はたらけど はたらけど 猶わが生活 楽にならざり じっと手を見る (はたらけど はたらけど なおわがくらし らくにならざり じっとてをみる) ※この作品には季語はなく、感情をしずかに詠んでいます |
俳句・川柳・短歌の作品の数え方
俳句・川柳・短歌は、それぞれ作品の数え方が異なります。以下に、その数え方をまとめました。
俳句
俳句は「一句(いちく)」「二句(にく)」と数えます。
例えば、「この人の俳句、とても面白いね。もう一句読みたいな」といった使い方をします。
川柳
川柳も俳句と同様に「一句(いちく)」「二句(にく)」と数えるのが一般的です。
「今日の川柳、傑作が一句できたよ」のように使われます。
短歌
短歌は「一首(いっしゅ)」「二首(にしゅ)」と数えます。 短歌の歴史が古く、和歌の一部であるため、和歌と同じ数え方をします。
「好きな短歌が一首あります」とも使いますし。「百人一首」という言葉もありますね。
俳句・川柳・短歌、どれが先?
「俳句・川柳・短歌」のうち、短歌が最も古く、次に川柳、そして最後に俳句が成立しました。
短歌
短歌は、日本の定型詩の最も古い形式の一つで、起源は奈良時代の歌集『万葉集』にまでさかのぼります。
ただ、その頃はまだ、「短歌」という言葉はなく、ただ「歌(うた)」と呼ばれていました。
川柳
川柳は、江戸時代中期に生まれました。
柄井川柳(からい せんりゅう)が選者となり、世相や人間の滑稽な姿を風刺的に詠んだ句が人気を博しました。
俳句
俳句は、江戸時代に連歌(れんが)から発展しました。
連歌とは、複数の人が上の句(五・七・五)と下の句(七・七)を交互に詠みつなげていく共同制作の文芸です。
その連歌の上の句(五・七・五)だけを独立させて、芸術性を高めたのが松尾芭蕉です。
俳句・川柳・短歌、一番難しいのはどれ?
俳句、川柳、短歌は、どれも日本の伝統的な詩の形式で、それぞれに異なる魅力と奥深さがあります。
一見、文字数が少ないから簡単そうに思えるかもしれませんが、実はどれも奥が深く、極めるのはとても難しいものです。
俳句
わずか17音に世界観を凝縮する難しさ
五七五の17音で構成される俳句は、短いからこそ言葉を選ぶのが非常に難しいと言えます。
特に「季語」を入れるというルールがあるため、季節感を表現しつつ、情景や心情を巧みに織り込む必要があります。
私は俳句を初めて7年目になりますが、「やればやるほど難しく感じる」と感じます。
ただ、限られた音数の中で、いかに自分だけの世界観を表現するか。この難しさが、俳句の醍醐味とも言えます。
川柳
季語に縛られず、日常を切り取る難しさ
俳句と同じく五七五の17音ですが、川柳には「季語」のルールがありません。
そのため、世相や社会を風刺したり、日々の暮らしの中で感じたことを自由に表現することができます。
季語がない分、俳句より作りやすいと感じる人もいるかもしれませんが、実はその分、ありきたりな表現になりがちという難しがあると思います。
いかにユーモアや鋭い視点を盛り込み、読み手の心に響く句を作るか。自由だからこそ、個性を出すのが難しいと言えるのではないでしょうか。
短歌
五七五七七に込められた物語を紡ぐ難しさ
短歌は五七五七七の31音で構成され、俳句や川柳よりも長い分、より複雑な心情や物語を表現できます。
作品を見ていると、最後の「七七」でどう締めるかが、短歌を作る上で非常に重要なポイントになっていそうです。
上の句(五七五)で情景を描き、下の句(七七)で心情を詠む、といった構成が多くみられ、31音という限られた文字数の中で、起承転結を意識しながら、一つの物語を完成させる必要があります。
俳句や川柳とはまた異なる、物語を紡ぐ力が求められると言えるでしょう。
俳句・短歌で有名な人
俳句と短歌で有名な方をいくつかご紹介します。
俳句
作者
それぞれ代表的な作品を2つずつご紹介します。
作品
松尾芭蕉
古池や 蛙飛びこむ 水の音
閑さや 岩にしみ入る 蝉の声
与謝蕪村
菜の花や 月は東に 日は西に
春の海 ひねもすのたりのたりかな
小林一茶
やれ打つな 蝿が手を擦り 足を擦る
雀の子 そこのけそこのけ お馬が通る
正岡子規
柿くへば 鐘が鳴るなり 法隆寺
いくたびも 雪の深さを 尋ねけり
短歌
作者
| 柿本人麻呂 | 柿本人麻呂の歌集(Amazon) >> |
| 小野小町 | 小野小町の歌集(Amazon) >> |
| 与謝野晶子 | 与謝野晶子の歌集(Amazon) >> |
| 石川啄木 | 石川啄木の歌集(Amazon) >> |
| 俵万智 | 俵万智の歌集(Amazon) >> |
それぞれ代表的な作品を2つずつご紹介します。
作品
柿本人麻呂
あしびきの 山鳥の尾の しだり尾の ながながし夜を ひとりかも寝む
近江の海 夕波千鳥 汝が鳴けば 心もしのに 古思ほゆ
小野小町
花の色は うつりにけりな いたづらに わが身世にふる ながめせしまに
思ひつつ 寝ればや人の 見えつらむ 夢と知りせば さめざらましを
与謝野晶子
君死にたまふことなかれ
やは肌の あつき血潮に ふれも見で さびしからずや 道を説く君
石川啄木
東海の 小島の磯の 白砂に われ泣きぬれて 蟹とたはむる
はたらけど はたらけど猶 わが生活 楽にならざり ぢっと手を見る
俵万智
この味がいいねと君が言ったから七月六日はサラダ記念日
万葉の あしたのしじみ 汁つくる わが手もとほし 夫よ飲め飲め
正岡子規
柿くへば 鐘が鳴るなり 法隆寺
いくたびも 雪の深さを 尋ねけり
俳句の疑問に関する記事
- 俳句の『漢字』の疑問
- 俳句の『切れ字』とは
- 俳句の『取り合わせ』とは
- 俳句の『句切れ』とは
- 俳句の『自由律俳句』とは
- 俳句の『有季定型』とは
- 昔の俳句で見られる「く」「ぐ」とは
- 昔の俳句で見られる「ゝ」「ゞ」「ヽ」「ヾ」とは
- 「俳句結社」の内容から探し方まで
- 俳句の『季重なり』とは
- 俳句の『季語』とは
- 俳句の『字余り・字足らず』とは
- 俳句の『吟行』とは
- 「俳句・川柳・短歌」の違い
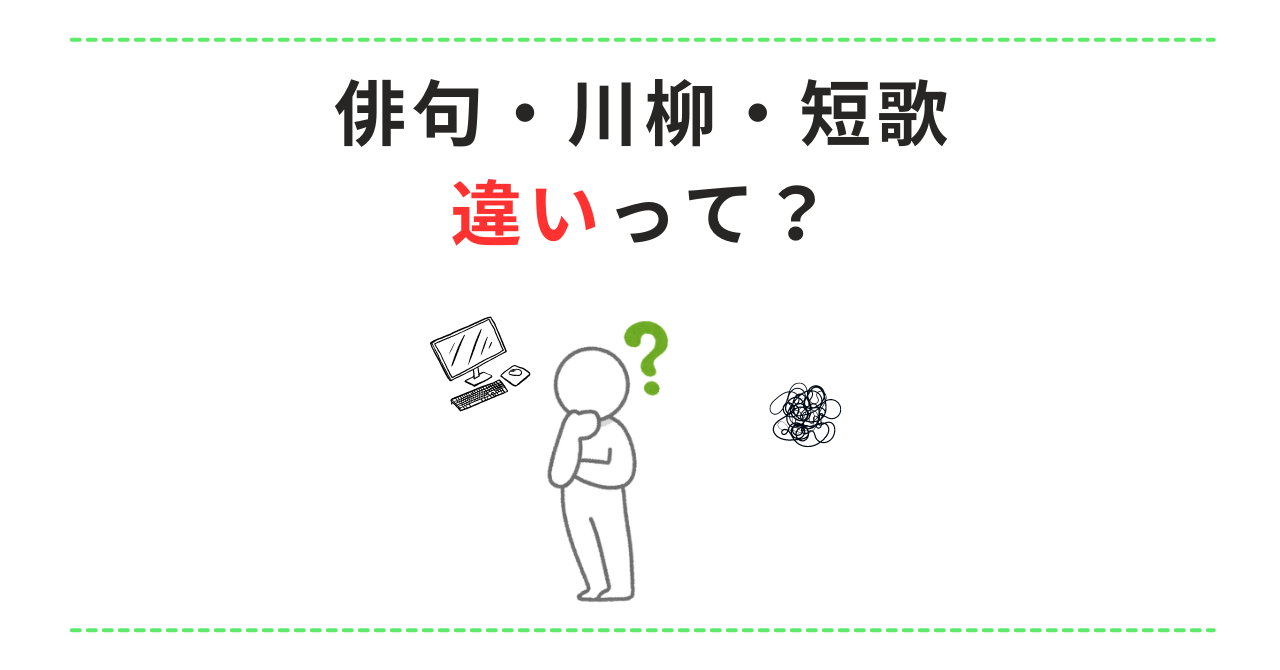
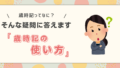

コメント