「月」を歳時記で調べると、「月」の他に「十六夜の月(いざよいのつき)」や「初月(はつつき)」と言った(子)季語も紹介されています
聞きなれない季語であるため、初めのうちは戸惑ってしまうのではないでしょうか
ここでは、初めて目にする季語でもすぐ使えるように、季語と共に意味をまとめています
意味を理解して使えるようになると、俳句の幅も広がるはずですし、俳句が楽しくなります
単に「月」といえば秋の季語なのですが、月は四季のそれぞれに別の顔を見せます
季節ごとの月の微妙な違いも理解しておくと良いと思います
秋の月
月(つき)
俳句では、単に「月」という場合、秋を指す
| ある僧の月を待たずに帰りけり 正岡子規 | 正岡子規の句集(Amazon) >> |
| ある時は月を古仏となしにけり 尾崎迷堂 | 尾崎迷堂の句集(Amazon) >> |
| あかあかと寶珠のごとき月のぼる 角川春樹 | 角川春樹の句集(Amazon) >> |
| ある僧の月を待たずに帰りけり 正岡子規 | 正岡子規の句集(Amazon) >> |
秋の月(あきのつき)
秋、澄んだ夜空に輝き冴えている月
単に「月」と言っても俳句では秋を指すので、「秋」を冠する必要はないのではないか?という意見もある
月よりも秋という季節を強調したいときに、「秋の月」と言ってもよいかもしれない
| ヴェランダから賞めあっている秋の月 望月富子 | - |
| 秋の月木蔭は闇を従へて 大野百子 | - |
孀娥(そうが)
月の異名。もとは仙女の名
月の輪(つきのわ)、月輪(げつりん)
特に、満月を指す
| 月の輪の立山熊や獵の月 石坂梢鳥 | - |
●●●形の違い●●●
新月(しんげつ)
一日目の月
太陽の方角にあって見られない月
| 新月の消耗するまで四畳半 田口鷹生 | - |
| 東京の新月を待つ異教徒ら 柿本妙子 | 柿本妙子の句集(Amazon) >> |
二日月(ふつかづき)
二日目の月
糸のように細い月
| 二日月死者の足裏は見えざりき 野間口千賀 | - |
| 二日月神州狭くなりにけり 渡邊水巴 | 渡邊水巴の句集(Amazon) >> |
三日月(みかづき)
三日目の月
太陽がしずむころ、西の低い空に見つかります
| 三日月に浅瀬はくだらないところ 佐藤文香 | 佐藤文香の句集(Amazon) >> |
| 三日月に添ふ春星の一しずく 中嶋秀子 | 中嶋秀子の句集(Amazon) >> |
上弦の月(じょうげんのつき)、弓張月(ゆみはりづき)
七日目の月
満月まんげつを縦たてに半分に切った形
弓の形に似にているところから「弓張月」と呼よばれ
夜中に西の空にしずむときに弓の弦つるが上にあります
| 上弦の月は兜か落城址 羽柴雪彦 | - |
十三夜(じゅうさんや)
十三日目の月
満月まんげつまであと少しの月
古くから豆や栗くりをお供そなえしてお月見が行われてきました
これから満みちていく様子が縁起の良よい月として親しまれてきました
| 十三夜頬杖か転寝か決める 森下草城子 | - |
| 半身の沈みしままや十三夜 照井翠 | 照井翠の句集(Amazon) >> |
| 市振の欠けたる家並十三夜 森野稔 | 森野稔の句集(Amazon) >> |
満月(まんげつ)、十五夜(じゅうごや)
十五日目の月
もっとも丸い状態になった月
太陽の光が月全体を照てらしているので月の明るさも一番強い
満月だけは一晩ひとばん中見ることができるのも大きな特徴
十五夜とも呼よばれる
| 一満月一韃靼の一楕円 加藤郁乎 | 加藤郁乎の句集(Amazon) >> |
| 久し振りいま満月を茹でている 品田まさを | - |
| 庭の池映る満月一人じめ 長谷川郁子 | 長谷川郁子の句集(Amazon) >> |
| 十五夜のみんな普通に生きる歌 中内亮玄 | - |
| 十五夜の鼻先にある薬壜 鹿又英一 | 鹿又英一の句集(Amazon) >> |
十六夜(いざよい)、十六夜の月(いざよいのつき)、いざよふ月(いざよふつき)
十六日目の月
月の出が十五夜より少しおそくなっているのを「月がはずかしがっている」と見立て「十六夜」と呼ばれています
新月に向かって、少しずつ欠かけていく月
| 十六夜の竹ほのめくにをはりけり 水原秋櫻子 | 水原秋櫻子の句集(Amazon) >> |
| 十六夜の紙が手紙となりにけり 宮本佳世乃 | 宮本佳世乃の句集(Amazon) >> |
立待月(たちまちづき)
十七日目の月
十六夜よりもさらにおそく、外に立って待っていたことから「立待月」と呼よばれる
新月に向かって、少しずつ欠かけていく月
居待月(いまちづき)
十八日目の月
満月まんげつを境さかいに月の出が次第におそくなり
座すわって月の出を待つことから「居待月」と呼よばれる
| 暗(くらが)りをともなひ上る居待月 後藤夜半 | 後藤夜半の句集(Amazon) >> |
| 曲屋の盗っ人となる居待ち月 中井不二男 | - |
寝待月(ねまちづき)、臥待月(ふしまちづき)
十九日目の月
この月はさらにおそくなり、寝て月の出を待つことから「寝待月」と呼よばれる
夜が明けるまで輝かがやいており、太陽がのぼる前まで西の空で白くすきとおったように見えます
| 寝待月夢で裏側覗かせる 加藤光樹 | 加藤光樹の句集(Amazon) >> |
| 平均寿命過ぎれば余禄寝待月 的井健朗 | - |
更待月(ふけまちづき)
二十日目の月
夜が更けてから月の出を待つところから「更待月」と呼ばれる
下弦の月(かげんのつき)
二十三日目の月
おそい時間にあらわれる月
左側半分が輝かがやいて見える
弓張月のひとつ
弓の弦つるを下にした形で地平に沈む
夜中の12時前後にのぼるので、観察するためにはおそくまで起きていないと見られない
| みの虫の痴情 下弦の月にぶらさがる 前原東作 | - |
二十六夜月(にじゅうろくやづき)
二十六日目の月
夜中の1時から3時の間にのぼり、夜が明けるころに空で白く輝かがやきます
三日月とは逆を向いており、うかんでいる場所も西ではなく東です
明けの三日月(あけのみかづき)
二十九日目の月
実際じっさいに私わたしたちが見られるのは、この日までの月
明け方に輝かがやいて見えるので「明けの三日月」と呼ばれる
半月(はんげつ)
半円形をした月。弦月。弓張り月とも
| 半月やドアの取っ手が痩せている 村田まさる | - |
| 半月や馬の背春の匂ひして 桜井誠司 | - |
●●●特定の時期の呼び方●●●
待宵月(まちよいづき)、待宵の月(まつよいのつき)
旧暦七月十四日の月
十五夜の前日で、満月を待つところから、この名がつく
盆の月(ぼんのつき)
旧暦七月 十五日の月
中秋の名月の一カ月前の満月
盂蘭盆会の夜であるため、特別な感慨を抱かせる
| 盆の月後ろを人の通りけり 野田哲夫 | - |
| 盆の月赤い紐より鎮められ 曾根毅 | 曾根毅の句集(Amazon) >> |
| ひとりつ子静かなりけり盆の月 小河原節子 | 小河原節子の句集(Amazon) >> |
| ふるさとの橋見えてきて盆の月 二橋満璃 | 二橋満璃の句集(Amazon) >> |
中秋の名月(ちゅうしゅうのめいげつ)、十五夜(じゅうごや)
旧暦八月 十五日の満月
十五夜とも呼ばれています
| 名月や見えざるものの降り注ぐ 高橋将夫 | 高橋将夫の句集(Amazon) >> |
| 名月や門の欅も武蔵ぶり 石田波郷 | 石田波郷の句集(Amazon) >> |
| ふたりしてちがう十五夜見ておりぬ 山本悦子 | 山本悦子の句集(Amazon) >> |
| 十五夜とむかふわたしといふひとり 三輪初子 | 三輪初子の句集(Amazon) >> |
初月(はつつき)
旧暦八月初めの月
| ほのぼのと渚は近江初月夜 阿波野青畝 | 阿波野青畝の句集(Amazon) >> |
| 初月を部屋の灯とする夜かな 木幡忠文 | 木幡忠文の句集(Amazon) >> |
後の月(のちのつき)、後の名月(のちのめいげつ)、名残の月(なごりのつき)、豆名月(まめめいげつ)、栗名月(くりめいげつ)
旧暦九月 十三夜の月
秋最後の月であることから名残の月
また豆や栗を供物とすることから豆名月、栗名月ともいう
| 太りたる猫を枕に後の月 前田美智子 | - |
| 表札の母の名消すや後の月 豊田まつり | - |
月待ち(つきまち)
月が昇るのを待って多くの人々が集まり、供え物をしたり拝んだりする行事。三日月待ち、十三夜待ち、十六夜待ち、などがある
●●●時間帯による違い●●●
有明の月(ありあけのつき)、有明月(ありあけつき)、残月(ざんげつ)
夜明け前、東の空から昇る二十六日前後の細い月を指す場合が多い
古くは朝立ちの旅人が有明の月の影を踏んで出立したというような風情を詠われた
| 有明の月に雲仙眠るかな 中川鬼一 | - |
| 有明の月の淡さを目で量り 押見淑子 | - |
| 兄の忌の有明月と六花 亀山歌子 | 亀山歌子の句集(Amazon) >> |
暁月(ぎょうげつ)
暁の空に残っている月
普通、下弦から二十六~二十七日月くらいをさす
有明よりも、空が少し明るくなった時間帯
暁月夜(あかつきづくよ)
暁月は月そのもののことだが
暁月夜は、暁月がみられる”夜”を指す
昼の月(ひるのつき)
青い空に、白雲のように浮かぶ月
上弦の月は昼頃に東の空から昇ります
昼過ぎから夕方にかけて、東~南の青空の中で簡単に見つけることができます
| 代掻きの親みえる場所昼の月 舘岡誠二 | 舘岡誠二の句集(Amazon) >> |
| 匿名のように兄いる昼の月 前田弘 | 前田弘の句集(Amazon) >> |
斜月(しゃげつ)
斜めに照らす月
西に沈もうとしている月
名残の月(なごりのつき)
夜明けの空に残る月
旧暦 九月十三夜(仲秋の名月の名残という意味か)の月をいう時もある
| 自在鉤名残の月に吊られけり 土谷とし雄 | - |
夕月(ゆうづき)
夕空に残る月。三日月が沈む時間が夕方であることから、三日月を指すことが多い
| 夕月や雪あかりして雑木山 藤田湘子 | 藤田湘子の句集(Amazon) >> |
| 夕月細るその極限の罪を負う 林田紀音夫 | 林田紀音夫の句集(Amazon) >> |
夕月夜(ゆうづきよ)
夕月のある”夜”を指す
| わが骨の髄はくれなゐ夕月夜 沼尻巳津子 | 沼尻巳津子の句集(Amazon) >> |
宵月(よいづき)
宵(日暮れの頃)の間だけ出ている月
宵月夜(よいづきよ、またはよいづくよ)
宵月のある”夜”を指す
朝月日(あさつきひ)
朝日の出た向かいに、月の残っていること
夕月日(ゆうつきひ)
秋の夕方の月
●●●見え方の違い●●●
素月(そげつ)
白く冴えた月、名月
白月(はくげつ)
白く輝く月、冬の寒々しい月
| 一教師たかが青天白月ぞ 香西照雄 | 香西照雄の句集(Amazon) >> |
明月(めいげつ)
曇りなく済みきった満月
| しぐれ濃し明月谷のことさらに 藤倉頼江 | - |
朗月(ろうげつ)
澄みわたった月
皓月(こうげつ)
白く照り輝く月。名月をさすことも
月白(つきしろ)
月が出ようとする時、空が明るくしらんで見えること
| 月白やひらく手帳の縦の罫 大澤玲子 | - |
| 月白や戯画の鳥獣掌にのぼれ 佐怒賀正美 | 佐怒賀正美の句集(Amazon) >> |
月光(げっこう)
月のひかり
| 月光に貧しき心持て余す 池田暎子 | 池田暎子の句集(Amazon) >> |
| しなやかに月光を跳ぶ猫若き 島田静子 | - |
| ひらひらと月光降りぬ貝割菜 川端茅舎 | 川端茅舎の句集(Amazon) >> |
月明り(つきあかり)
月の光。また、月の光で明るいこと
| 水鳥の夢宙にある月明り 飯田龍太 | 飯田龍太の句集(Amazon) >> |
| 漁師町鱗にのこる月明り 小松博 | - |
月光環(げっこうかん)
月のまわりに現れる光冠
月影(げつえい)
月の光
月の光にてらし出された人や物の陰影
薄月(うすづき)
薄い雲にさえぎられて、ほのかに光る月。 薄雲のかかった月
月の蝕(つきのしょく)、月食(げっしょく)、月蝕(げっしょく)
月が地球の本影の中に入って、月面の一部または全部が暗くなる現象
月の暈(つきのかさ)、月暈(つきがさ・げつうん)
月の周囲に現れる輪状の光暈。月の光が細かい氷の結晶からできている雲に反射・屈折して起こる
| 白桃も月の暈をも傷つけたり 佃悦夫 | - |
●●●空の状況による違い●●●
霽月(せいげつ)
雨上がりの月
雨月(うげつ)
名月の夜、雨が降って月が見えない様
| いつまでもサイレン降り止まぬよ雨月 中内亮玄 | - |
無月(むげつ)
名月の夜、むら雲がかかり月が見えないが、雲のどこかがほのかに明るくなっている様
薄月(うすづき)
薄雲がかかって、ほのかに光る月
月の鏡(つきのかがみ)
晴れわたった空にかかる満月。形を鏡と見立てた語
●●●映った月●●●
田毎の月(たごとのつき)
小さく区切られた階段状の水田(棚田)の一つひとつに映る月影
湖月(こげつ)
湖に映った月
| 根の国の近づいてくる湖月かな 曾根毅 | 曾根毅の句集(Amazon) >> |
水月(すいげつ)
水面に映った月
●●●心の状態を含めたもの●●●
胸の月(むねのつき)、心の月(こころのつき)
悟りを開いた心を、清く澄む月にたとえていう
心のさまを名月にたとえて言うため、季語となる
真如の月(しんにょのつき)
真如が一切の迷いを破ることを月が闇を照らすのにたとえた言葉
心のさまを名月にたとえて言うため、季語となる
●●●伝説などに関連するもの●●●
月の桂(つきのかつら)、月桂(げっけい)
中国の伝説。月に生えているという桂の木
桂男(かつらおとこ)
中国の伝説。月に住んでいるとされる伝説上の住人
月の兎(つきのうさぎ)、玉兎(ぎょくと)
月に兎がいる、という伝承に登場する兎
月の蛙(つきのかえる)
月にいるとされる蛙のこと
嫦娥(じょうが・こうが)
中国神話に登場する人物。后羿の妻
月の鼠(つきのねずみ)
象に追われた人が木の根を伝わって井戸に隠れたところ、井戸の周囲には4匹の毒蛇がいてかみつこうとし、また、木の根を黒と白2匹の鼠がかじろうとしていたという「賓頭盧 (びんずる) 説法経」にある説話で、象を無常、鼠を昼と夜、毒蛇を地・水・火・風の四大にたとえるところから
月日の過ぎゆくことを言う
月の都(つきのみやこ)
月の中にあるといわれる宮殿。月宮殿
月宮殿(げっきゅうでん)、月宮(げっきゅう)
伝説に登場する月にあるとされる宮殿
●●●その他●●●
遅月(おそづき)
月の出の遅いこと
満月を過ぎると、月の出は日に日に遅くなってゆく
月の出(つきので)
月が東から出ること。また、その時刻
| 月の出や印南野に苗余るらし 永田耕衣 | 永田耕衣の句集(Amazon) >> |
| 月の出や口をつかいし愛のあと 江里昭彦 | 江里昭彦の句集(Amazon) >> |
月の入り(つきのいり)
月が西に沈むこと。また、その時刻
月夜(つきよ)
月の照っている夜
月の美しい夜
| びしよぬれのKが還つてきた月夜 眞鍋呉夫 | 眞鍋呉夫の句集(Amazon) >> |
| ふる郷は波に打たるゝ月夜かな 吉田一穂 | 吉田一穂の句集(Amazon) >> |
月の顔(つきのかお)
月のおもて。月の表面
袖の月(そでのつき)
涙にぬれた袖に映った月
月の出潮(つきのでしお)
月が出るとともに満ちてくる潮
月渡る(つきわたる)
月が渡ること
| 鳥渡り月渡る谷人老いたり 金子兜太 | 金子兜太の句集(Amazon) >> |
月下(げっか)
月の光がさしている所
| 鮭跳ねて月下に銀のしぶき散る 木幡忠文 | 木幡忠文の句集(Amazon) >> |
| 徐々に徐々に月下の俘虜として進む 平畑静塔 | 平畑静塔の句集(Amazon) >> |
冬の月
冬の月(ふゆのつき)
冬の月の光には、研いだ刃物のような鋭さがある
ぞくっとする美しさの前に、身じろぎすらできなくなるような気がする
| 雲を染め雲を割らむや冬の月 篠田清美 | 篠田清美の句集(Amazon) >> |
| もう一度女を起こす冬の月 杉浦圭祐 | - |
| るにんなる意識過剰の冬の月 小柳いつ子 | - |
寒月(かんげつ)
寒の内の月に限らず、寒空にかかる月一般を指す
寒さによる心理的な要因もあってか荒涼とした寂寥感が伴う
雲が吹き払らわれた空のすさまじいまでの月の光には誰しもが心をゆすられる思いがあるだろう
| 寒月にひしめく石を何故去らぬ 赤城さかえ | 赤城さかえの句集(Amazon) >> |
| 寒月に水捨つひとの華燭の日 桂信子 | 桂信子の句集(Amazon) >> |
| 寒月下鬼女ならずとも刃物研ぐ 吉田未灰 | 吉田未灰の句集(Amazon) >> |
月冴ゆ(つきさゆ)
月冴ゆとなると、通常の冬の月よりも寒々しさが一層増す
月の寒々しさを詠みたいときの表現の一つである
| 月冴ゆる一度は見たき棺造り 小檜山繁子 | 小檜山繁子の句集(Amazon) >> |
| 胸うちに石積む地獄月冴ゆる 大西岩夫 | - |
月氷る(つきこおる)
月氷るともなると、通常の冬の月よりも寒々しさが一層増す
月の寒々しさを詠みたいときの表現の一つである
| 月氷る古鏡にふたりの祖母の貌 糸山由紀子 | 糸山由紀子の句集(Amazon) >> |
冬三日月(ふゆみかづき)
眉のように細い月であり、特に冬三日月は薄氷のごとく
いまにも壊れてしまいそうなもろさがある
| 寂しくば寄り添ひてゆけ冬三日月 池田暎子 | 池田暎子の句集(Amazon) >> |
| 冬三日月のふたつの尖り繋ぎたし 花谷清 | 花谷清の句集(Amazon) >> |
| 冬三日月更に呑むため別れゆく 寺井谷子 | 寺井谷子の句集(Amazon) >> |
月天心(つきてんしん)
冬の月は高度が高く、真上を通るように見えることから月天心と呼ばれる
ただ、高度が高いのは満月であり、冬三日月になるほど高度は低くなる
| 月天心ちぎってパンを山にする 村井和一 | - |
| 月天心もとにはちょっともどれない 森さかえ | 森さかえの句集(Amazon) >> |
春の月
朧月(おぼろづき)
春の夜の朧な月をいう
澄んだ秋の月に対し、水分の多い春の季節の月は水蒸気のベールがかかったように見える
秋の煌々と照る月とは対照的に、滲んだ輪郭で重たげに上る月である
暈のかかることもある(月暈(ゲツウン))
ただし、月暈は雨の降った後の月ではよく見られるため、それだけで季語になることはない
| 夜の魚跳ねて大きな朧月 加藤知子 | 加藤知子の句集(Amazon) >> |
| 寝床から子規も見たでしょ 朧月 近藤千恵子 | - |
| ゆつたりと母偲ぶ今日おぼろ月 長谷川郁子 | 長谷川郁子の句集(Amazon) >> |
月朧(つきおぼろ)
朧月と同義である
朧月は ”朧の月” というように、月そのものを指しているが
月朧は ”月が朧に見える” 状態を指している
朧月 = 朧月(名詞)
月朧 = 月(名詞)朧(形容動詞)
名詞で詠むか、形容動詞を含めて詠むかの違いとも言える
| ひとが夢語るとき月朧にて 前田霧人 | 前田霧人の句集(Amazon) >> |
| 月朧黒い電話が鳴っている 松原静子 | - |
朧月夜 (おぼろづきよ)
「おぼろづきよ」または「おぼろづくよ」と読む
朧月の出ている夜を指す
朧月は月そのものを指すが、朧月夜は朧月の出ている夜を指す
| 鶫旅立つ朧月夜の朧の軀 金子皆子 | 金子皆子の句集(Amazon) >> |
朧夜(おぼろよ)
朧月夜を略した語
| 朧夜のむんずと高む翌檜 飯田龍太 | 飯田龍太の句集(Amazon) >> |
| 朧夜の五指しなやかに火をつかひ 河野多希女 | 河野多希女の句集(Amazon) >> |
淡月(たんげつ)
朧月と同義である
光の薄い(淡い)月ということから淡月と呼ばれる
句の中で光の濃淡が重要な場合には”淡月”を使う
春の月(はるのつき)、春月(しゅんげつ)
春の夜に見られる月
| あしらいは小指でつつく春の月 白木暢子 | - |
| いつよりか薄く重たし春の月 飯田枝美子 | 飯田枝美子の句集(Amazon) >> |
春満月(はるまんげつ)
春の夜に出る満月
| 函嶺に春満月や酔ひて帰る 山岸文明 | - |
| 戦あり春満月の昇りくる 浅生圭佑子 | - |
春月夜(はるづきよ)
「はるづきよ」または「はるづくよ」と読む
春月の出ている夜を指す
春月は月そのものを指すが、春月夜は春月の出ている夜を指す
| 蝶番ゆるめて眠る春月夜 渡辺郁子 | - |
夏の月
夏の月(なつのつき)
夜半の眼ざめに見る月
短夜の曙の闇に残る月である
暑さを避け涼むために、夏は月を見る機会が多い
暮時に地平に昇る夏の月は、赤々と火照るような感じがする
| たまゆらの草の匂や夏の月 山中恵子 | - |
| ためらい傷ほどの痛みや夏の月 柴崎ゆき子 | - |
夏の霜(なつのしも)
夏の月影を霧に見立てて”夏の霜”という
月涼し(つきすずし)
夏の夜といっても暑苦さに変りはないが、暑い昼が去り
夏の夜空に青白く輝く月には涼しさを感じさせる
| 月涼し僧も四条へ小買物 川端茅舎 | 川端茅舎の句集(Amazon) >> |
| 過去の日々篩にかけて月涼し 赤堀睦枝 | - |
梅雨の月(つゆのつき)
雨雲に閉ざされがちな梅雨に、ふと現れる月である
長い間月を見えない日が続くと、今日が満月であったかと驚くこともある
多くは雲に見え隠れする
| 梅雨の月皓々と雲寄せつけず 中嶋秀子 | 中嶋秀子の句集(Amazon) >> |
| 長巻の繃帯ゆるみ梅雨の月 沼尻巳津子 | 沼尻巳津子の句集(Amazon) >> |
その他
季節ごとの月の軌道
月の位置は、同じ季節でも、満月と新月によって、通る軌道が変わります
新月
| 春・秋分 | 南中高度は中間 (太陽と同じく赤道付近にいるため) |
| 夏至 | 南中高度は高い (夏の太陽の軌跡をたどるため) |
| 冬至 | 南中高度は低い (冬の太陽の軌跡をたどるため) |
満月
| 春・秋分 | 南中高度は中間 (太陽と同じく赤道付近にいるため) |
| 夏至 | 南中高度は低い (冬の太陽の軌跡をたどるため) |
| 冬至 | 南中高度は高い (夏の太陽の軌跡をたどるため) |
季節ごとの月の出ている時間
| 春・秋分 | 18時~6時 |
| 夏至 | 19時~5時 |
| 冬至 | 17時~7時 |
(※満月の出ている時間)
月の有名な俳句
月の有名な俳句はいろいろありますが、個人的に好きな月の俳句です
| やはらかき身を月光の中に容れ 桂信子 | 桂信子の句集(Amazon) >> |
| 大原や蝶の出て舞ふ朧月 内藤丈草 | - |
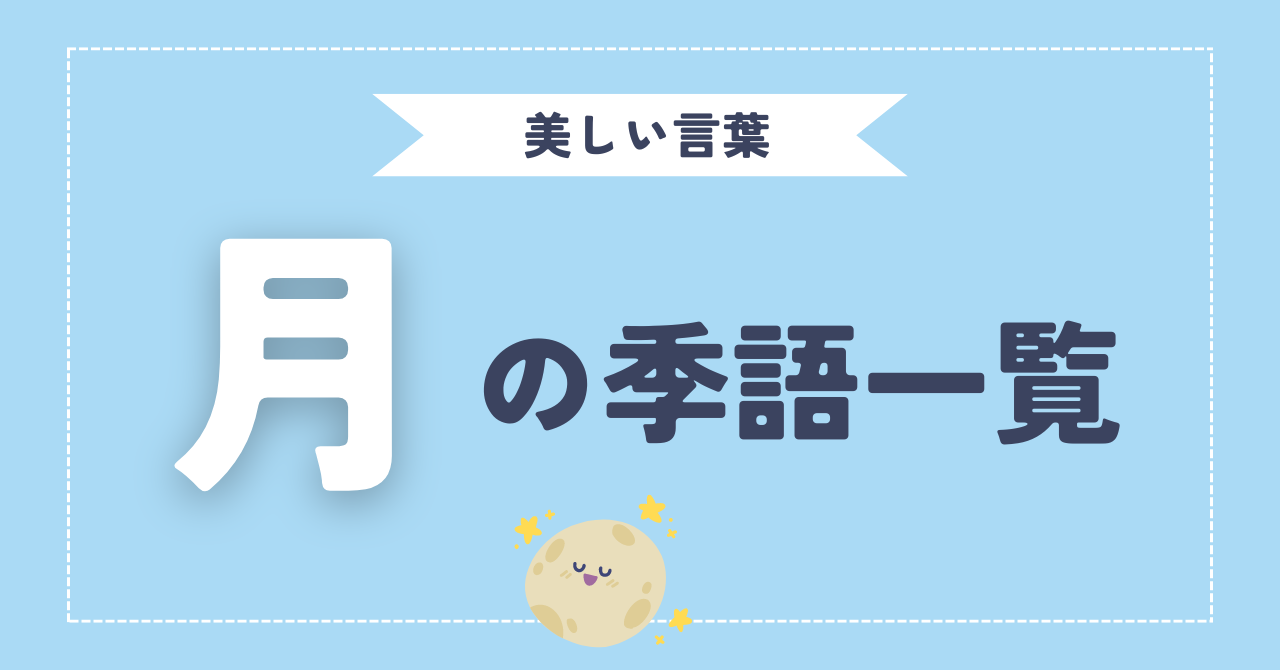

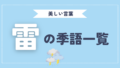
コメント