俳句では桜といえば春の季語になります
冬に見られる桜は「冬桜」と呼ばれます
桜に関連する季語には、桜蘂降る、花筏といった、少し意味の分かりづらいものもあります
この記事では、桜の関連季語と意味をまとめまていますので、俳句を作る際のさんこうになさってください
春の季語の一覧 >>>
- 春の桜
- 桜(さくら)
- 花(はな)
- 若桜(わかざくら)
- 姥桜(うばざくら)
- 千本桜(せんぼんざくら)
- 庭桜(にわざくら)
- 一重桜(ひとえざくら)
- 御所桜(ごしょざくら)
- 楊貴妃桜(ようきひざくら)
- 左近の桜(さこんのさくら)
- 深山桜(みやまのさくら)
- 里桜(さとざくら)
- 南殿(なんでん)
- 大島桜(おおしまざくら)
- 上溝桜(うわみずざくら)
- 染井吉野(そめいよしの)
- 桜月夜(さくらづきよ)
- 桜の園(さくらのその)
- 桜山(さくらやま)
- 山桜(やまざくら)
- 初桜(はつざくら)
- 嶺桜(みねざくら)
- 犬桜(いぬざくら)
- 吉野桜(よしのざくら)
- 遅桜(おそざくら)
- 桜散る(さくらちる)
- 花吹雪(はなふぶき)
- 吉原の夜桜(よしわらのよざくら)
- 桜蘂降る(さくらしべふる)
- 八重桜(やえざくら)、牡丹桜(ぼたんざくら)
- 枝垂桜(しだれざくら)、糸桜(いとざくら)、しだり桜(しだりざくら)、紅枝垂(べにしだれ)
- 彼岸桜(ひがんざくら)、枝垂彼岸(しだれひがん)、江戸彼岸(えどひがん)、姥彼岸(うばひがん)
- 桜人(さくらびと)、花人(はなびと)、花見人(はなみびと)
- 老桜(ろうざくら)
- 桜狩(さくらがり)、桜見(さくらみ)、観桜(かんおう)
- 夜桜(よざくら)
- 桜まじ(さくらまじ)
- 桜衣(さくらごろも)、桜がさね(さくらがさね)
- 花筏(はないかだ)
- 夏の桜
- 冬の桜
- その他の桜
- 桜の有名な俳句
- 四季でみられる季語の関連記事
春の桜
桜(さくら)
桜といえば春の季語
古来より詩歌に歌われ、日本人に愛されてきた花である
もともとは、山野に自生する野生種であったが、江戸末期から明治にかけて、栽培種である染井吉野が誕生し、広く分布している
| からかさをひらけば雨の桜かな 齊藤美規 | 齊藤美規の句集(Amazon) >> |
| この土や桜咲く国わが住む国 細木芒角星 | - |
花(はな)
俳句で「花」といえば桜を指す
| あしおとの花のさかりへまぎれこむ 松澤昭 | 松澤昭の句集(Amazon) >> |
| ありがとう花に心を託すかな 伊藤哲子 | - |
若桜(わかざくら)
生えてからまだ年数の経っていない木の桜。また、若木の桜をいう。
姥桜(うばざくら)
葉が出るより先に花が開く桜の通称。「歯なし」にかけたもの
ヒガンザクラ・ウバヒガンなどがある
千本桜(せんぼんざくら)
吉野山(奈良県)の花盛りを称える表現であるが、桜の木が沢山植えられている名所および、その花盛りに対しても使われる
形容表現として一目千本桜などと称されることもあり、現在では、日本の各地に「千本桜」と称する名所が存在する
庭桜(にわざくら)
ニワウメの変種
葉が細長く、上面にしわがあり、花は白色で八重咲き
| 庭桜 暮天に色を深めおり 佐野二三子 | - |
一重桜(ひとえざくら)
花が単弁の桜
御所桜(ごしょざくら)
サクラの一品種。八重の大形の花が五輪ずつ群がって咲く
楊貴妃桜(ようきひざくら)
サトザクラの一品種。花は八重で4月ころ咲き、花びらは淡紅色であるが先端は濃紅色。奈良興福寺の僧玄宗が愛でたことからの名という
| よく笑う妻いて楊貴妃桜咲く 益田清 | - |
左近の桜(さこんのさくら)
紫宸殿(ししんでん)の階段の下、東方に植えられている桜
深山桜(みやまのさくら)
深山に生え、5月ごろ、若葉が出てから白い5弁花を総状につける
葉は長円形で先がとがる
シロザクラとも呼ばれる
里桜(さとざくら)
オオシマザクラに由来する桜の園芸品種の総称。八重咲きで、花の色が白・黄・紅色など多くの品種がある
| せせらぎのたたきだしたる里桜 松澤昭 | 松澤昭の句集(Amazon) >> |
南殿(なんでん)
サトザクラの一品種
葉の裏面に毛が密にある。花は八重または半八重で淡紅色
大島桜(おおしまざくら)
日本の固有種で、日本に10種あるサクラ属基本野生種のうちの一つ
花は大輪、一重咲きで白色。開花期は3月下旬。伊豆七島や房総半島などに自生して、潮風に強い桜
上溝桜(うわみずざくら)
ヨーロッパ北部とアジア北部に自生するサクラの一種
古代の亀卜(亀甲占い)で溝を彫った板(波波迦)に使われた事に由来する
染井吉野(そめいよしの)
日本固有種のオオシマザクラの雑種の交配で生まれた日本産の園芸品種のサクラ
| 胸そらしそのまま染井吉野かな 五島高資 | 五島高資の句集(Amazon) >> |
桜月夜(さくらづきよ)
桜の咲いている月夜
桜の園(さくらのその)
桜の咲いている庭
桜山(さくらやま)
桜の咲いている山
| 百人が眉そってゆく桜山 あざ蓉子 | あざ蓉子の句集(Amazon) >> |
山桜(やまざくら)
日本に自生するサクラの野性種
バラ科サクラ属の落葉高木
| 会ひにゆくおのれの一樹山桜 加藤一雄 | - |
| 山又山山桜又山桜 阿波野青畝 | 阿波野青畝の句集(Amazon) >> |
初桜(はつざくら)
その年に初めて咲いた桜の花
咲いて間もない桜の花
| 実朝の海あをあをと初桜 高橋悦男 | 高橋悦男の句集(Amazon) >> |
| 極楽や二丁目一の初桜 石井国夫 | - |
嶺桜(みねざくら)
バラ科の落葉小高木。本州中部以北の高山に自生
サクラの仲間では最も高いところに生育する桜の野生種
樹木としてはあまり大きく育たず、高くても5~10m程にしかならない
赤褐色の葉が開くのと同時に淡紅紫色の花をつける
犬桜(いぬざくら)
樹皮は暗灰色でつやがあり、春、白い小花を密につけるが、見劣りするのでこの名がある
実は黄赤色から黒紫色に変わる
吉野桜(よしのざくら)
吉野山に咲くヤマザクラ
ソメイヨシノの別名
遅桜(おそざくら)
花時に遅れて咲く桜のこと
行春を惜しむ思いが重なる
| ちちははの世へ一歩づつ遅桜 佐藤博美 | 佐藤博美の句集(Amazon) >> |
| 乾杯や伊豆の山山遅桜 森節子 | - |
桜散る(さくらちる)
桜の花が散ること
| 道化師の顔に散りゆく桜かな 小河原節子 | 小河原節子の句集(Amazon) >> |
| 梵鐘の鳴りてはらりと散る桜 木幡忠文 | 木幡忠文の句集(Amazon) >> |
花吹雪(はなふぶき)
桜の花が一斉に散る様子を吹雪に例えた言葉
吉原の夜桜(よしわらのよざくら)
遊郭吉原の夜桜見物のこと
その日のためにわざわざ見ごろとなる桜を植えて、終われば抜くという手の込んだものだったという
桜蘂降る(さくらしべふる)
花が散り終わったあと、こまやかな桜の蘂が降ることをいう
花蘂が降るころのひそやかさは、花の頃とは別の趣がある
| 桜蘂降るがやがや記号騒がしい 白石司子 | - |
| 桜蘂降る東北のこと語らざる 星野昌彦 | 星野昌彦の句集(Amazon) >> |
八重桜(やえざくら)、牡丹桜(ぼたんざくら)
八重咲きの桜
花期は遅く、四月末から五月上旬にかけて開花する
ぼってりとした花房はほかの桜とは異なった艶やかさをもつ
花の姿が牡丹と似ていることから牡丹桜とも呼ばれる
| おむすびの中のつめたし八重桜 関戸美智子 | 関戸美智子の句集(Amazon) >> |
| だく点の笑ひ出したる八重桜 渡邉紅華 | - |
枝垂桜(しだれざくら)、糸桜(いとざくら)、しだり桜(しだりざくら)、紅枝垂(べにしだれ)
エドヒガンの一変種で観賞用園芸種
薄紅色の花を垂れ下った枝につけるが、特に花色の濃いものを紅枝垂と呼ぶ
| 天蓋のしだれざくらに立ち眩む 綾野道江 | - |
| 誉め言葉枝垂桜に使いきる 吉田孝子 | - |
| 咲き満ちて光ゆらすも糸桜 佐藤邦子 | 佐藤邦子の句集(Amazon) >> |
彼岸桜(ひがんざくら)、枝垂彼岸(しだれひがん)、江戸彼岸(えどひがん)、姥彼岸(うばひがん)
春の彼岸の頃咲くのでこの名がある
花はソメイヨシノにくらべると、白っぽくややこぶりでパラパラとした感じに咲く
| 首塚に日のある彼岸桜かな 久米正雄(三汀) | 久米正雄(三汀)の句集(Amazon) >> |
桜人(さくらびと)、花人(はなびと)、花見人(はなみびと)
花見をする人の総称
桜を待つ人、桜を愛でる人、桜を尋ねる人など様々
| 九条の枝を手折るか桜人 大平星雲 | - |
老桜(ろうざくら)
樹齢70年を超える、年老いた桜
| 一心に咲いて降らせる老桜 木幡忠文 | 木幡忠文の句集(Amazon) >> |
桜狩(さくらがり)、桜見(さくらみ)、観桜(かんおう)
花に誘われて、野や山に桜を訪ね歩いて愛でること
| 桜狩いつか死ぬ人ばかりくる 前川弘明 | - |
夜桜(よざくら)
夜の桜、また夜の花見をいう
篝火を焚くところもあり、闇中に浮かび上がる桜は昼間とは異なる美しさを持っている
| たつぷりと夜桜を見し深眠り 川島芳江 | 川島芳江の句集(Amazon) >> |
| 夜桜にひとりでゐると耳が散る 林桂 | 林桂の句集(Amazon) >> |
桜まじ(さくらまじ)
桜の花の咲く頃に南から吹いてくる暖かい風のこと
まじは偏南風の地方の呼び名で、瀬戸内海、広島県あたりで多く使われる
桜衣(さくらごろも)、桜がさね(さくらがさね)
襲の色目一つ桜襲の衣をいう
表が白、裏が赤の春の衣
花筏(はないかだ)
水面に散る浮かんでいる桜の花びらを筏(いかだ)に見立てたもの
| うはさ話尾鰭をつけて花筏 平佐和子 | - |
| しんがりに昭和一桁花筏 山崎聰 | - |
夏の桜
葉桜(はざくら)、桜若葉(さくらわかば)
花が散って若葉となったころの桜をいう
花が散って葉桜になってしまったという惜しむ思いと、桜若葉の美しさを愛でる思いが交錯する季語である
| 葉ざくらの等高線にかさなりて 新関幸至 | - |
| 葉ざくらや廃坑が吐く白地熱 難波江昇 | 難波江昇の句集(Amazon) >> |
花は葉に(はなははに)
桜の花が葉に変わった様子を指す言葉
葉桜を眺めながらも散り果てた花を忍ぶ思いがある
| 声掛けて体位交換花は葉に 岩永千恵子 | - |
| 歳時記は疲れています花は葉に 長谷川栄子 | - |
実桜(みざくら)、桜の実(さくらのみ)
桜の花が散った後に結ぶ小さな実
| 実桜や実らぬ恋の哲学道 堺玲子 | 堺玲子の句集(Amazon) >> |
氷室の桜(ひむろのさくら)、氷室の花(ひむろのはな)
氷室のある辺りで夏になって咲く桜をいう
また春咲いた花を氷室に入れて保存しておくことという解釈もある
| 魂うばふ氷室の桜ふぶくとき 大岳水一路 | 大岳水一路の句集(Amazon) >> |
冬の桜
冬桜(ふゆざくら)
冬に咲く桜のこと
| まだ冬の桜並木に靴ひからす 横山白虹 | 横山白虹の句集(Amazon) >> |
| 汝はをんな冬の桜の声あげて 永井江美子 | 永井江美子の句集(Amazon) >> |
寒緋桜(かんひざくら)、緋寒桜(ひかんざくら)
冬に咲く桜のひとつ
旧暦正月あたりに咲くことからガンジツザクラ(元日桜)とも呼ばれる
| 寒緋桜地を這うような炸裂音 宮里晄 | - |
| 抱き上ぐ寒緋桜の高さまで 水野二三夫 | - |
緋桜(ひざくら)
寒緋桜の別称
元日桜(がんじつざくら)
寒緋桜の別称
その他の桜
冬木の桜(ふゆきのさくら)、枯桜(かれざくら)
冬枯の桜をいう
色とりどりに美しい桜紅葉が散り尽くしたのち、桜は枯れ姿になる
華やかな花時をおもかげに、枯れた姿にも趣が感じられる
返り花や冬桜とは違うので間違えて使わないようにしてください
桜の有名な俳句
桜の有名な俳句はいろいろありますが、個人的に好きな桜の俳句です
| 中空にとまらんとする落花かな 中村汀女 | 中村汀女の句集(Amazon) >> |
| 葉桜の中の無数の空さわぐ 篠原梵 | - |


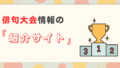
コメント