単に蝶というと、俳句では春の季語になります
夏・秋・冬で蝶を季語として使う場合は、季節を冠して夏蝶・秋蝶・冬蝶と呼びます
ここでは、四季でみられる蝶の種類や、蝶に関連する言葉を31個紹介していきます
俳句をされている人は、季語の理解が深まり、俳句作りが楽しくなります
昆虫が好きな人は、いろいろな言葉を知ることで、蝶に対する愛着がさらに増すと思います
春の蝶
蝶(ちょう)、蝶々(ちょうちょう)
蝶は、蝶(ちょう)のほか、蝶々(ちょうちょう)とも呼ばれます
「ちょうちょう」は話し言葉で使われることが多い呼び名です
ちなみに、「ちょうちょ」は、「ちょうちょう」の音変化です
俳句では昔の呼び方の蝶(てふ)、蝶々(てふてふ)が使われます
種類は、モンシロチョウ、スジグロシロチョウ、ツマキチョウモンシロチョウなどあります
| あてどなく急げる蝶に似たらずや 藤田湘子 | 藤田湘子の句集(Amazon) >> |
| あをあをと空を残して蝶分れ 大野林火 | 大野林火の句集(Amazon) >> |
| いつの間にわが抽出しを出でし蝶 谷元左登 | - |
| 羽ばたきの迷ふことなき春の蝶 篠田清美 | 篠田清美の句集(Amazon) >> |
胡蝶(こちょう)
蝶(ちょう)の昔の名前です
| すき通るほどの握手や胡蝶蘭 田口佐江 | - |
| 宇治川をわたりおほせし胡蝶かな 高浜虚子 | 高浜虚子の句集(Amazon) >> |
蝶生る(ちょううまる)
蝶が生まれること
秋と春に蝶は羽化しますが、俳句では春に羽化するものを指します
「生る(うまる)」は「生れる(うまれる)」文語形で、俳句の中で使われる言葉です
| 紋白蝶生るればすぐに影もらふ 服平知草 | - |
| 約束の一つもなしに蝶生れる 大野黎子 | - |
初蝶(はつちょう)
春になって初めて目にする蝶をいいます
| あ初蝶こゑてふてふを追ひにけり 川崎展宏 | 川崎展宏の句集(Amazon) >> |
| きのふ見し初蝶けふの鬱の中 三輪初子 | 三輪初子の句集(Amazon) >> |
眠る蝶(ねむるちょう)
夜になり眠っている蝶をいう
枝先や葉の後ろに逆さになっているのを観察できる
狂う蝶(くるうちょう)
狂ったようにあちこちに飛び回る蝶を言います
俳句の季語として掲載されています
双蝶(そうちょう)
二匹で舞っている蝶
| 双蝶の一つは影をすてゆけり 宮森碧 | - |
小灰蝶(しじみちょう)、蜆蝶(しじみちょう)
シジミチョウ科のチョウ
一般に小形で色彩は豊か
ルリシジミ・ヤマトシジミ・ミドリシジミ・オナガシジミなどがある
| 蜆蝶きらきら捨てるあやされる 徳永希代子 | - |
白蝶(しろちょう)
シロチョウ科のチョウの総称
翅(はね)は白色が多く、後ろ翅に突起がない
モンシロチョウ・モンキチョウ・ツマキチョウ・ツマベニチョウなどがある
| 白蝶々一言ならば届けると 飯村恭代 | - |
| 白蝶の己が軌跡をなぞるとき 堀田季何 | 堀田季何の句集(Amazon) >> |
黄蝶(きちょう)
翅は黄色く、夏型では前翅の黒い縁どりが目立つ
| おんまから黄蝶二頭の恋あそび 八木和子 | - |
| 黄蝶に促される体土弄り 平田直樹 | - |
紋白蝶(もんしろちょう)
白色で、前羽の先に二点、後ろ羽の縁(ふち)の中央あたりに一点の黒点がある
| 紋白蝶すぐ斬新に惨死せり 佃悦夫 | - |
| 紋白蝶来て懐に入り給う 羽石昭子 | 羽石昭子の句集(Amazon) >> |
紋黄蝶(もんきちょう)
早春に見られる蝶で、雄の翅が黄色
岐阜蝶(ぎふちょう)、だんだら蝶(だんだらちょう)
岐阜県で発見されたチョウ
黄色と黒のだんだら模様があることから、だんだら蝶とも言う
立羽蝶(たてはちょう)
中形のチョウで活発に飛ぶ
止まると翅(はね)を立て下げすることが名の由来
赤立羽蝶(あかたてはちょう)
黒色の翅に赤色が一部広がったタテハチョウ
瑠璃立羽蝶(るりたてはちょう)
開張6センチメートル
翅は開くとあでやかな青色だが、閉じると地味
緋縅蝶(ひおどしちょう)
タテハチョウ科のチョウ
表面は朱褐色に黒斑があり、外縁に黒色帯がある
夏の蝶
夏の蝶(なつのちょう)、夏蝶(なつちょう)
夏に見かける蝶
俳句では単に蝶というと春を指すので、夏に見る蝶は「夏」を冠して呼ぶ
アゲハチョウなどが多い
| この道の果ては洋館夏の蝶 岸本由香 | - |
| 夏の蝶らしく疲れた白い紙 川崎千鶴子 | - |
| 花よりも翅を広げて夏の蝶 木幡忠文 | 木幡忠文の句集(Amazon) >> |
揚羽蝶(あげはちょう)、鳳蝶(あげはちょう)
あげはちょう科に属するちょうの総称
黄色の翅に黒い筋や黒いまだらを持つ
| 嘘のやう影のやうなる黒揚羽蝶 岩淵喜代子 | 岩淵喜代子の句集(Amazon) >> |
| 壺の蜜ゆるみはじめる揚羽蝶 桂信子 | 桂信子の句集(Amazon) >> |
梅雨の蝶(つゆのちょう)
梅雨の晴れ間をとぶ蝶
特に種類が決まっているわけではない
| ひと筋の光となりて梅雨の蝶 門野ミキ子 | - |
| 低く翔ぶ高層都市の梅雨の蝶 三谷昭 | 三谷昭の句集(Amazon) >> |
挵蝶(せせりちょう)
小形で、体が太くガに似る
色彩は褐色や黒色などで地味
蛇目蝶(じゃのめちょう)
翅に蛇の目模様をもつ蝶
斑蝶(まだらちょう)
中形から大形の蝶
翅にさまざまな斑紋を持つことが名の由来
| 斑蝶斑蛾斑蝶斑 堀田季何 | 堀田季何の句集(Amazon) >> |
大紫(おおむらさき)
大形で美しい紫色の翅を持つ蝶
クヌギなどの樹液に集まるのを観察できる
| 磨崖佛おほむらさきを放ちけり 黒田杏子 | 黒田杏子の句集(Amazon) >> |
高山蝶(こうざんちょう)
高山帯に分布するチョウ
アサヒヒョウモン・ウスバキチョウ・タカネヒカゲ、ミヤマモンキチョウなどがある
秋の蝶
秋の蝶(あきのちょう)、秋蝶(あきちょう)
秋に見かける蝶
俳句では単に蝶というと春を指すので、秋に見る蝶は「秋」を冠して呼ぶ
数は減るが、秋の花野にはまだ見かける蝶を言う
| 海鳴りやまうしろに来る秋の蝶 須藤徹 | 須藤徹の句集(Amazon) >> |
| 片男波潮満ち来らし秋の蝶 川上万里 | - |
老蝶(おいちょう、ろうちょう)
立秋を過ぎてから見かける蝶
春や夏の蝶にから比べるといくらか弱々しい印象を受けることから老蝶と呼ぶ
冬の蝶
冬の蝶(ふゆのちょう)
冬の暖かい日に見られる蝶をいう
俳句では単に蝶というと春を指すので、冬に見る蝶は「冬」を冠して呼ぶ
暖かい地域では、越冬する蝶を見ることができる
| 冬の蝶はんこを持って上野へ行く 大畑等 | - |
| 冬の蝶睦む影なくしづみけり 西島麦南 | 西島麦南の句集(Amazon) >> |
凍て蝶(いてちょう)
冬にじっと動かないでいる蝶を、凍てているように見立てた言葉
| 凍て蝶の宿になりしか石仏 小磯國雄 | - |
| 凍て蝶や五次元世界いづくにか 林信江 | 林信江の句集(Amazon) >> |
蝶の有名な俳句
蝶の有名な俳句はいろいろありますが、個人的に好きな蝶の俳句です
| あをあをと空を残して蝶別れ 大野林火 | 大野林火の句集(Amazon) >> |
| 閉ぢし翅しづかにひらき蝶死にき 篠原梵 | - |
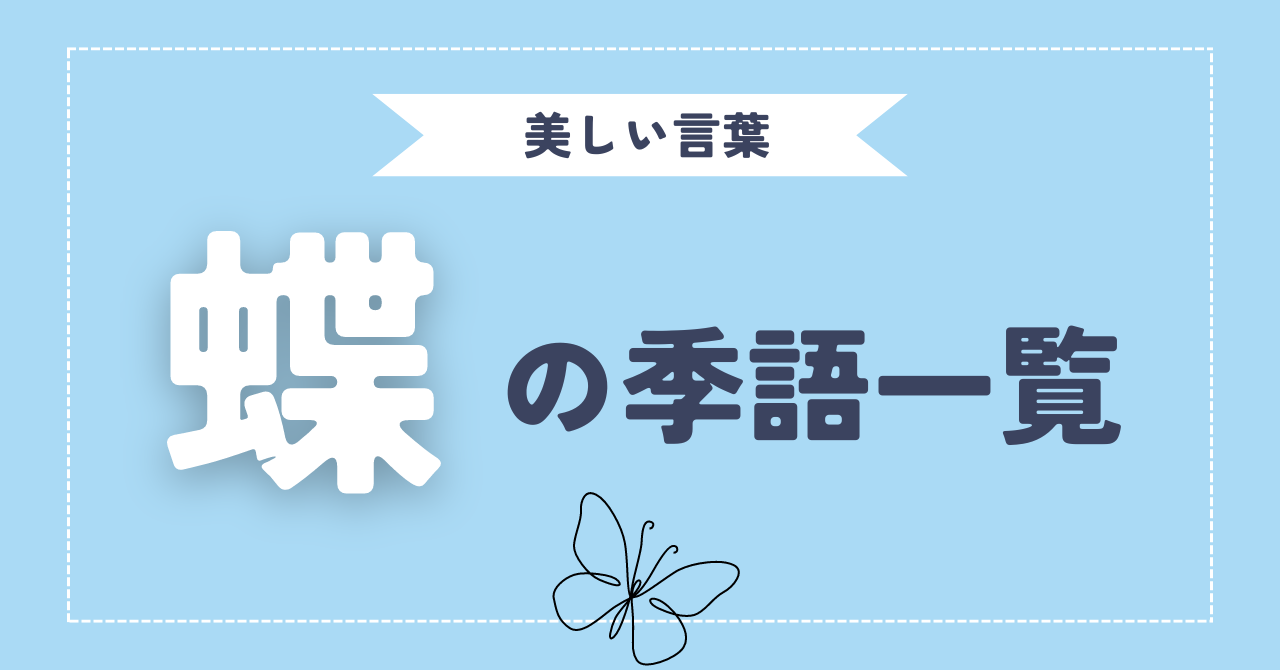


コメント