俳句の切れ字「や」の使い方をマスターしていきましょう。
「や」という、たった一つの言葉を加えるだけで、俳句の世界は大きく変わります。
この記事を読むと、切れ字「や」の意味、役割、使い方、効果などが分かります。
初心者向けの丁寧な解説ですので、あなたも今日から俳句の中に使うことができます。
切れ字「や」の意味
俳句では切れ字の「や」を使うことがあります
次の芭蕉の句では、「古池や」のところで切れ字の「や」が使われています
古池や 蛙飛びこむ 水の音
(ふるいけや かわずとびこむ みずのおと)
「や」の意味は、自身の深い感慨や感動を表すものですので
文字で意味だけを書くと「…だなあ」「…よ」「ああ、…よ」となります
ただ、実際には、そのような意味で簡単に説明できるものではありません
というのは、切れ字の「や」は、言葉では言い表せない作者の感動が含まれているからです
ですから、上記の句でいえば
静寂な景色の中で、蛙の飛び込んだ音が響いた、その瞬間の作者の大きな感動があるので
作者が感動した景色に、読者自身も入り込んで、作者の心の動きなどを想像することが大切といえます
以上のことを踏まえて、切れ字の「や」を使った他の俳句も見てみましょう
より幅広い「や」の使い方を理解できると思います
切れ字「や」を使った俳句
切れ字の「や」を使った他の俳句を紹介します
| 閑さや 岩にしみ入る 蝉の声 松尾芭蕉 (しずけさや いわにしみいる せみのこえ) | 松尾芭蕉の句集 (Amazon) >> |
| 荒海や 佐渡によこたふ 天河 松尾芭蕉 (あらうみや さどによこたう あまのがわ) | 松尾芭蕉の句集 (Amazon) >> |
| 金剛の 露ひとつぶや 石の上 川端茅舎 (こんごうの つゆひとつぶや いしのうえ) | 川端茅舎の句集 (Amazon) >> |
どうでしょうか、作者の心の動きを感じることはできたでしょうか
では次に、実際に切れ字の「や」を使う場合には、どこに置けば良いのかを説明します
切れ字「や」を置く場所
切れ字の「や」を置く場所は、「上五の最後」か「中七の最後」が良いと言われます
〇〇〇〇や/〇〇〇〇〇〇〇/〇〇〇〇〇
〇〇〇〇〇/〇〇〇〇〇〇や/〇〇〇〇〇
この場所ですね
上で紹介した俳句も、どちらかの形をとっています
逆に、置かない方がよい場所は、「下五の最後」です
〇〇〇〇〇/〇〇〇〇〇〇〇/〇〇〇〇や
「下五の最後」に切れ字の「や」を置いた俳句はあまり見かけません
作りなれてくると、ここに「や」が置きにくいことは分かるようになります
はじめのうちは、その感覚が分からないと思いますので、とりあえず「下五の最後」に置かないように注意をすればよいと思います
切れ字「や」の効果
切れ字を置くことの効果を説明します
「切れ字」は名前の通り、そこで一句を切る効果があります
文章でいえば「。」が入るイメージです
これによって、強制的に余白が生まれ、一句に余韻が生まれます
最初に紹介した芭蕉の俳句を見ましょう
古池や 蛙飛びこむ 水の音 松尾芭蕉
この俳句では、「古池や」で一度俳句が切れます
古池や / 蛙飛びこむ 水の音
切れることで、そこに余白が生まれます
余白があることで、静寂な池のある景色をゆっくりと頭に思い浮かべることができます
それが、一句全体の余韻につながります
仮に、この部分を切らずに続けて読むと、余韻は生まれません
実際に見てみましょう
古池に 蛙飛びこむ 水の音
「古池に蛙が飛びこんだ」というように、一続きの俳句にしてみました
多くの人は、この俳句からは余韻は感じられないのではないでしょうか
たった一文字の違いなのですが、感じ方に大きな違いがあります
切れ字の「や」の効果を感じていただけたのではないでしょうか
切れ字「や」の接続
切れ字の「や」は、様々な言葉につけて使うことができます
| 古池や | 名詞+「や」 |
| 荒海や | 名詞+「や」 |
| 咲くや | 動詞+「や」 |
| 零れるや | 動詞+「や」 |
| 美しや | 形容詞+「や」 |
このように、様々な言葉で使うことができるので、簡単に使うことができるとも言えます
難しく考えずに、積極的に使ってみて、その中で使い方に慣れてゆくことが、切れ字の「や」に慣れる近道といえます
名詞・動詞・形容詞に「や」の付いた俳句を紹介します。参考にしてください。
名詞+「や」
| あかつきや 歩く音して 籠の虫 岸本尚毅 (あかつきや あるくおとして かごのむし) | 岸本尚毅の句集 (Amazon) >> |
動詞+「や」
| えご散るや 沓かんばしき ソクラテス 安西篤 (えごちるや くつかんばしき そくらてす) | 安西篤の句集 (Amazon) >> |
形容詞+「や」
| いとほしや 人にあらねど 小紫 森澄雄 (いとおしや ひとにあらねど こむらさき) | 森澄雄の句集 (Amazon) >> |
切れ字「や」に似た「よ」:その使い分け
切れ字の「や」に似た助詞に「よ」があります。使い分けの方法が分からない、という声をよく聞きますので、簡単に解説します。
「や」と「よ」は、どちらも「詠嘆(~だなぁ、~であることよ)と呼びかけ(~よ)」の二つの意味を持ちます。
しかし、使われ方には傾向があります。
「や」 は、比較的詠嘆の意味で使われることが多いです。
「よ」 は、呼びかけの意味で使われることが多いです。
俳句を作るときは、「や」は詠嘆、「よ」は呼びかけ、として作ればよいでしょう。
「や」と「よ」を使った俳句の比較!
「や」は詠嘆が多い。
「よ」は呼びかけが多い。
この傾向を踏まえつつ、「や」と「よ」がどのように使われているか、実際の俳句を通して見ていきましょう。
詠嘆の「や」
| 閑さや岩にしみ入る蝉の声 松尾芭蕉 (静かだなぁ) | 松尾芭蕉の句集 (Amazon) >> |
| あたたかやしきりにひかる蜂の翅 久保田万太郎 (暖かだなぁ) | 久保田万太郎の句集 (Amazon) >> |
呼びかけの「や」
| これからのわが十年や更衣 長峰竹芳 (わが十年よ) | 長峰竹芳の句集 (Amazon) >> |
| この国や鬱のかたちの耳飾り 曾根毅 (この国よ) | 曾根毅の句集 (Amazon) >> |
詠嘆と呼びかけの両方を含む「や」の例
| いつのまにわく孑孑や戦争や 加藤知子 | 加藤知子の句集 (Amazon) >> |
※「孑孑(ぼうふら)だなぁ」という詠嘆と、「戦争よ」という呼びかけの両方の意味で「や」が使われています。
詠嘆の「よ」
| いつか死ぬ人を愛する涼しさよ 茅根知子 (涼しいことだなぁ) | 茅根知子の句集 (Amazon) >> |
| うすものを着て雲の行くたのしさよ 細見綾子 (楽しいことだなぁ) | 細見綾子の句集 (Amazon) >> |
呼びかけの「よ」
| あぢさゐのほとんど白となり海よ 宮本佳世乃 (海よ) | 宮本佳世乃の句集 (Amazon) >> |
| きさらぎの雪の羽毛を被て(きて)妻よ 成田千空 (妻よ) | 成田千空の句集 (Amazon) >> |
「や」「よ」の区別の仕方
俳句を鑑賞するとき、「や」や「よ」が詠嘆なのか呼びかけなのか迷った場合は、それぞれの持つ「よく使われる傾向」と、意味が通じるかどうかの違和感で判断できます。
「や」の場合
「や」は多くの場合、詠嘆で使われます。 しかし、「~だなぁ」と訳してみて違和感がある場合は、「呼びかけかな?」と考えてみましょう。
例句:
- いもうとや墓標の蒲公英黄をつくす
- 「いもうとだなぁ」と訳すと不自然に感じます。この場合は「いもうとよ」という呼びかけだと分かります。
- この国や鬱のかたちの耳飾り
- 「この国だなぁ」と訳すと違和感があります。これも「この国よ」という呼びかけとして解釈できます。
「よ」の場合
「よ」は多くの場合、呼びかけで使われます。 しかし、「~よ」と呼びかけで訳してみて違和感がある場合は、「詠嘆かな?」と考えてみましょう。
例句:
- いつか死ぬ人を愛する涼しさよ
- 「涼しさよ」と呼びかけることは通常ありません。この場合は「涼しいことだなぁ」という詠嘆だと分かります。
- うすものを着て雲の行くたのしさよ
- 「たのしさよ」と呼びかけるのは不自然です。これも「楽しいことだなぁ」という詠嘆として理解できます。
その他の「切れ字」の記事
俳句には、「や」以外にも「かな」や「けり」など、様々な切れ字があります
これらの切れ字は、俳句に奥行きと深みを与えてくれる大切な要素です
それぞれの切れ字が持つ特徴を理解することで、より豊かな表現の俳句を作ることができます
「かな」や「けり」については、別の記事でも詳しく解説していますので、ぜひご覧ください
「切れ字」が深く理解できる本
切れ字が生じさせる余白の様々な洞察が書かれています
読んでいて、「なるほど」と何度も思います
また、読んだ後に、いままでに無かった視点で切れ字を使えるようになるはずです
切れ字の効果をより深く勉強したい、という人にはお勧めです
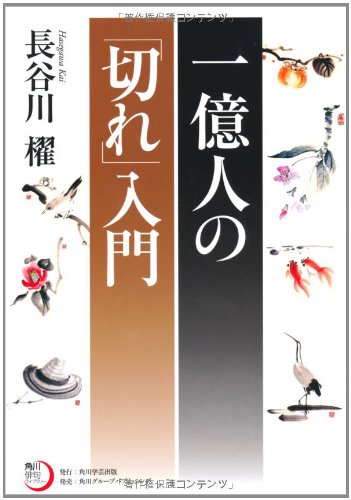





コメント