季語の中には、子季語として歳時記に掲載されているものもありますが、その意味が詳しく説明されていない場合もあります。子季語の意味を知ることで、より良い俳句を作ることができるので、今回はよく使われる主季語と子季語の意味をまとめてみました。
「霞」の季語
下の表では、一番上の「霞」が主季語、その下に並んでいるものが子季語になります。
子季語は、主季語の関連語、という考えで大丈夫です。
《 春 》
| 霞【かすみ】 | 空気中に浮かんでいるさまざまな細かい粒子のため 遠くがはっきり見えない現象。 また、霧や煙が薄い帯のように見える現象。 |
| 春霞(はるがすみ) | 春の季節に立つかすみ。 |
| 朝霞(あさがすみ) | 朝に立つ霞。 |
| 夕霞(ゆうがすみ) | 夕暮れに立つ霞。 |
| 遠霞(とおがすみ) | 遠くにある霞。 |
| 薄霞(うすがすみ) | 薄くかかった霞。 |
| 棚霞(たながすみ) | 霞がたなのようになっているさま。 |
| 霞む(かすむ) | かすみがかかること。 |
| 草霞む(くさかすむ) | 草原が霞(かすみ)でかすんで見えること。 |
| 霞の海(かすみのうみ) | 霞のかかっている海。または霞を海にみなしていう語。 |
霞(かすみ)と霞む(かすむ)について
「霞(かすみ)」と「霞む(かすむ)」は、前者が名詞で霞そのものを指し、後者が動詞で霞む様子を表します。俳句では、霞そのものを詠みたい場合は名詞の「霞」、霞がかかる様子を詠みたい場合は動詞の「霞む」を使い分けます。
名詞は送り仮名がないので「霞」、動詞は送り仮名をつけて「霞む」と書く点がポイントです。
また「霞がかかる様子」を、そのまま「霞みがかる」といったのでは、説明的ですし、余計な音数を使ってしまうため、「霞み」の一言で表現することがあります。
俳句を詠む上でのちょっとしたテクニックです、季語を選ぶ際の参考にしてみてください。
春霞について
歳時記には「春霞」という季語が掲載されていますが、霞自体が春の季語であるため、厳密に言えば「春霞」と「春」を付ける必要はありません。
「春霞」という季語が生まれた背景には、昔は霞が春の季語として定着していなかったことが挙げられます。そのため、「春の霞」という意味で「春霞」という表現が使われていました。
その後、霞が季語として認められるようになり、多くの作品で「霞」の言葉が使われるようになりました。しかし、過去の作品には「春霞」が使われていたため、慣習的に季語として残っているのです。
「霞」関連の俳句
「霞」を使った俳句にはこのようなものがあります。俳句作りの参考になさってください。
「霞」の例句
| 下駄箱の中が霞に満ちている 福本弘明 | 福本弘明の句集(Amazon) >> |
| 二階より下りきて霞む方へゆく 西野理郎 | - |
「春霞」の例句
| かごめかごめあの子も消える春霞 波多野寿子 | - |
| カササギに出逢うふるさと春霞 鳥越やすえ | - |
| 春霞だんだん松が松になり 中山洋子 | - |
「朝霞」の例句
| 浮御堂あるべき方も朝霞 鷹羽狩行 | 鷹羽狩行の句集(Amazon) >> |
| 煙突は古き世のもの朝霞 福場朋子 | - |
「夕霞」の例句
| 一本の杖の行手に夕霞 桂信子 | 桂信子の句集(Amazon) >> |
| 鳥貌や遠方(をちかた)ふかき夕霞 中村苑子 | 中村苑子の句集(Amazon) >> |
「遠霞」の例句
| 軍隊は膝に悪かろ遠霞 松本勇二 | 松本勇二の句集(Amazon) >> |
| 頬杖やお伽の山の遠霞 桂信子 | 桂信子の句集(Amazon) >> |
| 風景の過去に分け入る遠霞 野木桃花 | 野木桃花の句集(Amazon) >> |
「薄霞」の例句
| 金縷梅や下界の町の薄霞 阿部悦子 | - |
| 杉の秀の法の御山の薄霞 池田倶子 | - |
「棚霞」の例句
| 眼を凝らす北方領土棚霞 相沢有里子 | - |
| 棚霞子ら吸いこまる始業ベル 西田敏之 | 西田敏之の句集(Amazon) >> |
「霞む」の例句
| 人の死も今は遠くに海霞む 桂信子 | 桂信子の句集(Amazon) >> |
| 大廻して出航の汽笛は霞む 小出奈緒美 | - |
「草霞む」の例句
| べに鶴の脚組みかへて草霞む 豊田都峰 | 豊田都峰の句集(Amazon) >> |
「霞の海」の例句
季語探しの強い味方『四季を語る季語』
季語を選ぶ際には、様々な要素を考慮する必要がありますが、従来の歳時記には子季語の意味が詳しく記載されていないため、適切な季語を選ぶのが難しいという課題がありました。
『四季を語る季語』は、全ての子季語の意味を網羅することで、この課題を解決し、よりスムーズな季語選択を可能にします。
↓↓下の本がそうです。
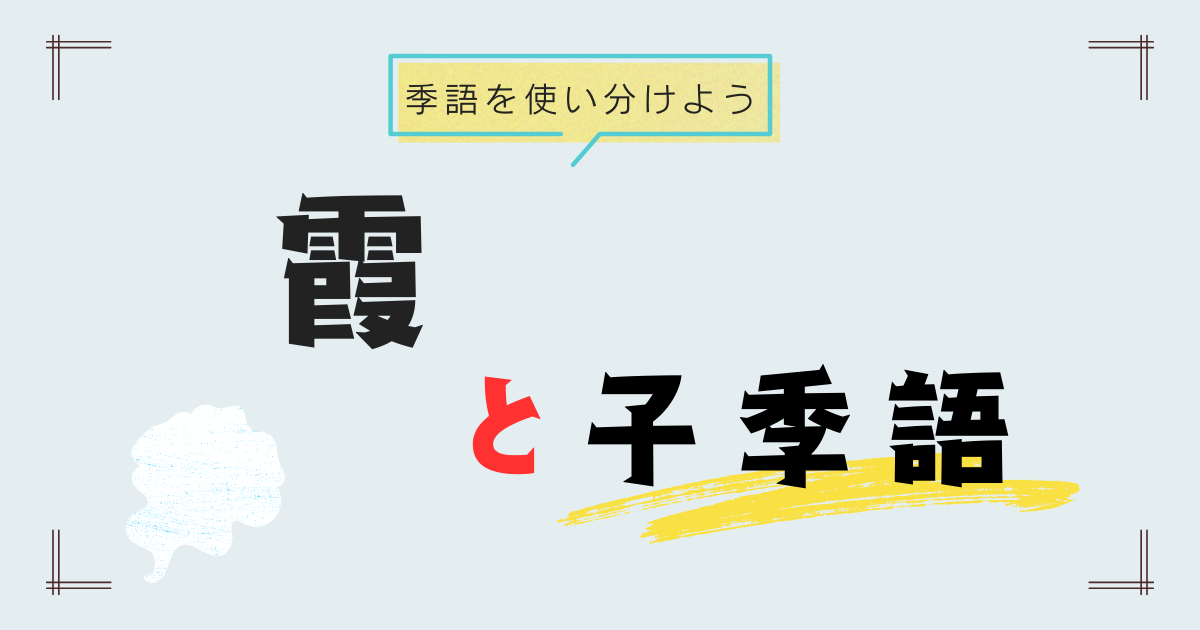


コメント