季語の中には、歳時記には掲載されているものの、意味が不明確な子季語も多く存在します。この記事では、より良い季語が選べるように、今回はよく使われる主季語と子季語のそれぞれの意味を解説しています。
「簗」の季語
下の表では、一番上の「簗」が主季語、その下に並んでいるものが子季語になります。
子季語は、主季語の関連語、という考えで大丈夫です。
《 夏 》
| 簗【やな】 | 川の瀬などで魚をとる仕掛けの一つ。 木・竹を並べて水を一か所に流すようにし、そこに来る魚を、斜めに張った簀(す)などに受けて捕らえる。 |
| 魚簗(やな) | 川瀬で魚を獲るための仕掛け。 |
| 簗さす(やなさす) | 簗をかけること。 |
| 簗打つ(やなうつ) | 簗をかけること。 |
| 簗かく(やなかく) | 簗をかけること。「掛く」は「掛ける」の古語。 |
| 簗瀬(やなせ) | 梁をしかけてある瀬。 |
「簗かく」について
「簗かく」という言葉を初めて歳時記で見かけた時、「かく」とは一体何だろう?と疑問に思う方もいるかもしれません。
「簗かく」の「かく」は、「掛ける」の古い言葉である「掛く」が変化した形です。つまり、「簗」という仕掛けを川に設置することを意味します。「簗」とは、川に木や竹を並べて水をせき止め、魚を捕らえるための仕掛けのことです。
俳句は古くからの伝統を持つ文学であるため、古語が使われることが多く、「簗かく」のように表現されることがあります。歳時記によっては、子季語の意味が詳しく解説されていない場合もあり、「簗かく」が「簗」の別名だと誤解してしまうことがあるかもしれません。しかし、「簗かく」は、実際に「簗」を設置する動作を表している言葉です。
現代語で俳句を作る人は、「簗かける(掛ける)」を使います。
「簗」関連の俳句
「簗」を使った俳句にはこのようなものがあります。俳句作りの参考になさってください。
「簗」の例句
| 新しき簗の打たれて鳴る山河 金箱戈止夫 | 金箱戈止夫の句集(Amazon) >> |
| 最上川秋風簗(やな)に吹きつどふ 水原秋櫻子 | 水原秋櫻子の句集(Amazon) >> |
| 二の簗にいぢけてをりぬ落鰻 和田照海 | - |
「魚簗」の例句
| 白魚簗川口さほど遠からず 高浜年尾 | 高浜年尾の句集(Amazon) >> |
| 魚簗かけて峯おのおのに雲の相 古舘曹人 | 古舘曹人の句集(Amazon) >> |
| 魚簗の向うを村人素っ気なく通る 飯田龍太 | 飯田龍太の句集(Amazon) >> |
「簗さす」の例句
「簗打つ」の例句
| 簗打つにいくそたび来る日照雨かな 椙山正彦 | - |
| 崩れ簗打つ大粒の山の雨 海老澤映草 | - |
「簗かく」の例句
「簗瀬」の例句
| 夕日照雨簗瀬にそうて蟲の鳴く 飯田蛇笏 | 飯田蛇笏の句集(Amazon) >> |
| 霧すさぶ月の簗瀬となりにけり 西島麦南 | 西島麦南の句集(Amazon) >> |
季語探しの強い味方『四季を語る季語』
季語を選ぶ際には、様々な要素を考慮する必要がありますが、従来の歳時記には子季語の意味が詳しく記載されていないため、適切な季語を選ぶのが難しいという課題がありました。
『四季を語る季語』は、全ての子季語の意味を網羅することで、この課題を解決し、よりスムーズな季語選択を可能にします。
↓↓下の本がそうです。
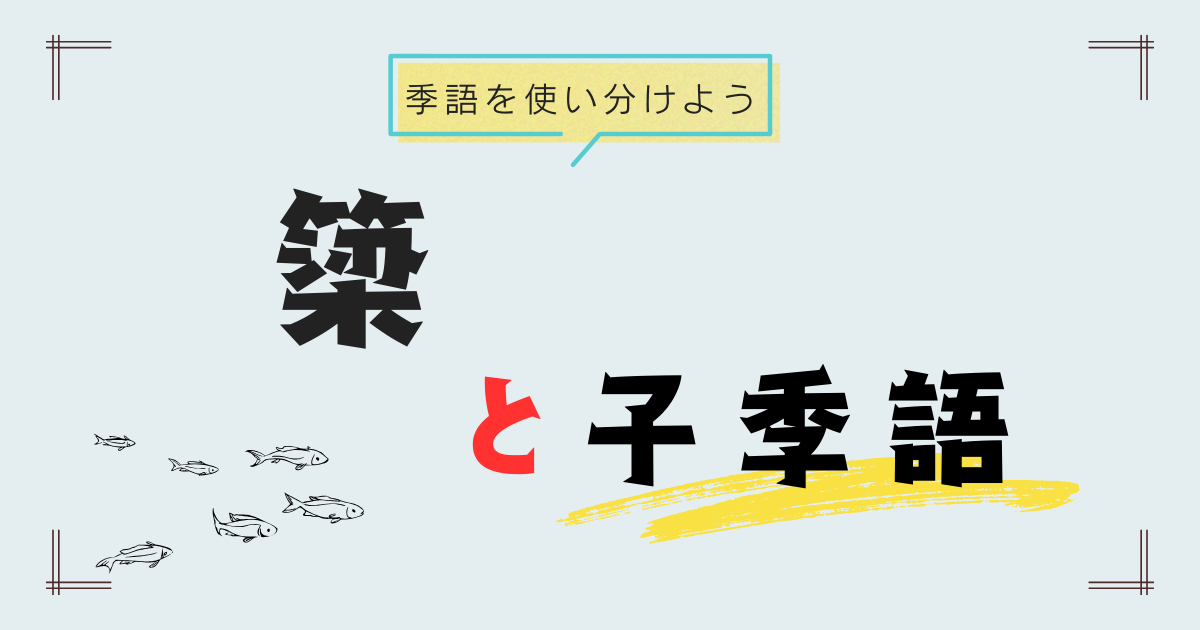


コメント