「あたたかい」という言葉には、「暖かい」と「温かい」という二つの漢字があります。どちらも同じように使えそうに思えますが、実はそれぞれに異なる意味があり、使い分けることで句の情景がより豊かになります。
この記事では、「暖かい」と「温かい」の基本的な違いから、俳句で使う際の文語表現までを分かりやすく解説します。
「暖かい・温かい」の使い分け
「暖かい」と「温かい」は、それぞれ異なるニュアンスで使われます。
暖かい
この漢字は、気温や空間全体の温度を表す際に使われます。
使用例:
- 暖かい春の日
- 暖かい部屋
- 暖かい気候
温かい
この漢字は、食べ物や飲み物、人の心など、個別の物体や感覚が持つ熱や優しさを表す際に使われます。
使用例:
- 温かい家庭
- 温かいスープ
- 温かい手
- 温かい人柄
季語に見る「暖」と「温」の使い分け
この違いは、季語を見るとわかります。「暖」と「温」のそれぞれの漢字が持つニュアンスを理解することで、季語の情景をより深く感じることができます。
「暖」のつく季語
「暖」を含む季語は、気候や空間全体の温かさを表すものが多いです。
| 季語 | 季節 | 意味合い |
| 春暖(しゅんだん) | 春 | 春全体の暖かさ |
| 暖雨(だんう) | 春 | 暖かな春の雨 |
| 春暖炉(はるだんろ) | 春 | 春になってもまだ残っている暖炉の温かさ |
| 冬暖か(ふゆあたたか) | 冬 | 寒い冬の中で、比較的暖かな日 |
| 暖房車(だんぼうしゃ) | 冬 | 暖房の効いた電車や車 |
| 床暖房(ゆかだんぼう) | 冬 | 床下に作った暖房設備 |
| 暖炉会(だんろかい) | 冬 | 暖炉を囲んでの集まり |
「温」のつく季語
「温」を含む季語は、個別のものや特定の場所が持つ温かさを表すものが多いです。
| 季語 | 季節 | 意味合い |
| 水温む(みずぬるむ) | 春 | 寒い冬が終わり、水が温かくなる様子 |
| 温む水(ぬるむみず) | 春 | 温かくなった水 |
| 温む沼・池・川 | 春 | 沼や池、川の水が温かくなる様子 |
| 温風(おんぷう) | 夏 | 梅雨明けに吹く温かい風 |
| 温麦(ぬるむぎ) | 秋 | ぬるくして食べる素麺 |
| 温め酒(ぬるめざけ) | 冬 | 温めたお酒 |
| 冬温し(ふゆあたたかし) | 冬 | 寒い冬の中で、ほっとするような温かさ |
| 温床(おんしょう) | 冬 | 苗を育てるための温かい場所 |
季語は季節を表す言葉で、『歳時記』という本に四季の季語がまとめられています。季語をもっと知りたい方は、ぜひ購入を検討してみてください。
Amazonで歳時記を見る >>
「暖かい・温かい」の文語
口語の「暖かい」「温かい」は、文語では「暖かし」「温かし」として使われます。
文語「暖かし・温かし」の活用
暖かし・温かし
形容詞ク活用
| 未然形 | 連用形 | 終止形 | 連体形 | 已然形 | 命令形 |
| (-く) -から | -く -かり | -し | -き -かる | -けれ | -かれ |
文語「暖かし・温かし」の俳句
例句を通じて、「暖かし・温かし」がどのような場面で使われているか見てみましょう。
「暖かし」の例句
| 死後通る道見えてゐて暖かし 岡地蝶児 | |
| 登校の子らのスキップ暖かし 堀地恒代 |
これらの句では、空間や季節全体の暖かさを表現することで、その場の空気感や作者の心持ちを伝えています。
「温かし」の例句
| 掌に受くる早苗饗の餅温かし 庄司栄子 |
この句では、手に持ったお餅が持つ温かさを表現しています。触れたときの温度感が、読み手にも伝わってきますね。
「暖か・温か」にまつわる多様な表現
「暖か・温か」に関連する言葉は、他にもたくさんあります。
「暖」と「温」を使った言葉
| 読み方 | 意味 |
| あたたけし(暖けし・温けし) | 暖かいこと。 |
| あたたか(暖か・温か) | 暖かい様子。 |
| あたたむ(暖む・温む) | 熱を加えて暖かくすること。 |
| あたたまる(暖まる・温まる) | 暖かくなること。 |
| あたたまり(暖まり・温まり) | 暖かくなること。 |
| あたたかさ(暖かさ・温かさ) | 暖かいこと。 |
これらの言葉を使いこなすことで、句にさらなる深みと色彩を与えることができます。例えば、「日が暖か」と「日が暖けし」では、わずかに響きが異なり、読み手の心に異なる印象を与えます。
「あたたかい」という一言にも、使う漢字や言葉の選び方で、句の世界観は大きく変わります。
ぜひ、これらの言葉を活かして、あなたの俳句をより豊かなものにしてください。
関連記事
この記事で言葉の違いを学んだように、俳句には他にも似て非なる言葉が数多くあります。
あなたの句をさらに磨き上げるために、他の言葉の使い分けをぜひチェックしてみてください。
- 俳句における「ある・おる・いる」の使い分け
- 俳句における「とき」「時」の使い分けから、「時間」の言葉まで
- 俳句における「上る・上がる・上げる」の使い分け
- 俳句における「出る・出来る」の使い方
- 俳句における「初」「始」の使い分け
- 俳句における「去ぬ」「去る」について
- 俳句における「合う・会う・逢う・遭う」の使い分け
- 俳句における「変わる・変える」の使い分け
- 俳句における「川・河・江」の使い分け
- 俳句における「影・陰・蔭・翳」の使い分け
- 俳句における「日・陽」の使い分け
- 俳句における「暖かい・温かい」の使い分け
- 俳句における「氷る・凍る」の使い分け
- 俳句における「答える・応える」の使い分け
- 俳句における「聞く・聴く・訊く」の使い分け
- 俳句にみる「咲かぬ」「咲きぬ」の違い
- 俳句にみる「来ぬ(こぬ)」と「来ぬ(きぬ)」の違い
お勧めの本
俳句の奥深さは、言葉のわずかな違いが表現を大きく変える点にありますよね。
そんな言葉の探求を助けてくれる本が、『同じ読みで意味の違う言葉の辞典』です。
一冊手元にあるだけで、より豊かな俳句創りができるはずです。
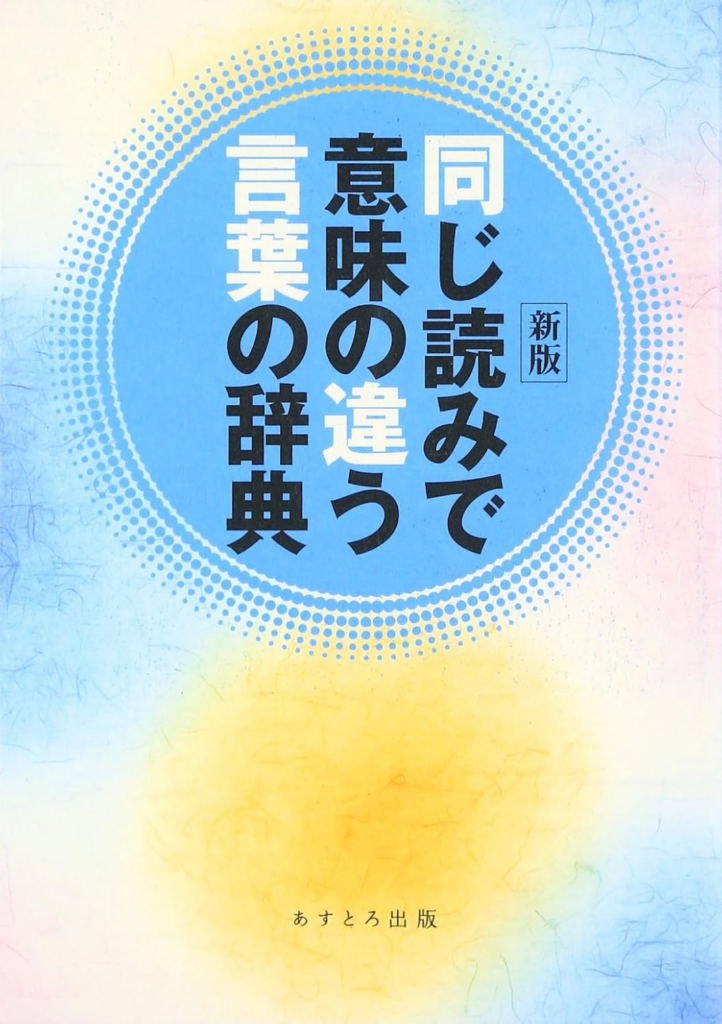

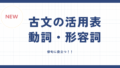

コメント