俳句では、現代の言葉(口語)ではなく昔の言葉(文語)を使うのが一般的です。しかし、「出る」や「出来る」といった日常でよく使う言葉を文語に直そうとすると、どの言葉を選べば良いか迷ってしまうことがあります。
この記事では、俳句で間違いやすい「出る」「出来る」という言葉について、それぞれの文語表現や意味の違い、そして誤用例をわかりやすく解説します。
読み・意味
「出る」と「出づ」「出」
まずは、「出る(でる)」という言葉の文語表現から見ていきましょう。
「ある場所から外へ移る」という意味を持つ「出る」は、口語です。これを文語で表現する場合は、「出づ(いづ)」または「出(づ)」を用います。
| 意味 | 口語 | 文語 |
| ある場所から外へ移る 現れる | 出る(でる) | 出づ(いづ)、出(づ) |
これらの言葉はすべて同じ意味を持ちますが、俳句では「出づ(いづ)」を使うのが一般的です。
【例句】
| げんげ田がいやで紫雲英は畦に出づ 小宅容義 | 小宅容義の句集 (Amazon) >> |
「出来る」と「出で来」「出来」
次に、「出来る(できる)」という言葉についてです。
「新しく物事が生じる」という意味を持つ「出来る」は口語です。これを文語に直すと、「出で来(いでく)」や「出来(でく)」となります。
| 意味 | 口語 | 文語 |
| 新しく物事が生じる 現れる | 出来る(できる) | 出で来(いでく)、出来(でく) |
【例句】
| 大泣きの子の出で来たる春の家 市川葉 | 市川葉の句集 (Amazon) >> |
| 巻き戻し出来ぬ年月半夏雨 堺玲子 | 堺玲子の句集(Amazon) >> |
| 等分のキャベツに今日と明日が出来 いのうえかつこ | いのうえかつこの句集 (Amazon) >> |
俳句作品は、『歳時記』という本に多く掲載されています。作品を学びたい方は、ぜひ購入を検討してみてください。
Amazonで歳時記を見る >>
文語と口語の活用を知る
言葉の活用を知ることは、俳句で正しく言葉を使うために非常に重要です。文語と口語では活用形が異なるため、注意が必要です。
「出づ・出・出る」の活用
「出づ・出・出る」の活用形を見ていきましょう。
| 言葉 | 文語・口語 | 活用 | 活用 |
| 出づ(いづ) | 文語 | ダ行下二段 | (で・で・づ・づる・づれ・でよ) |
| 出(づ) | 文語 | ダ行下二段 | (で・で・づ・づる・づれ・でよ) |
| 出る(でる) | 口語 | ダ行下一段 | (で・で・でる・でる・でれ・でろ(でよ)) |
文語と口語で活用形が異なります。
俳句作品を文語で作っている人は、確認をしておきましょう。
「出で来・出来・出来る」の活用
「出で来・出来・出来る」の活用形を見ていきましょう。
| 言葉 | 文語・口語 | 活用 | 活用 |
| 出で来(いでく) | 文語 | カ行変格 | (こ・き・く・くる・くれ・こ) |
| 出来(でく) | 文語 | カ行変格 | (こ・き・く・くる・くれ・こ) |
| 出来る(できる) | 口語 | カ行上一段 | (き・き・きる・きる・きれ・きろ(きよ)) |
こちらも、文語と口語で活用形が異なるので、確認をしておきましょう。
言葉の成り立ちを知る
それぞれの言葉がどのように変化してきたかを知ることで、より深く言葉を理解し、自信を持って俳句に使うことができます。
「出る」の成り立ち
| 言葉 | 成り立ち |
| 出づ(いづ) | この言葉が、現代の「出る」の元になっています。 |
| 出(づ) | 出づ(いづ)の語頭の母音「い」が脱落した形です。 |
| 出る(でる) | 出(づ)が下一段活用化した形です。 |
このように、「出づ(いづ)」→「出(づ)」→「出る(でる)」という順に言葉が変化してきたことがわかります。
「出来る」の成り立ち
| 言葉 | 成り立ち |
| 出で来(いでく) | 「出づ(いづ)」の連用形「出で(いで)」に「来(く)」が付いてできた言葉です。 |
| 出来(でく) | 「出で来(いでく)」が短縮した形です。 |
| 出来る(できる) | 「出で来(いでく)」の連体形「出来(でくる)」が、上一段化した形です。 |
「出来る」もまた、もとは「出づ(いづ)」に由来していることが分かりますね。
俳句でよく使われる「出づ(いづ)」の使い方
ここまで見てきたように、「出づ(いづ)」がすべての言葉の「おおもと」であるため、俳句では特に多く使われています。
以下に、よく使われる「出づ(いづ)」のいろいろな使い方と、その意味をまとめました。
「出でぬ」
構造
「出で」(「出づ」の未然形)+「ぬ」(助動詞の「ず」の連体形)
意味
出ない
例句
| 早蕨や若狭を出でぬ仏たち 上田五千石 | 上田五千石の句集 (Amazon) >> |
「出でて」
構造
「出で」(「出づ」の連用形)+「て」(助動詞の「つ」の連用形)
意味
出てしまう
例句
| 照り出でて満都を覆ふ飛花の宙 水木夏子 | 水木夏子の句集 (Amazon) >> |
「出で」
構造
「出で」(「出づ」の連用形)
意味
出る
例句
| まつすぐの道に出でけり秋の暮 高野素十 | 高野素十の句集 (Amazon) >> |
「出でし」
構造
「出で」(「出づ」の連用形)+「し」(助動詞の「き」の連体形)
「出で」(「出づ」の連用形)+「し」(語調を整えるための「し」)
意味
(すでに)出ている
出た
例句
| つと出でし馬に驚く躑躅かな 林愈青 | - |
「出でたる」
構造
「出で」(「出づ」の連用形)+「たる」(助動詞の「たり」の連体形)
意味
出てしまった
例句
| よく光る泥に出でたる蘆の角 後藤章 | 後藤章の句集(Amazon) >> |
「出づる」
構造
「出づる」(「出づ」の連体形)
名詞に接続して使われる
意味
出る
例句
| 日の出づる国のまほろば雪の川 深谷雄大 | 深谷雄大の句集(Amazon) >> |
「出でよ」
構造
「出でよ」(「出づ」の命令形)
意味
出てこい
例句
| 「船漕ぎ俑」しぐれ川瀨へ漕ぎ出でよ 渡邉きさ子 | 渡邉きさ子の句集(Amazon) >> |
「出来(でき)」について
「新しく物事が生じる」という意味の「出来(でく)」とは別に、名詞として使われる「出来(でき)」という言葉もあります。
これは「出で来(いでく)」の連用形「出で来(いでき)」が変化して名詞化したものです。
「出来過ぎ」「出来次第」「上出来」といった熟語の中で、名詞として使われているのがこの「出来(でき)」です。
例句
| 七夕竹畳の上に出来上る 千葉皓史 | 千葉皓史の句集 (Amazon) >> |
注意したい言葉の読み方と使い方
「出る・出来る」に関連して、特に注意が必要な言葉の読み方と誤用について解説します。
「出る」の読み方
「出る」という表記は、口語と文語で読み方が異なります。
- 口語での「出る」は「でる」と読む
- 文語での「出る」は「づる」と読む ※「出(づ)」の連体形「出る(づる)」です。
「出る」と書かれた場合、どちらで詠んでいるかは一見して判断がつきません。前後の文脈や、助詞の付き方、旧仮名の使用の有無などで、どちらかを判断することになります。
【用例】
| いつせいに土を出る音つくつくし 大盛和美 | 大盛和美の句集(Amazon) >> |
この句は、「いっせいに」を「いつせいに」と旧仮名で表記しているので、「つちをづる」と文語で読むのが一般的です。
| 春鳥のうすむらさきを哭いてでる 松澤昭 | 松澤昭の句集(Amazon) >> |
この句のように、ひらがなで「でる」と書かれていれば、口語であることがわかります。
誤用されやすい「出ず(いず)」
俳句では、文語の「出づ(いづ)」を口語表記にしたとされる「出ず(いず)」という言葉がまれに使われることがあります。
| ほろ酔の暖簾出ずれば冬の星 軽部榮子 | - |
| 連絡船より主婦等出ずオートバイ殘し 金子兜太 | 金子兜太の句集(Amazon) >> |
しかし、「出ず(いず)」は、文法的に存在しない言葉です。
このような表記を行うと、文語の「出(づ)」の未然形「出(で)」に、打ち消しの助動詞「ず」を付けた「出ず(でず)」という正しい文語と、表記が同じになってしまい、読者の混乱を招きます。
| 言葉 | 意味 | 補足 |
| 出ず(いず) | 出る | 誤用:「出づ(いづ)」を口語表記で「出ず(いず)」と書いたもの |
| 出ず(でず) | 出ない | 正しい文語:「出づ(いづ)」の未然形に「ず」が付いたもの |
上記の俳句が何故、正しい「出ず(でず)」ではなく、誤用の「出ず(いず)」だと言えたのか?ですが、理由は次の通りです。
ほろ酔の暖簾出ずれば冬の星
「暖簾を出れば」と言っているので、「出ず(いず)」を使っているのがわかります。
連絡船より主婦等出ずオートバイ殘し
こちらも、「主婦等が出る」と言っているので、「出ず(いず)」を使っているのがわかります。
「出でる(いでる)」も誤用
「出でる(いでる)」という言葉も、俳句で使われることがありますが、これも正しい文語ではありません。
おそらく、ですが
「出づ(いづ)」の連体形の「出づる(いづる)」を、口語の「出る(でる)」に似せて「出でる(いでる)」と変換してしまったか
「出づ(いづ)」の連用形の「出で(いで)」に、誤って助詞の「る」をつけてしまった(助詞の「る」は下二段活用の出づ(いづ)には付かない)のではないでしょうか
言葉の混乱を防ぎ、読者に意図が正しく伝わるよう、この言葉にも注意しましょう。
まとめ:俳句で「出る」「出来る」を正しく使うために
俳句では、現代の言葉である口語ではなく、昔の言葉である文語を使うのが一般的です。しかし、日常でよく使う「出る」「出来る」といった言葉を文語に直そうとすると、混同しやすい表現がいくつかあります。
この記事で解説したポイントをまとめました。
1. 「出る」と「出来る」の文語表現
- 「出る(でる)」:「ある場所から外へ移る。現れる。」という意味。
- 文語は「出づ(いづ)」または「出(づ)」を使います。俳句では「出づ(いづ)」が一般的です。
- 「出来る(できる)」:「新しく物事が生じる。現れる。」という意味。
- 文語は「出で来(いでく)」または「出来(でく)」を使います。
2. 紛らわしい表記と誤用
- 「出る」の読み方:同じ表記でも、口語は「でる」、文語は「づる」と読み方が異なります。文脈や使われている助詞から判断する必要があります。
- 「出ず(いず)」は誤用:「出る」という意味で使われることがありますが、文法的に正しくありません。正しくは、打ち消しの意味を持つ文語の「出ず(でず)」(出ない)であり、混同すると意味が全く逆になってしまいます。
- 「出でる(いでる)」も誤用:これも文法的に存在しない言葉です。「出づ(いづ)」の活用形である「出づる(いづる)」を口語風に変化させたものと考えられます。
これらの言葉は、すべて「出づ(いづ)」という古い言葉に由来しています。言葉の成り立ちなども理解しておくと、俳句で言葉を選ぶ際に自信を持って使うことができるでしょう。
言葉のルールを正しく守ることで、読者に意図が正確に伝わり、より洗練された俳句を作ることができます。
関連記事
この記事で言葉の違いを学んだように、俳句には他にも似て非なる言葉が数多くあります。
あなたの句をさらに磨き上げるために、他の言葉の使い分けをぜひチェックしてみてください。
- 俳句における「ある・おる・いる」の使い分け
- 俳句における「とき」「時」の使い分けから、「時間」の言葉まで
- 俳句における「上る・上がる・上げる」の使い分け
- 俳句における「出る・出来る」の使い方
- 俳句における「初」「始」の使い分け
- 俳句における「去ぬ」「去る」について
- 俳句における「合う・会う・逢う・遭う」の使い分け
- 俳句における「変わる・変える」の使い分け
- 俳句における「川・河・江」の使い分け
- 俳句における「影・陰・蔭・翳」の使い分け
- 俳句における「日・陽」の使い分け
- 俳句における「暖かい・温かい」の使い分け
- 俳句における「氷る・凍る」の使い分け
- 俳句における「答える・応える」の使い分け
- 俳句における「聞く・聴く・訊く」の使い分け
- 俳句にみる「咲かぬ」「咲きぬ」の違い
- 俳句にみる「来ぬ(こぬ)」と「来ぬ(きぬ)」の違い
間違えやすい言葉について書かれた本
俳句の奥深さは、言葉のわずかな違いが表現を大きく変える点にありますよね。
そんな言葉の探求を助けてくれる本が、『同じ読みで意味の違う言葉の辞典』です。
一冊手元にあるだけで、より豊かな俳句創りができるはずです。
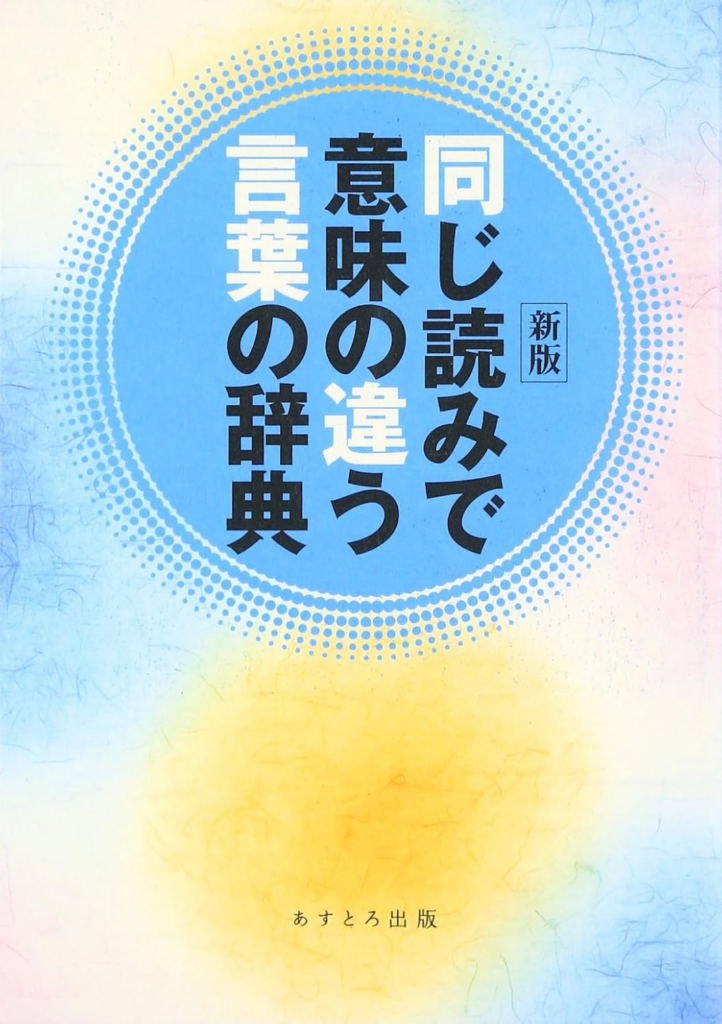


コメント