俳句では、現代の言葉(口語)をそのまま使うのではなく、昔の言葉(文語)に直して詠むのが一般的です。日常でよく使う「変わる」「変える」も例外ではありません。
しかし、これらの言葉には微妙なニュアンスの違いや、紛らわしい文語表現があります。この記事では、俳句で正しく言葉を選ぶためのポイントを解説します。
「変わる」と「変える」の違い
まず、この2つの言葉の根本的な違いを理解することが大切です。
- 「変わる」:自動詞
- 「物事の形や様子などが、自然に今までと違った状態になる」ことを表します。
- 【例】「季節が変わる」「考え方が変わる」
- 「変える」:他動詞
- 「物事を、自分の意志で以前と違った状態に変化させる」ことを表します。
- 【例】「服装を変える」「予定を変える」
このように、「変わる」は自然な変化や外的な要因による変化、「変える」は意図的な変化を表します。この違いを意識することで、俳句で伝えたいニュアンスをより明確にできます。
「変わる」
「変わる」の文語
口語の「変わる」に対応する文語は、「変はる(かはる)」です。活用は以下のようになります。
「変はる(かはる)」の活用
四段活用
| 未然形 | 連用形 | 終止形 | 連体形 | 已然形 | 命令形 |
| -ら | -り | -る | -る | -れ | -れ |
この活用形を理解することで、さまざまな表現が可能になります。
「変わる」の活用形:口語と文語の比較表
下の表を参考に、動詞「変わる」の口語と文語の活用を比べてみましょう。
| 活用形 | 口語 | 例文 | 文語 | 例文 |
| 未然形 | 変わら | 色が変わらない | 変はら | 色が変はらず |
| 連用形 | 変わり | 色が変わり | 変はり | 色が変はり |
| 終止形 | 変わる | 色が変わる | 変はる | 色が変はる |
| 連体形 | 変わる | 変わる色 | 変はる | 変はる色 |
| 已然形 | 変われ | 色が変われば | 変はれ | 色が変はれば |
| 命令形 | 変われ | 色よ変われ | 変はれ | 色よ変はれ |
「変はる」を使った俳句
| 未然形 | がちやがちやの騒いで何も変はらぬ世 髙橋健文 | |
| 連用形 | 声変はり好みも変はり更衣 近藤倫子 | |
| 終止形 | また人に生まれ変はるや枯野人 小豆澤裕子 | |
| 連体形 | 海の名の変はる辺りか風花す 中島道子 | 中島道子の句集 >> |
| 已然形 | 浜容変はれど故郷の柏餅 一峰 | 一峰の句集 >> |
| 命令形 | 来世には生まれ変はれよと蟻潰す 谷口桂子 | 谷口桂子の句集 >> |
俳句作品は、『歳時記』という本に多く掲載されています。作品を学びたい方は、ぜひ購入を検討してみてください。
Amazonで歳時記を見る >>
「変える」
「変える」の文語
口語の「変える」に対応する文語は、「変ふ(かふ)」です。活用は以下のようになります。
「変ふ(かふ)」の活用
下二段活用
| 未然形 | 連用形 | 終止形 | 連体形 | 已然形 | 命令形 |
| -へ | -へ | -ふ | -ふる | -ふれ | -へよ |
この活用形を理解することで、さまざまな表現が可能になります。
「変える」の活用形:口語と文語の比較表
口語の「変える」は「下一段活用」という活用形を持つ動詞で、文語の「変ふ」は「下二段活用」となります。
古典作品を読む際などに役立つよう、口語と文語の活用形を並べて比較できるようにしました。
| 活用形 | 口語 | 例文 | 文語 | 例文 |
| 未然形 | 変え | 色を変えない | 変へ | 色を変へず |
| 連用形 | 変え | 色を変えて | 変へ | 色を変へて |
| 終止形 | 変える | 色を変える | 変ふ | 色を変ふ |
| 連体形 | 変える | 変える色 | 変ふる | 変ふる色 |
| 已然形 | 変えれ | 色を変えれば | 変ふれ | 色を変ふれば |
| 命令形 | 変えろ | 色を変えろ | 変へよ | 色を変へよ |
「変ふ」を使った俳句
| 未然形 | あぢさゐや変へぬ信念時に邪魔 杉本正明 | 杉本正明の句集 >> |
| 連用形 | ロボットのやうに向き変へ兜虫 伊佐新吉 | |
| 終止形 | 苗代寒胎児が母の貌を変ふ 辻田克巳 | 辻田克巳の句集 >> |
| 連体形 | 秋立つや向き変ふる床の薬瓶 武象 | |
| 已然形 | 樹下の昼餉ところ変ふれど小鹿来る 藤岡紫風 | |
| 命令形 | 紫陽花の月に色変へよ衣紋竹の衣 虚空 | 虚空の句集 >> |
俳句作品は、『歳時記』という本に多く掲載されています。作品を学びたい方は、ぜひ購入を検討してみてください。
Amazonで歳時記を見る >>
「変える」の例文を文語に変換する
口語の文を文語に直す際の対応関係を知っておくと、迷わず言葉を選べます。
| 口語の表現 | 対応する文語の活用形 | 例文 |
| 色を変えない | 未然形(変へ)+ず | 色を変へず |
| 色を変えて | 連用形(変へ)+て | 色を変へて |
| 色を変える | 終止形(変ふ) | 色を変ふ |
| 変える色 | 連体形(変ふる) | 変ふる色 |
| 色を変えれば | 已然形(変ふれ)+ば | 色を変ふれば |
| 色を変えろ | 命令形(変へよ) | 色よ変へよ |
未然形の「変へ」や、連用形の「変へ」に助詞がついていますが、この未然形・連用形・終止形などに付ける助詞は、こちらで確認できます。
古文の助詞一覧 >>
関連記事
この記事で言葉の違いを学んだように、俳句には他にも似て非なる言葉が数多くあります。
あなたの句をさらに磨き上げるために、他の言葉の使い分けをぜひチェックしてみてください。
- 俳句における「ある・おる・いる」の使い分け
- 俳句における「とき」「時」の使い分けから、「時間」の言葉まで
- 俳句における「上る・上がる・上げる」の使い分け
- 俳句における「出る・出来る」の使い方
- 俳句における「初」「始」の使い分け
- 俳句における「去ぬ」「去る」について
- 俳句における「合う・会う・逢う・遭う」の使い分け
- 俳句における「変わる・変える」の使い分け
- 俳句における「川・河・江」の使い分け
- 俳句における「影・陰・蔭・翳」の使い分け
- 俳句における「日・陽」の使い分け
- 俳句における「暖かい・温かい」の使い分け
- 俳句における「氷る・凍る」の使い分け
- 俳句における「答える・応える」の使い分け
- 俳句における「聞く・聴く・訊く」の使い分け
- 俳句にみる「咲かぬ」「咲きぬ」の違い
- 俳句にみる「来ぬ(こぬ)」と「来ぬ(きぬ)」の違い
「同じ読みで違う意味のことば」を確認できる本
俳句の奥深さは、言葉のわずかな違いが表現を大きく変える点にありますよね。
そんな言葉の探求を助けてくれる本が、『同じ読みで意味の違う言葉の辞典』です。
一冊手元にあるだけで、より豊かな俳句創りができるはずです。
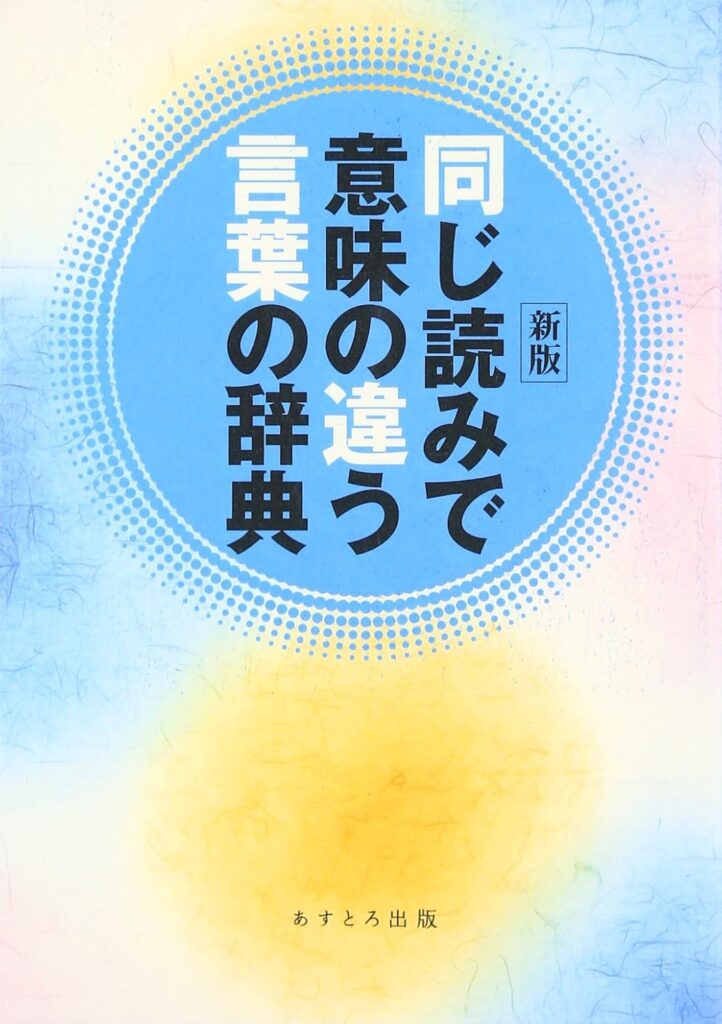


コメント