俳句で「初める・初む・始める・始む・始まる」などを使うとき、どの言葉を使えばいいか迷うことはありませんか?
俳句では、たった一文字、読み方の違いで句の印象が大きく変わることがあります。この記事では、俳句でよく使われる「はじまり」を意味する「初」「始」の言葉の使い分けを、具体的な例を交えながらわかりやすく解説します。
口語と文語の違いを知る
まず、現代語(口語)と古語(文語)の違いを理解することが、言葉の使い分けの第一歩です。俳句は文語で詠まれることが多いため、それぞれの言葉がどちらに分類されるかを知っておきましょう。
| 現代語(口語) | 古語(文語) | 意味の違い |
| 初める(そめる) | 初む(そむ) | 長く続く「状態の始まり」を表す |
| 始める(はじめる) | 始む(はじむ) | 新たな「行動の始まり」を表す |
| 始まる(はじまる) | 始まる(はじまる) | 何かが自然に「起こる」ことを表す |
たとえば、私たちが使っている「空が明け初める(そめる)」は、昔の言葉で「空が明け初む(そむ)」と表記されていて、空が明るくなるという状態が始まったことを表します。
また、「勉強を始める(はじめる)」は、昔の言葉で「勉強を始む(はじむ)」と表記され、自ら主体的に勉強を始めるという行動を表します。
このように見ると、「初」は状態に、「始」は行動に焦点を当てていると考えると、違いがわかりやすくなると言えます。
文語の「初む」「始む」の違い
文語の「初む(そむ)」と「始む(はじむ)」の違いをもう少し確認します。
ポイントは、「初む(そむ)」が「長く続くときのはじまり」、「始む(はじむ)」が「新たに事を起こす」という違いです。
たとえば、「聞き初む」と「聞き始む」では意味が大きく変わります。
- 聞き初む(ききそむ): 講義や講演など、これから長く続く話を聞き始める、といった「状態の始まり」を意味します。
- 聞き始む(ききはじむ): 自ら主体的に話を聞くという「行動の始まり」を意味します。
このように、同じ「ききはじめる」ことを言うにしも、漢字や読み方によって伝えたいニュアンスが全く異なるため、注意が必要です。
俳句での注意
俳句では、五・七・五の音数(字足らずや字余りも含む)を整えるために言葉を選びますが、この際に「初む」と「始む」を安易に入れ替えてしまうと、詠んだ人の意図と異なる意味になってしまう可能性があるので注意しましょう。
〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇 聞き初む(ききそむ)
↓音数が足りないので、「聞き始む」に変える
〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇 聞き始む(ききはじむ)
「初む」「始む」の活用
初む(そむ)
下二段活用
| 未然形 | 連用形 | 終止形 | 連体形 | 已然形 | 命令形 |
| -め | -め | -む | -める | -めれ | -めよ |
始む(はじむ)
下二段活用
| 未然形 | 連用形 | 終止形 | 連体形 | 已然形 | 命令形 |
| -め | -め | -む | -める | -めれ | -めよ |
文語の「初む」「始む」を使った俳句
「初む(そむ)」「始む(はじむ)」が、実際の俳句でどのように使われているか、見てみましょう。
「初む」を使った俳句
| オリオンの見え初む山古志寂莫たり 本多豊明 | - |
| 全山の霧氷に朝日あたり初む 吉原柳雨亭 | - |
| 蒼き指星のフーガを弾き初む 五島瑛巳 | - |
これらの句からは、星座のオリオンが見え始める様子や、霧氷に朝日が当たり始める様子、星のフーガ(音楽)を弾き始める様子など、「状態の始まり」が感じられます。
「始む」を使った俳句
| 山に雪身の内鷹の舞ひ始む 加藤瑠璃子 | 加藤瑠璃子の句集 (Amazon) >> |
| 瓜坊は闇を食むことから始む 松本勇二 | - |
| 田の神に一礼稲田刈り始む 伊藤佐和 | - |
これらの句からは、鷹が舞い始める「動き」、瓜坊が闇を食むという「行動」、稲を刈り始めるという「作業」など、「主体的な行動の始まり」が伝わってきます。
俳句作品は、『歳時記』という本に多く掲載されています。作品を学びたい方は、ぜひ購入を検討してみてください。
Amazonで歳時記を見る >>
名詞の「はじめ」について
名詞に「はじめ」という言葉があります。
漢字では「初め」と「始め」の2つの書き方があり、それぞれ意味が異なります。
| 漢字 | 意味 | 例文 |
| 初め(はじめ) | 順序の一番目 時間的に早い段階 最初 | 夏の初め 月初め 初めは順調 |
| 始め(はじめ) | 何かをはじめる ものごとの起こり 起源 | 仕事の始め 国会の始め 始めが大事 |
「初め」は、「最初」という言葉に置き換えることができます。「始め」は、「開始」という言葉に置き換えることができます。
どちらを使えばいいか迷ったときは、この2つの言葉を当てはめて考えるとわかりやすいでしょう。
名詞の「始め」「初め」を使った俳句
名詞の「始め(はじめ)」「初め(はじめ)」を使った俳句を紹介します。
「始め(はじめ)」の俳句
| もてなしの始めを舞うて御慶かな 赤尾恵以 | 赤尾恵以の句集 (Amazon) >> |
| 筆始め色紙に一字福と書き 長谷川郁子 | 長谷川郁子の句集(Amazon) >> |
| 大言海割つて字を出す稿始め 鷹羽狩行 | 鷹羽狩行の句集 (Amazon) >> |
これらの句は、もてなしの「最初」を舞う、一年の「始め」に筆を使う、原稿の「書き始め」といった使い方がされています。
「初め(はじめ)」の俳句
| 年輪の初めまんまる法師蟬 堤保徳 | - |
| 剣山にひたひたと水夏初め 河村芳子 | - |
| 仕事初めの電気ブランを注ぎくれし 佐藤晏行 | - |
これらの句は、年輪の「最初」の部分や、夏の「最初」の時期、新年「最初」の仕事といった、時間的な「最初」という使い方がされています。
俳句作品は、『歳時記』という本に多く掲載されています。作品を学びたい方は、ぜひ購入を検討してみてください。
Amazonで歳時記を見る >>
名詞と動詞の「初め・始め」に注意
名詞の「初め(はじめ)」と「始め(はじめ)」を見ました。
ちなみに、文語の動詞である「初む(そむ)」の連用形は「初め(そめ)」、「始む(はじむ)」の連用形は「始め(はじめ)」となります。
漢字が同じなので、意味を取り違えないように、注意しなければいけません。
それぞれの意味を確認してみましょう。
| 名詞 | 初め(はじめ) | 順序の一番目 |
| 名詞 | 始め(はじめ) | ものごとの起こり |
| 文語の「初む(そむ)」の連用形 | 初め(そめ) | 長く続くときの、はじまりにいう。 |
| 文語の「始む(はじむ)」の連用形 | 始め(はじめ) | 新たに事を起こす |
「初め」「始め」は表記が同じですが、意味が違います。
これでは、読者はどちらの意味で鑑賞すればよいのか分からなくなります。
そのため、俳句では「送り仮名をつけない方を名詞」「送り仮名をつける方を動詞」として、書き分けています。
これによって、正確に意味を伝えることができます。
| 名詞 | 初(はじめ) ←送り仮名をつけない |
| 名詞 | 始(はじめ) ←送り仮名をつけない |
| 動詞 | 初め(そめ) ←送り仮名をつける |
| 動詞 | 始め(はじめ) ←送り仮名をつける |
このように、名詞と動詞を送り仮名の有無で明示しないと、読者が混乱してしまいますが、実際の俳句では、送り仮名を気にせずに使っている人が多いようです。
実際の「始め」「初め」を使った俳句を見てみましょう。
「〇〇始め」「〇〇初め」の読み方
動詞の連用形に「始め」「初め」をつけると読み方が変わるので、解説します。
書き+「始め」は、書始め(かきはじめ)
書き+「初め」は、書初め(かきぞめ)
と読みます。
「書始め」と「書初め」の違いは、次の通りです。
- 「書始め(かきはじめ)」:「今から書き始めること」や「書き出し」を意味する言葉で、季語ではありません。
- 「書初め(かきぞめ)」:「新年になって初めて行う習字」を指し、新年の季語です。
漢字は同じでも読み方が異なり、意味も全く違います。俳句を作る際も鑑賞する際も、この違いをしっかり把握しておきましょう。
季語の「筆始・書初」の微妙な違い
「筆始(ふではじめ)」と「書初(かきぞめ)」は、どちらも新年の季語で、似た意味を持ちます。しかし、込められたニュアンスには微妙な違いがあります。
- 筆始(ふではじめ):「年明けに筆をとり始めること」を指し、行為の開始に重きを置いた言葉です。
- 書初(かきぞめ):「年明けの最初に字を書くこと」を指し、時間的な最初に重きを置いた言葉です。
微妙な意味の違いですが、このような違いを使い分けることで、表現したいことを正確に伝えることができます。
一般的な歳時記には、一つ一つの季語の意味までは書かれていませんが、下記の本には全ての季語に意味が書かれているので、季語を選ぶ際の参考になります。

季語の「〇〇始め・〇〇初め」の読み方
俳句の季語では、「〇〇始め(はじめ)」と「〇〇初め(ぞめ)」というように、読み方は使い分けられています。
- 歌会始(うたかいはじめ)・鞠始(まりはじめ)・講書始(こうしょはじめ)
- 笑初(わらいぞめ)・泣初(なきぞめ)・話初(はなしぞめ)
ですので、季語として「笑初」を使う際に、音数を増やしたいからといって「わらいはじめ」と読ませることはありません。
「〇〇始め」「〇〇初め」の季語
「○○始め(はじめ)」や「○○初め(ぞめ)」は、新年にまつわる季語でよく使われます。
「始」は「何かを始める行為」を意味する季語が多く、「初」は「一年で最初のもの」を意味する季語が多くあります。「始」「初」を含む季語をいくつか挙げます。
| 始 | 仕事始/細工始/手斧始/窯始/鞴始/鍛冶始/鋳始/御用始/正月事始/日記始/歌会始/鞠始/講書始/年始 |
| 初 | 初茜/初東雲/初明り/初日/初空/初晴/初霞/初風/初東風/初松籟/初凪/初景色/初富士/初筑波/初比叡/初浅間/初手水/掃初/初座敷/初屏風/初暦/初湯/初燈/初電話/笑初/泣初/話初/梳初/初髪/初鏡/初灸/初夢/書初/出初 |
季語は季節を表す言葉で、『歳時記』という本に四季の季語がまとめられています。季語をもっと知りたい方は、ぜひ購入を検討してみてください。
Amazonで歳時記を見る >>
「出始め」と「出初め」に注意
「始」と「初」を書き分けることは、異なる言葉の意味を明確にする役割も果たします。
- 出始め(ではじめ): 季節の野菜が出たばかりのことで、季語ではありません。
- 出初め(でぞめ): 新年に消防演習などの行事を催すことで、新年の季語です。
このように、漢字を正確に書くことで、言葉の本来の意味や、それが季語であるかどうかも明確になります。
俳句を作る際は、書き方や読み方を含めて正確な言葉使いを心がけましょう。
「〇〇始め・〇〇初め」を使った俳句
動詞の連用形に続く形で、「始め(はじめ)」「初め(ぞめ)」は使われます。
俳句の例を見ていきましょう。
「〇〇始め(はじめ)」の俳句
| 牡丹に崩れ始めしこの世かな 久保純夫 | 久保純夫の句集(Amazon) >> |
| 結城着て論語集解読み始め 山中正己 | 山中正己の句集(Amazon) >> |
| 前文がゆらぎ始めた稲光 稲葉明日香 | 稲葉明日香の句集(Amazon) >> |
これらの句では、「崩れ始める」「読み始める」「ゆらぎ始める」というように、連用形について使われています。
「〇〇初め(ぞめ)」の俳句
| コスモスの風を集めてお履初め 北村量子 | |
| 奔放にまたいで書きぬお書初 杉本るつ | 杉本るつの句集(Amazon) >> |
| 読初めは荻生徂徠や致道館 古川京子 | 古川京子の句集(Amazon) >> |
これらの句も「履き初め」「書き初め」「読み初め」というように、連用形について使われています。
俳句作品は、『歳時記』という本に多く掲載されています。作品を学びたい方は、ぜひ購入を検討してみてください。
Amazonで歳時記を見る >>
誤用の俳句?
いくつか、言葉の使い方に疑問を感じる句を挙げます。
| ある本の海賊版や読初 山口青邨 | 山口青邨の句集(Amazon) >> |
「読初」は、通常「よみぞめ」と読み、四音になります。
しかし、この句では五音にするために「よみはじめ」と読ませた可能性があります。
ただ、「よみはじめ」とすると季語としての意味が薄れてしまいます。
| 巡礼のひとりふり向く夢初め 大路彦堂 | - |
「初夢」という言葉はありますが「夢初め」という言葉はありません。「夢初め(ゆめはじめ)」となると、「夢の最初」という意味に解釈されてしまい、季語としては成立しません。
関連記事
この記事で言葉の違いを学んだように、俳句には他にも似て非なる言葉が数多くあります。
あなたの句をさらに磨き上げるために、他の言葉の使い分けをぜひチェックしてみてください。
- 俳句における「ある・おる・いる」の使い分け
- 俳句における「とき」「時」の使い分けから、「時間」の言葉まで
- 俳句における「上る・上がる・上げる」の使い分け
- 俳句における「出る・出来る」の使い方
- 俳句における「初」「始」の使い分け
- 俳句における「去ぬ」「去る」について
- 俳句における「合う・会う・逢う・遭う」の使い分け
- 俳句における「変わる・変える」の使い分け
- 俳句における「川・河・江」の使い分け
- 俳句における「影・陰・蔭・翳」の使い分け
- 俳句における「日・陽」の使い分け
- 俳句における「暖かい・温かい」の使い分け
- 俳句における「氷る・凍る」の使い分け
- 俳句における「答える・応える」の使い分け
- 俳句における「聞く・聴く・訊く」の使い分け
- 俳句にみる「咲かぬ」「咲きぬ」の違い
- 俳句にみる「来ぬ(こぬ)」と「来ぬ(きぬ)」の違い
「同じ読みで違う意味のことば」を確認できる本
俳句はたった17音という限られた文字数で表現するため、言葉選びが非常に重要です。漢字一文字や読み方の違いで、作品全体の意味が大きく変わってしまいます。
今回の「初」と「始」の違いのように、迷いやすい言葉はたくさんあります。正確な俳句を作るためには、言葉の意味を正しく理解し、意図した通りの表現を選ぶことが大切です。
下の本は、間違えやすい言葉を調べるときに役立ちます。例文も載っているため、間違わずに言葉を選ぶことができます。一冊持っておいてもよいと思います。
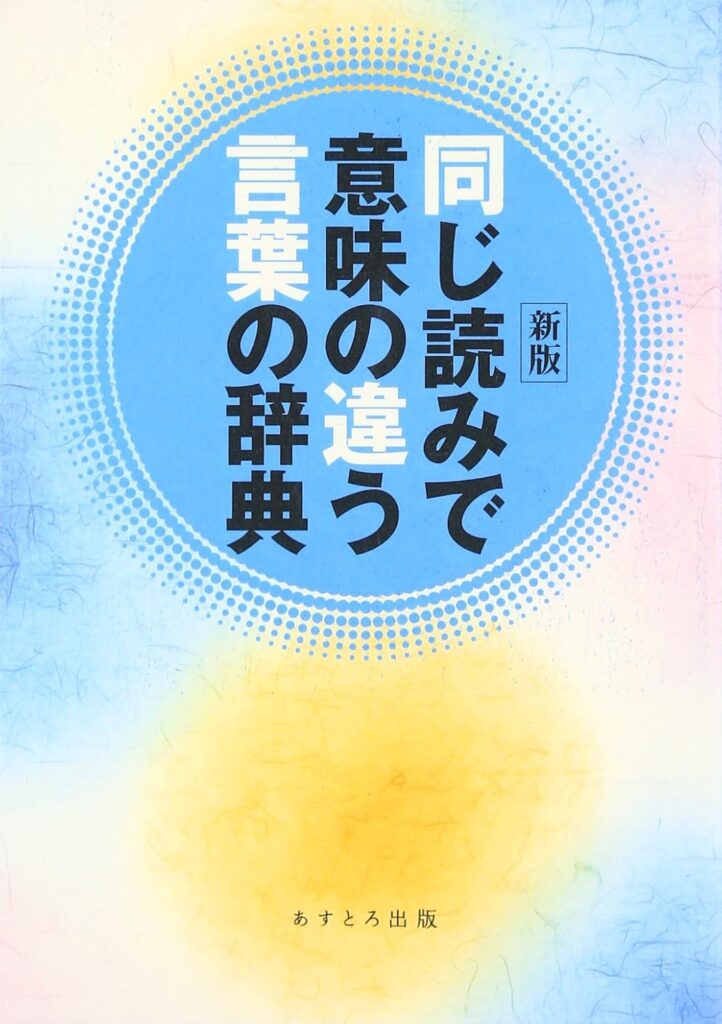


コメント