新年を詠む季語には、普段あまり使わない言葉が隠されていることがあります。
今回は、新年の季語「米こぼす」と共に歳時記に載っている「若水あぐ(わかみずあぐ)」という言葉の謎に迫ってみましょう。
「若水(わかみず)」は、元日の朝に初めて汲む水のことを指します。この若水で茶を点てたり、雑煮を煮たりする風習はよく知られています。しかし、「若水あぐ」は、その意味が少し異なります。
新年の季語の一覧 >>>
謎の季語「若水あぐ」の正体
歳時記や辞典を調べると、「若水あぐ」は「新年はじめて泣くこと」、または「初泣きを汲み上げる」と説明されることがあります。 1.2)
しかし、この説明だけでは、どうして「初泣き」が「若水」と「あぐ(上ぐ)」という言葉で表現されるのか、その意味が分かりません。
実は、この言葉には、古くからの風習が関係していると考えられています。日本では古来より、元日に「涙」と言うことを忌み嫌う風習がありました。 3)
そこで、涙を別のものに見立てる言葉が生まれたのです。
- 米こぼす(よねこぼす):涙を米に見立てた言葉
- 若水あぐ(わかみずあぐ):涙を若水に見立てた言葉
「あぐ(上ぐ)」は、「差し上げる」や「神様に捧げる」といった意味があります。つまり、「若水あぐ」は、「新年最初の涙を、若水として神様に捧げる」というような、比喩的な意味合いで使われたのかもしれません。
誤解されやすい「若水」の季語
この「若水あぐ」を使うときに気をつけたいのは、「若水」そのものを詠んでいるのか、「初泣き」を詠んでいるのか、読者に伝わるように工夫することです。
例えば、「万戸さらに新まる、若水を汲み上ぐるを、今年の事始めとなす」 4)
という表現では、一般的に「若水を汲む」という行為を指していると解釈されます。
このように、同じ言葉でも、文脈によって意味が大きく変わってしまうため、作者が何を意図しているのかを明確にすることが大切です。
季語の背景を探る旅へ
俳句を詠むことは、言葉の奥深さを探求する旅でもあります。歳時記に載っている言葉でも、その背景や由来をたどってみると、意外な発見があるかもしれません。
もし、あなたが「若水あぐ」を季語として使うなら、その言葉に秘められた「初泣き」という繊細な感情を、どう表現しますか?
季語の謎を解き明かすことは、あなたの俳句をさらに豊かなものにしてくれるはずです。
新年の季語の一覧 >>>
1) 角川書店.(2022).新版角川俳句大歳時記.KADOKAWA.
2) 高橋仁.(昭和9).俳句季語事典.立命館出版部.
3) 明治文献.(1976).図会に見る日本の百年 第13巻 (行事祝祭図会 1).
4) 菊池貴一郎,鈴木棠三.絵本江戸風俗住来.(1969).平凡社.
関連記事
- 「うそ寒(うどざむ)」の「うそ」とは
- 「夕焼ける」の使い方は正しい?
- 「梅つ五月」の意味が旧暦二月?
- 「百松明の神事」は実在する?
- 「秋の隣」が季語にならない時?
- ショウブ、アヤメ、カキツバタの違い
- 一茶の句に学ぶ「露の世」の謎
- 七十二候に隠された、もう一つの顔
- 俳句の季語「たかみそぎ」って何?
- 俳句初心者さん向け!「秋の色」について深掘り解説
- 季語「歳暮祝(せいぼいわい)」の違和感
- 季語の物語を探る!「蘆の神輿」は担ぐものじゃない?
- 季語の落とし穴?「大吉」とは
- 季語の落とし穴?「林の鐘」とは
- 季語の落とし穴?「雁の涙」とは
- 季重なり季語?「冬衾(ふゆぶすま)」とは
- 季重なり季語?「冬襖(ふゆぶすま)」とは
- 季重なり季語?「冬障子」とは
- 季重なり季語?「斑雪凍つ」とは
- 季重なり季語?「木の芽流し」は春?夏?
- 歳時記の間違い?紫陽花の別称の瓊花(けいか)とは
- 熊が冬の季語?クマ被害は夏に多いけれど・・・
- 音数から季語を探したいときは、こちら

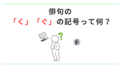

コメント