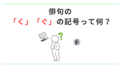「正雪蜻蛉」とは
夏の季語に、川辺を飛び交う「蜉蝣(かげろう)」があります。
この「カゲロウ」の関連季語として、歳時記によっては「正雪蜻蛉(しょうせつとんぼ)」という、少し不思議な名前が載っていることがあります。
この名前は、江戸時代前期の軍学者、由比正雪(ゆいしょうせつ)に由来します。彼は幕府への謀反を企てたものの、計画は事前に露見。駿府(現在の静岡市)で取り囲まれ、自ら命を絶ちました。
夏の季語一覧 >>>
季語に隠された「静岡の物語」
由比正雪の墓は、彼が最期を迎えた駿府に残されています。
この「正雪蜻蛉」という呼び名は、彼の墓が残る静岡県でのみ使われている、非常に地域性の高い季語のようです。
静岡の人々は、カゲロウの大群が川面を覆うように飛び交う姿を見て、由比正雪の無念の死を連想し、その霊魂がカゲロウとなって現れたものだと考えたのかもしれません。
ただ、なぜカゲロウが由比正雪の怨念に見立てられるようになったのか、その明確な理由は不明です。しかし、その謎が、この季語をよりミステリアスなものにしています。
季語を選ぶということ
もし、あなたが「正雪蜻蛉」という季語を使うのであれば、その背後にある物語を理解しておくことが大切です。
- 単なるカゲロウとして詠むなら「蜉蝣」
- 静岡の歴史や、由比正雪の悲劇に思いを馳せるなら「正雪蜻蛉」
たった一つの季語を選ぶだけで、あなたの句は全く異なる世界観を持つことができます。
季語を学ぶことは、言葉の背後にある物語を探る旅です。
少しでも気になった季語があったら、ぜひ一度調べてみてください。
そこには、思いがけない歴史や、俳句の題材になるヒントが隠されているかもしれません。
夏の季語一覧 >>>
関連記事
- 「うそ寒(うどざむ)」の「うそ」とは
- 「夕焼ける」の使い方は正しい?
- 「梅つ五月」の意味が旧暦二月?
- 「百松明の神事」は実在する?
- 「秋の隣」が季語にならない時?
- ショウブ、アヤメ、カキツバタの違い
- 一茶の句に学ぶ「露の世」の謎
- 七十二候に隠された、もう一つの顔
- 俳句の季語「たかみそぎ」って何?
- 俳句初心者さん向け!「秋の色」について深掘り解説
- 季語「歳暮祝(せいぼいわい)」の違和感
- 季語の物語を探る!「蘆の神輿」は担ぐものじゃない?
- 季語の落とし穴?「大吉」とは
- 季語の落とし穴?「林の鐘」とは
- 季語の落とし穴?「雁の涙」とは
- 季重なり季語?「冬衾(ふゆぶすま)」とは
- 季重なり季語?「冬襖(ふゆぶすま)」とは
- 季重なり季語?「冬障子」とは
- 季重なり季語?「斑雪凍つ」とは
- 季重なり季語?「木の芽流し」は春?夏?
- 歳時記の間違い?紫陽花の別称の瓊花(けいか)とは
- 熊が冬の季語?クマ被害は夏に多いけれど・・・
- 音数から季語を探したいときは、こちら