俳句を詠む上で、言葉の選び方はとても大切です。
「去ぬ」と「去る」という二つの漢字があります。似た言葉ですが、読み方や活用などが違うため、使い方をで、正確に読者に伝わる俳句を作ることが可能になります。
「去ぬ」「去る」の読み方
「去ぬ」「去る」の読み方を確認します。
- 「去ぬ」は「いぬ」
- 「去る」は「さる」
漢字は同じですが、読み方が違うので注意が必要です。
「去ぬ」「去る」の意味
「去ぬ」「去る」の意味です。
「去ぬ(いぬ)」も「去る(さる)」も、どちらも「ある場所から離れる。ある季節が過ぎ去る。あるいは、季節がやってくる。」という意味です。
ここで注意したいのが、「去ぬ(いぬ)」も「去る(さる)」も、「ある季節が過ぎ去る」という意味を持ちながら、真逆の「季節がやってくる」という意味を持っているということです。
これが、俳句の季語で、混乱を招きやすい部分にもなります。
季語における「去ぬ」と「去る」の注意点
季語の中には、「去ぬ(いぬ)」「去る(さる)」を含むものが多くあります。
ただ。同じ「去る」を使った季語でも、逆の意味になることがあります。
- 生き物が「去る」場合: 遠くへいく様子を表す季語として、「燕去る(つばめさる)」「鶴去る(つるさる)」のように使われます。
- 季節が「去る」場合: やってくる様子を表す季語として、「秋去る(あきさる)」「年去る(さる)」のように使われます。
現代語では「去る」は「遠くへ行く」という意味で使うことが多いです。そのため、「秋去る」というと「秋が終わる」という意味で使ってしまいがちですが、俳句では「秋がやってくる」という意味でつかわれます。
「去ぬ」「去る」の活用の違い
「去ぬ(いぬ)」と「去る(さる)」は、活用が違うため、使うときには注意が必要です。
「去ぬ」の活用
(ナ変活用)
| 未然形 | 連用形 | 終止形 | 連体形 | 已然形 | 命令形 |
| な | に | ぬ | ぬる | ぬれ | ね |
「去る」の活用
(四段活用)
| 未然形 | 連用形 | 終止形 | 連体形 | 已然形 | 命令形 |
| ら | り | る | る | れ | れ |
「去ぬ」「去る」を使った俳句
「去ぬ」「去る」の活用を見ましたが、言葉の使い分けは、実際の俳句の例を見るとよくわかります。
「去ぬ(いぬ)」を使った俳句
| 未然形 | 去にしてふ人去なであらば恋すてふ 漱石 | 漱石の句集(Amazon) >> |
| 連用形 | 颱風の去にし夜よりの大銀河 竹下しづの女 | しづの女の句集(Amazon) >> |
| 終止形 | ねもごろに鮎くれて去ぬ鄙(ひな)住居 黙黙庵 | - |
| 連体形 | 雑魚売りの時雨れて去ぬる畷(なわて)かな 里梅 | - |
| 已然形 | 爐邊の客去ぬればすぐに妻の愚痴 永田光尾 | - |
| 命令形 | とても霽(は)れぬ五月雨傘をさして去ね 竹下しづの女 | しづの女の句集(Amazon) >> |
「去る(さる)」を使った俳句
| 未然形 | ある街の木瓜の肉色頭を去らず 三谷昭 | 三谷昭の句集(Amazon) >> |
| 連用形 | うしろより見る春水の去りゆくを 山口誓子 | 山口誓子の句集(Amazon) >> |
| 終止形 | この良夜渦も響きをしづめ去る 佐野まもる | 佐野まもるの句集(Amazon) >> |
| 連体形 | いづこかへ去る身なれども暖し 神田ひろみ | 神田ひろみの句集(Amazon) >> |
| 已然形 | 人去れば藤のむらさき力ぬく 澁谷道 | 澁谷道の句集(Amazon) >> |
| 命令形 | 落日のなかくらくらと夏去れり 櫻井博道 | 櫻井博道の句集(Amazon) >> |
俳句作品は、『歳時記』という本に多く掲載されています。作品を学びたい方は、ぜひ購入を検討してみてください。
Amazonで歳時記を見る >>
俳句創りでの「去ぬ」「去る」の使い分け
現代俳句では「去る」が一般的ですが、「去ぬ」を使うことで、より古風で情緒的な雰囲気を出すことができます。
- 音のリズムを変えたいとき: 同じ連体形で比較すると、「去る」が1音なのに対し、「去ぬる」は2音になります。音数を調整したいときに便利です。
- 古風な趣を出したいとき: 「去ぬ」は古語ならではの響きがあり、情景に深みを与えます。
まとめ
「去ぬ」と「去る」は、使い方を知ることで俳句の表現の幅を広げてくれる言葉です。読み方や活用、そして季語としての特別な意味を理解して、ぜひご自身の句作に役立ててみてください。
関連記事
この記事で言葉の違いを学んだように、俳句には他にも似て非なる言葉が数多くあります。
あなたの句をさらに磨き上げるために、他の言葉の使い分けをぜひチェックしてみてください。
- 俳句における「ある・おる・いる」の使い分け
- 俳句における「とき」「時」の使い分けから、「時間」の言葉まで
- 俳句における「上る・上がる・上げる」の使い分け
- 俳句における「出る・出来る」の使い方
- 俳句における「初」「始」の使い分け
- 俳句における「去ぬ」「去る」について
- 俳句における「合う・会う・逢う・遭う」の使い分け
- 俳句における「変わる・変える」の使い分け
- 俳句における「川・河・江」の使い分け
- 俳句における「影・陰・蔭・翳」の使い分け
- 俳句における「日・陽」の使い分け
- 俳句における「暖かい・温かい」の使い分け
- 俳句における「氷る・凍る」の使い分け
- 俳句における「答える・応える」の使い分け
- 俳句における「聞く・聴く・訊く」の使い分け
- 俳句にみる「咲かぬ」「咲きぬ」の違い
- 俳句にみる「来ぬ(こぬ)」と「来ぬ(きぬ)」の違い
間違えやすい言葉について書かれた本
今回は、わずかな違いで意味が変わる言葉について解説しました。
ここで紹介する本は、同じ読み方なのに意味が違う漢字を、用例を交えながらわかりやすく解説しています。
一冊手元にあるだけで、俳句創りの表現力が豊かになるのを感じられるはずです。
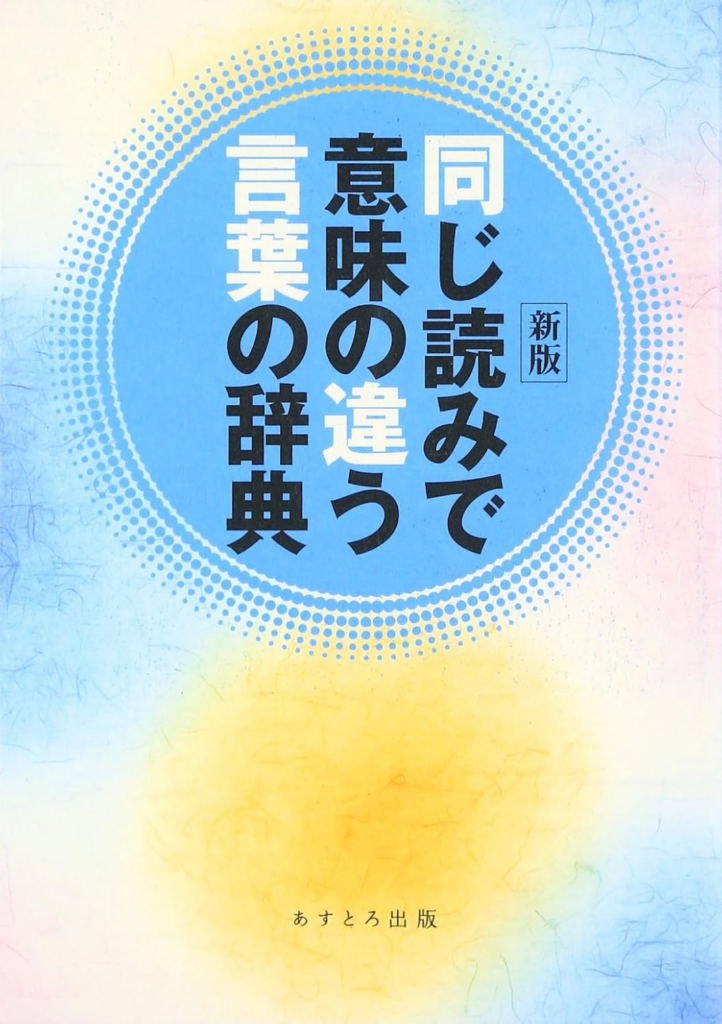


コメント