俳句において、「南風(みなみかぜ)」 は夏の季語です。
この「南風」という漢字は同じでも、地域によって様々な読み方があります。例えば、「まぜ」「まじ」「はえ」などと呼ばれ、これらの地域ごとの呼び名を使うことで、句を詠んだ場所を特定し、より情景豊かな俳句にすることができます。
また、音数合わせに困った時には、「南風(みなみかぜ)」を「みなみ」や「なんぷう」といった別の呼び方で表現することも可能です。
ここでは、「南風」に関連する季語をご紹介します。歳時記には掲載されていない読み方や子季語も紹介していますので、これからの俳句作りにぜひお役立てください。
夏の南風
南風(みなみかぜ、なんぷう、みなみ):一般的な呼び名
南から吹く夏の季節風。四月から八月ごろまで吹く海からの湿った風をいう。
南風(みなみかぜ)を、漢語で「なんぷう」と読んだり、略して「みなみ」と呼ぶことがある
俳句は5・7・5で詠まなくてはいけないので
「南風 小さな島の 影薄く」とあった場合は、「みなみかぜ」と読む
「南風や 小さな島の 影薄く」とあった場合は、「なんぷう」と読む
「南風吹く 小さな島の 影薄く」とあった場合は、「なみな」と読む
このように、鑑賞者は音数によって読み方を変える
南風(みなみかぜ、なんぷう、みなみ)の読み方を知っていなければ、鑑賞ができないので、覚えておきたい
| 南風や化粧に洩れし耳の下 日野草城 | 日野草城の句集 (Amazon) >> |
| 日々南風棕梠の葉先と髪亂る 野澤節子 | 野澤節子の句集 (Amazon) >> |
南風(まぜ、まじ):西日本の呼び名
南風(まぜ、まじ)とも読む。
南風(まぜ、まじ)は、南風(みなみかぜ)と同じ意味であるが、特に、西日本での呼び名となる。
| 南風(まぜ)吹けば海壊れると海女歎く 橋本多佳子 | 橋本多佳子の句集 (Amazon) >> |
南風(はえ、ぱいかじ):沖縄の呼び名
南風(はえ、ぱいかじ)とも読む。
南風(はえ、ぱいかじ)は、南風(みなみかぜ)と同じ意味であるが、特に、沖縄での呼び名となる。
「はえ」は、沖縄では南の方位を意味する言葉。
「ぱいかじ」の「ぱい」は沖縄で南、「かじ」は風を意味する言葉。
南(みなみ)、南吹く(みなみふく):関東以北の書き方
南(みなみ)は、南風(みなみかぜ)と同じ意味。
このように「南」の一文字だけで南寄りの風を指すのは、関東以北の太平洋岸だけ。
「南吹く」は、南風が吹いていることを言う。
| 南吹く一座みな目を八方へ 飯田龍太 | 飯田龍太の句集 (Amazon) >> |
正南風(まみなみ、まはえ):正面からの風
正南風(まみなみ、まはえ)は、南風(みなみかぜ)と同じ意味ですが、「正」という字があるように正面から吹く風の意味がある。
南東風(はえごち・みなみごち)、沖南風(おきばえ)、南西風(はえまじ):吹く方角
風の吹く方角の微妙な違いで名前が変わることがある。
南東風(はえごち・みなみごち)は、東南東からの風。「こち」は東から吹く風をいう。
沖南風(おきばえ)は、南西からの風。九州西部沿岸地方の言葉。
南西風(はえまじ)は、南西からの風。
大南風(だいなんぷう、おおみなみ):風の強さ
強い南風を(だいなんぷう、おおみなみ)という。
発達した低気圧が日本海を通過する際に、強い南風になる。
| 大南風岬端はもの思ふところ 小野恵美子 | 小野恵美子の句集 (Amazon) >> |
海南風(かいなんぷう):吹く場所
海上で吹く南風を海南風(かいなんぷう)という。
| 移り住み海南風をひとり占め 宮津昭彦 | 宮津昭彦の句集 (Amazon) >> |
黒南風(くろはえ)、荒南風(あらはえ)、白南風(しろはえ、しらはえ):梅雨のころ
梅雨時期の暗い空に吹く南風を、黒南風(くろはえ)という。
梅雨時期に吹く、大雨を伴う強い南風を、荒南風(あらはえ)という。
梅雨の晴れ間や、梅雨明け後の明るい空に吹く南風を、白南風(しろはえ、しらはえ)という。
| 病癒え来て黒南風の黒に堪ふ 三好潤子 | 三好潤子の句集 (Amazon) >> |
| 荒南風や揺るがぬ青き島一つ 野澤節子 | 野澤節子の句集 (Amazon) >> |
| 白南風や背戸を出づれば杏村 室生犀星 | 室生犀星の句集 (Amazon) >> |
五斗食い風(ごとぐいかぜ)、六俵南風(ろっぴょうばえ):海を荒らす風
海を荒す南風を、漁業の盛んな町では名前を付けている。
五斗食い風(ごとぐいかぜ)は、福岡県志賀島での呼び名。梅雨半ばの荒れ模様の天気を伴う南風のこと。海が荒れ、五斗の米を食べ終わるまで出漁できないことが名の由来。
六俵南風(ろっぴょうばえ)は、佐賀県東松浦半島での呼び名。海が荒れ、六俵の米を食べ終わるまで出漁できないことが名の由来。
秋の南風
送り南風(おくりまぜ)、後れまじ(おくれまじ)、おくりまじ
陰暦七月の盂蘭盆を過ぎて吹く南風をいう。近畿や中国地方で使われる言葉。
夏場の南風よりも弱い風となる。
| 海光に送りまぜ吹く林檎園 石原舟月 | 石原舟月の句集 (Amazon) >> |
「南風」の選択で、場所を暗示させる
南風は、単なる季節の風を指すだけでなく、それぞれの地域で多様な呼び名を持ちます。これらの呼び名は、その土地の風土や文化、人々の暮らしと深く結びついています。
例えば、西日本で使われる「まぜ」や、沖縄の「ぱいかじ」といった言葉を使うことで、作者がその地域を舞台に俳句を詠んでいることを読者に伝えることができます。
特に漁業が盛んな地域では、漁師たちが風向きや海の様子を言い表すためにこれらの言葉を使ってきました。そのため、漁に関連する句を詠む際に、これらの季語が選ばれることがよくあります。
このように、南風の様々な呼び方は、単なる地理的な情報にとどまりません。それは、その土地ならではの空気感や人々の営みを連想させ、読み手の想像力を豊かに掻き立てる力を持っているのです。
四季でみられる季語の関連記事
- 「南風」と関連季語の意味
- 「夕焼け」の季節ごとの季語
- 「天の川」の季節ごとの季語
- 「旱」の季節ごとの季語
- 「月」の季節ごとの季語
- 「朝顔」の季節ごとの季語
- 「桜」の季節ごとの季語
- 「梅」の季節ごとの季語
- 「椿」の季節ごとの季語
- 「滝」の季節ごとの季語
- 「燕」の季節ごとの季語
- 「牡丹」の季節ごとの季語
- 「百合」の季節ごとの季語
- 「紅葉」の季節ごとの季語
- 「菊」の季節ごとの季語
- 「薔薇」の季節ごとの季語
- 「蛙」の季節ごとの季語
- 「蝶」の季節ごとの季語
- 「蟷螂」の季節ごとの季語
- 「雪」の季節ごとの季語
- 「雲雀」の季節ごとの季語
- 「雷」の季節ごとの季語
- 「露」の季節ごとの季語
- 「鴨」の季節ごとの季語
迷わない季語選び!『四季を語る季語』で俳句を楽しもう
季語を選ぶ際には、様々な要素を考慮する必要がありますが、従来の歳時記には子季語の意味が詳しく記載されていないため、適切な季語を選ぶのが難しいという課題がありました。
『四季を語る季語』は、全ての子季語の意味を網羅することで、この課題を解決し、よりスムーズな季語選択を可能にします。
↓↓下の本がそうです。
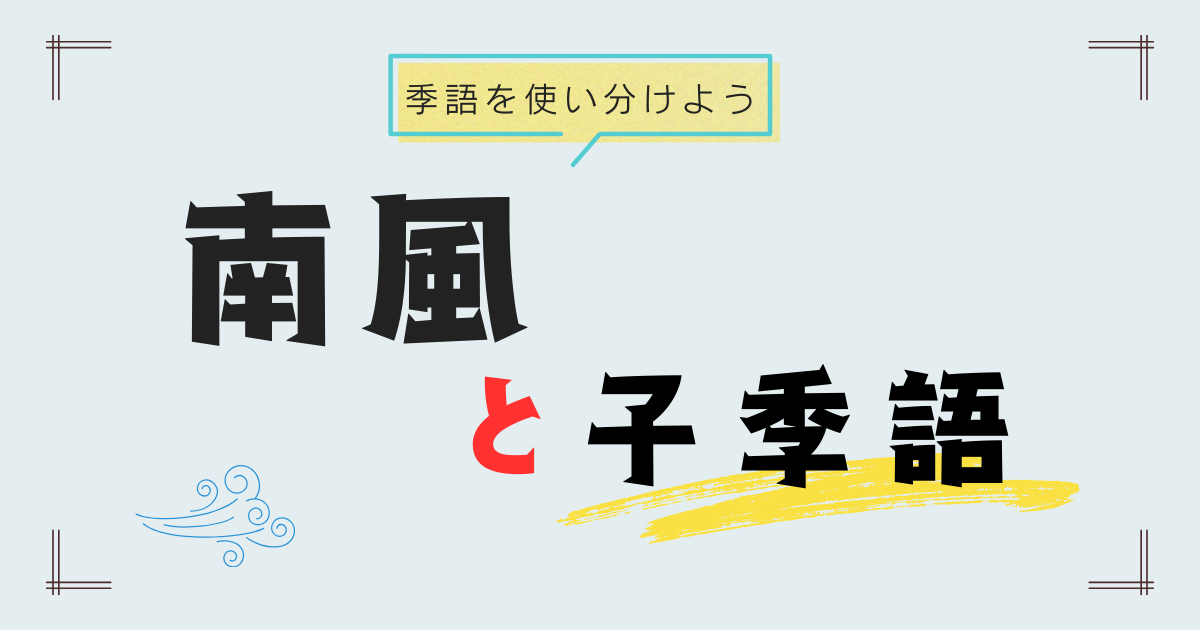


コメント