牡丹と言えば俳句では夏の季語です
ただ牡丹は四季のそれぞれに別の顔を見せます
ここでは、四季それぞれの牡丹の季語と、その意味を紹介しています
俳句作りの参考になさってください
夏の牡丹
牡丹(ぼたん)、ぼうたん
ボタン科の落葉低木
5月ごろ、白・紅・紫・黄色など芳香のある大輪の花を咲かせる
| この世から三尺浮ける牡丹かな 小林貴子 | 小林貴子の句集(Amazon) >> |
| しづかにてぼうたんに時経つつあり 桂信子 | 桂信子の句集(Amazon) >> |
| 待ち合わせ大師の牡丹懐かしく 佐藤邦子 | 佐藤邦子の句集(Amazon) >> |
深見草(ふかみぐさ)、二十日草(はつかぐさ)、富貴草(ふうきぐさ)
ボタンの別名
白牡丹(はくぼたん、しろぼたん)
白色の牡丹花
| 崩れむとして白牡丹羽ひらく 石原八束 | 石原八束の句集(Amazon) >> |
| 牡丹百巡りしあとの白牡丹 榮水朝夫 | - |
牡丹園(ぼたんえん)
牡丹を咲かせている庭
| 骨折れの傘かたく巻き牡丹園 大中祥生 | - |
野牡丹(のぼたん)
ノボタン科の常緑低木
7月~8月ごろ、枝先に紅紫色の五弁の花をつける
牡丹に似ていないが、牡丹のように美しいのでこの名がついた
狐の牡丹(きつねのぼたん)、山狐の牡丹(やまきつねのぼたん)
キンポウゲ科の多年草
野原や田の畦、道ばたなどで見られる
葉が牡丹に似るところからつけられた名前
実の形からコンペイトウグサとも呼ばれる
松葉牡丹(まつばぼたん)
葉は松葉に似て、花は牡丹のように鮮やかなところからこの名がついた
冬の牡丹
牡丹焚火(ぼたんたきび)、牡丹焚く(ぼたんたく)、牡丹供養(ぼたんくよう)
須賀川牡丹園や、奈良県の長谷寺でおこなわれる
天寿を全うした牡丹の枯木を、感謝と供養のために焚く
| 牡丹焚く口紅薄すぎはせぬか 渋川京子 | - |
| 牡丹焚く宙に青衣の女人の手 平井照敏 | 平井照敏の句集(Amazon) >> |
牡丹粗朶(ぼたんそだ)
牡丹焚火の為に枝を切り集めること
粗朶(そだ)とは、焚き木などのために切り取った木の枝を指す
牡丹鍋(ぼたんなべ)、猪鍋(ししなべ)、山鯨(やまくじら)
猪の肉を用いた鍋料理
野菜、焼豆腐、糸蒟蒻などと一緒に煮る
味付けは味噌あるいは醤油
山鯨(やまくじら)とは、イノシシ(更に、獣)の肉の異称
| 猪鍋を喰ひまぼろしの真神呼ぶ 八重樫弘志 | - |
| 足音を消し猪鍋の座に着けり 岩淵喜代子 | 岩淵喜代子の句集(Amazon) >> |
葉牡丹(はぼたん)
アブラ菜科の越年草でキャベツの変種
牡丹に似ているため、この名が付いた
正月用の生け花や鉢植として観賞される
| 葉牡丹に我が煩悩を投げ入れし 根岸敏三 | 根岸敏三の句集(Amazon) >> |
| 葉牡丹のなかはあざやかな生国 清水伶 | - |
牡丹菜(ぼたんな)
ハボタンの異名
寒牡丹(かんぼたん)、冬牡丹(ふゆぼたん)
夏の花である牡丹の花芽をつみとって冬に咲かせたもの
藁囲いをして、寒さの中大輪の花を咲かせる
年二度咲きの品種を仕立てている
| たましひの糧とも白の寒牡丹 平木智恵子 | 平木智恵子の句集(Amazon) >> |
| 人影のかたまつてくる寒牡丹 川崎展宏 | 川崎展宏の句集(Amazon) >> |
| 藁帽子冠りて咲くや寒牡丹 長谷川郁子 | 長谷川郁子の句集(Amazon) >> |
| 藁づともきつうなりたる寒牡丹 木幡忠文 | 木幡忠文の句集(Amazon) >> |
春の牡丹
牡丹の芽(ぼたんのめ)
牡丹は早春に朱色の太い芽が膨らむ
春の到来を教えてくれる
| ゆつくりと光が通る牡丹の芽 能村登四郎 | 能村登四郎の句集(Amazon) >> |
| ビニールの姐様かむり牡丹の芽 阿波野青畝 | 阿波野青畝の句集(Amazon) >> |
秋の牡丹
牡丹の根分(ぼたんのねわけ)
牡丹の良い株を選んで、移し植えること
| 大輪を夢見牡丹の根分けかな 黒川みつを | - |
牡丹の接木(ぼたんのつぎき)
2個以上の牡丹を、人為的に作った切断面で接着して、1つの個体とすること
牡丹植う(ぼたんうう)
牡丹を植えること
「植う(うう)」は「植える」の文語形
草牡丹(くさぼたん)
キンポウゲ科の落葉半低木
葉の形がボタンに似ることからこの名がついた
北海道から本州にかけての山地、林道脇などに分布
鐘形(ベル)のような花をまばらに付ける
牡丹の有名な俳句
牡丹の有名な俳句はいろいろありますが、個人的に好きな牡丹の俳句です
| 花ながら植ゑかへらるる牡丹かな 越人 | - |
| 牡丹散りて打ちかさなりぬ二三片 蕪村 | 蕪村の句集(Amazon) >> |

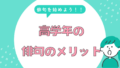

コメント