単に蛙というと春の季語ですが、夏にも蛙に関連する季語が存在します。蛙が春の季語とされるのは、主に3月頃、その年の最初に鳴き声を聞くことからきています。初燕や初蝶のように、一年の中で最初に目にするという事象を重んじる日本の風習が、蛙を春の季語とする理由の一つと言えるでしょう。
春の季語の一覧 >>>
春の蛙
蛙(かえる、かわず)
蛙は、田に水が張られるころ、雄は雌を求めてさかんに鳴き始める
昼夜の別なくなき続け、のどかさを誘う
「かはず」はもともとカジカガエルのことをさしていたが、平安時代から一般の蛙と混同されるようになった。
| ふかざけのくせまたつきし蛙かな 久保田万太郎 | 久保田万太郎の句集(Amazon) >> |
| 五と七の間で苦労する蛙 高橋京子 | 高橋京子の句集(Amazon) >> |
遠蛙(とおかわず)
遠くから聞こえるカエルの声のこと
| あまい指からだのなかに遠蛙 赤野四羽 | 赤野四羽の句集(Amazon) >> |
| ざわざわと雲の音する遠蛙 山崎文子 | 山崎文子の句集(Amazon) >> |
殿様蛙(とのさまがえる)
体長5~9センチ
背面は緑色ないし褐色で黒色斑紋があり、背の中央を黄色の線が走る
腹面は白または淡黄色
金線蛙(きんせんかへる)とも呼ぶ

赤蛙(あかがえる)
体長4~7センチ
背面は赤褐色で、目の後方からのびて体側を走る一対の背側線はほとんど曲がらない
日本のカエル類では最も早い2月ごろに産卵
本州・四国・九州の平地に分布

| 始めあり赤蛙跳ねるダムへの路 金子兜太 | 金子兜太の句集(Amazon) >> |
土蛙(つちがえる)
体長約4~6センチ
背面は暗褐色で線状やいぼ状の突起があり、腹面は灰色で斑紋が散在。4~6月ごろ産卵、おたまじゃくしのまま越冬し、翌年成体となる
本州以南に分布
いぼかへるとも呼ぶ

| 土蛙浮み紅葉手宗吾生地 香西照雄 | - |
初蛙(はつかわず)
春になると田んぼに水が張られ、繁殖期を迎えた蛙(かはず・かえる)たちが、元気よく鳴きはじめる
その年に初めて聞く蛙の声を初蛙
| ひとごゑがハウスの中に初蛙 齊藤美規 | 齊藤美規の句集(Amazon) >> |
| 妻子いま夕餉のころか初蛙 長谷川櫂 | 長谷川櫂の句集(Amazon) >> |
昼蛙(ひるかわず)
昼に聞く蛙の声を昼蛙なという
| 昼蛙どの畦のどこ曲ろうか 石川桂郎 | 石川桂郎の句集(Amazon) >> |
| 昼蛙なれもうつつを鳴くものか 室生犀星 | 室生犀星の句集(Amazon) >> |
夕蛙(ゆうかわず)
夕方に聞く蛙の声を夕蛙なという
| 夕蛙犬に引かれて一万歩 安井やすお | - |
| 明日はまた明日の日程夕蛙 高野素十 | 高野素十の句集(Amazon) >> |
夜蛙(よるかはわず)
夜に聞く蛙の声を夜蛙なという
| 夜蛙やくすり買ふ金敷寢して 目迫秩父 | 目迫秩父の句集(Amazon) >> |
| 夜蛙や歸郷促す母の文 目迫秩父 | 目迫秩父の句集(Amazon) >> |
筒井の蛙(つついのかわず)
井戸の中の蛙
蛙合戦(かえるがっせん)
繁殖期に一斉に水場に来てオスがメスを奪い合うこと
蛙軍(かえるいくさ)に同じ
鳴く蛙(なくかわず)
オスが鳴いてメスが選ぶこと
カエルの繁殖スタイル
オスの喉にある鳴(めい)のうと呼ばれる音を反響させて大きな鳴き声を出す
| KEROKEROと愚直に鳴く蛙かな 新谷ひろし | 新谷ひろしの句集(Amazon) >> |
苗代蛙(なしろかわず)
田植までの間、稲の苗(なえ)を育てるための田(苗代)にいる蛙のこと
通常、この時期はまだお玉杓子であることが多く
成長の早い個体が蛙となっている
| さざ波と見れば苗代蛙かな 井沢正江 | 井沢正江の句集(Amazon) >> |
| 尿前や苗代蛙昼鳴きて 茂里正治 | 茂里正治の句集(Amazon) >> |
田蛙(たかわず)
田に水が張られるころ、雄は雌を求めてさかんに鳴き始める
| 田蛙の囃すよ我が師と決めしより 小野元夫 | - |
| 田蛙の赤胴ごゑや月ひとつ 亀田蒼石 | 亀田蒼石の句集(Amazon) >> |
夏の蛙
夏蛙(なつがえる)、夏の蛙(なつのかえる)
夏に見られる蛙
夏は活動が最も活発になり、池や沼、水田などで蛙の姿を見かける
雨蛙(あまがえる)
小形の、かえるの一種。体は緑色であるが、周囲の状態によって変色する
指には吸盤が発達。草原・林にすみ、湿度に敏感で雄は夕立前によく鳴く

| 保護色となりて声上ぐ雨蛙 大竹照子 | - |
| 墓碑名の深みにありし雨蛙 今井園子 | - |
| 路地裏の祠に祈る雨蛙 小河原節子 | 小河原節子の句集(Amazon) >> |
枝蛙(えだかわず)
雨蛙の別称
樹上から卵を水中に落として産卵する
この時に枝にいる姿を見かける
| 枝蛙喜雨の緑にまぎれけり 西島麦南 | 西島麦南の句集(Amazon) >> |
青蛙(あおがえる)

| 新未来おもんぱかりて青蛙 中島房子 | - |
| 水滴をギラリと見せる青蛙 栗田希代子 | 栗田希代子の句集(Amazon) >> |
河鹿(かじか)、河鹿蛙(かじかがえる)
鳴き声がシカに似ており、川の鹿という意味で河鹿(かじか)と呼ばれる
フィー、フィーという鹿のような美しい鳴き声

| 湯浴み後の木椅子へ峽の河鹿鳴く 原田正子 | - |
河鹿笛(かじかぶえ)
河鹿を捕まえるときに吹く笛のこと
| 噛み合はぬ会話の間の河鹿笛 足立敏子 | - |
| 河鹿笛谷川の風抜ける宿 山本孝子 | - |
蟇(ひきがえる)、蝦蟇(がま)、蟾蜍(ひきがえる)、蟾(ひき)
体が大きく、皮膚にはいぼがたくさんある
竹藪や林に棲み、普段はあまり水に入らない
頭の両側から白色の毒液を出して難をのがれる
夜行性

| ひきがへるにも喉仏ありさうな 石倉夏生 | 石倉夏生の句集(Amazon) >> |
| ひきがへる眠り薬がまだ効かぬ 山田征司 | - |
牛蛙(うしがえる)
背面は褐色または緑〜暗緑色で黒褐色の斑紋がある
平地の池に多く、夜間、ウシに似た大きな声で鳴く
昆虫・魚介類を捕食

| 牛蛙途上の思いばかりなり 和知喜八 | 和知喜八の句集(Amazon) >> |
| 腹の底の暗さを思う牛蛙 山崎せつ子 | - |
四季でみられる季語の関連記事
- 「南風」と関連季語の意味
- 「夕焼け」の季節ごとの季語
- 「天の川」の季節ごとの季語
- 「旱」の季節ごとの季語
- 「月」の季節ごとの季語
- 「朝顔」の季節ごとの季語
- 「桜」の季節ごとの季語
- 「梅」の季節ごとの季語
- 「椿」の季節ごとの季語
- 「滝」の季節ごとの季語
- 「燕」の季節ごとの季語
- 「牡丹」の季節ごとの季語
- 「百合」の季節ごとの季語
- 「紅葉」の季節ごとの季語
- 「菊」の季節ごとの季語
- 「薔薇」の季節ごとの季語
- 「蛙」の季節ごとの季語
- 「蝶」の季節ごとの季語
- 「蟷螂」の季節ごとの季語
- 「雪」の季節ごとの季語
- 「雲雀」の季節ごとの季語
- 「雷」の季節ごとの季語
- 「露」の季節ごとの季語
- 「鴨」の季節ごとの季語


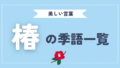
コメント