 俳句の疑問
俳句の疑問 俳句の『有季定型』とは
「五・七・五」の短い言葉の中に、深い情景や感情を込める俳句。俳句の世界には、「有季定型」という言葉があります。俳句をうまく作るための、要となる大切なルールです。ここでは、そんな「有季定型」について解説をしていきたいと思います。有季定型の読み...
 俳句の疑問
俳句の疑問 俳句の『漢字』の疑問
俳句を作るとき、こんな疑問を感じたことはありませんか? 「この漢字、どうやって音を数えるんだろう?」 「なんで難しい漢字ばかり使うんだろう?」この疑問を解消して、俳句の楽しさをより深く味わえるよう、この記事では俳句と漢字の関係を初心者にもわ...
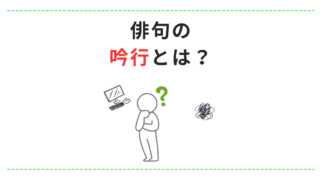 俳句の疑問
俳句の疑問 俳句の『吟行』とは
「吟行」という言葉をご存知でしょうか?俳句を作っている方にはおなじみですが、あまり聞きなれないかもしれませんね。ここでは、「吟行」の意味ややり方などを説明します。吟行の読み方吟行(ぎんこう)と読みます。吟行とは「吟行」とは、俳句を作るために...
 俳句の疑問
俳句の疑問 俳句の『切れ字』とは
俳句の「切れ字」とは、句の中で意味やリズムを区切り、一句をより引き締める役割を持つ特別な言葉のことです。五・七・五のたった17音の中に、作者の感動や情景を凝縮させるために、この切れ字が重要な働きをします。俳句は、五・七・五という短い音数の中...
 俳句の疑問
俳句の疑問 俳句の『季語』とは
前回俳句の重要ルールは「季語」と「5・7・5」の2つと説明しました >>>ここでは、「季語」とは何かについて説明します。季語とは?俳句には必ず季語を入れるというルールがあります。季語とは、四季や季節の移り変わりを表す言葉のことです。たとえば...
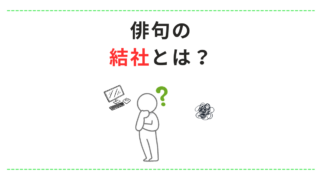 俳句の疑問
俳句の疑問 「俳句結社」の内容から探し方まで
俳句結社を簡単に説明するなら、「俳句を学ぶ人々の集まり」です。共通の師(主宰者)のもと、俳句を学び、お互いの作品を批評し合うグループや組織のことです。なぜ結社に入るのか?俳句は一人でも作れますが、結社に入ることで以下のようなメリットがありま...
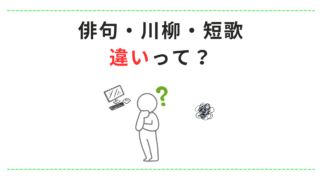 俳句の疑問
俳句の疑問 「俳句・川柳・短歌」の違い
「俳句・川柳・短歌」という言葉があるけれど、具体的にどのように違うのか分からない、という人のために、それぞれの違いを解説していきます。俳句・川柳・短歌の読み方「俳句・川柳・短歌」のそれぞれの読み方は次の通りです。俳句(はいく)川柳(せんりゅ...
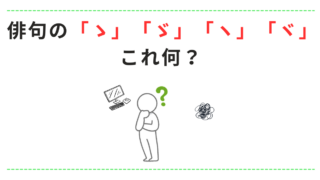 俳句の疑問
俳句の疑問 昔の俳句で見られる「ゝ」「ゞ」「ヽ」「ヾ」とは
昭和初期以前の俳句作品を見ていると、「ゝ」「ゞ」「ヽ」「ヾ」といった記号が出てきます。これらの意味を紹介します。作品作りで使うことは無いと思いますが、過去の作品を鑑賞するときには見かけるので、意味を知っておくと良いと思います。
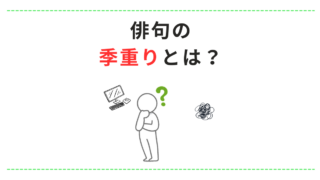 俳句の疑問
俳句の疑問 俳句の『季重なり』とは
「「季重なり」の読み方」「同じ季語が2つあるときは季重なり?」「季重なりは良いの?悪いの?」など、さまざまな視点で「季重なり」解説しています。
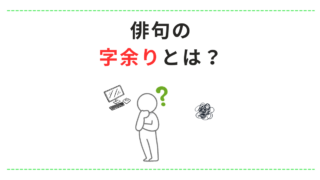 俳句の疑問
俳句の疑問 俳句の『字余り・字足らず』とは
「字余り・字足らず」の違いが判らない。どこまでの「字余り・字足らず」が許されるの?など、俳句を作る際に不安を覚える方は多くいると思います。ここでは、「字余り・字足らず」の意味や、俳句での効果などについて解説します。「字余り・字足らず」とは俳...