 俳句を作る
俳句を作る 動物の特徴で俳句を作ると良い
動物の特徴で俳句を作る時、まず次の説明文「何が どんな風にして どうした」の説明文を書いてから手直しをすると、簡単に俳句になります(このブログを読んでいる人も、一緒にやってみましょう)「何が どんな風にして どうした」の一文を書きますがこの...
 俳句を作る
俳句を作る  俳句を作る
俳句を作る  俳句を作る
俳句を作る  俳句を作る
俳句を作る  俳句を作る
俳句を作る  俳句を作る
俳句を作る 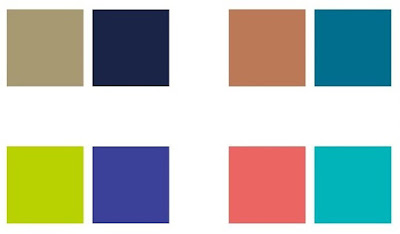 俳句を作る
俳句を作る  俳句を作る
俳句を作る  俳句を作る
俳句を作る  俳句を作る
俳句を作る