 季語の世界
季語の世界 冬の季語の謎!「しばれる」と「からしばれ」の違い
厳しい冬の寒さを表す季語に、「しばれる」があります。この言葉には、「しばれ」や「からしばれ」といった、よく似た言葉がありますが、一体何が違うのでしょうか?冬の季語の一覧 >>>季語に隠された、北国の言葉これらの言葉は、特に北海道や東北地方の...
 季語の世界
季語の世界  季語のいろいろ
季語のいろいろ  季語のいろいろ
季語のいろいろ 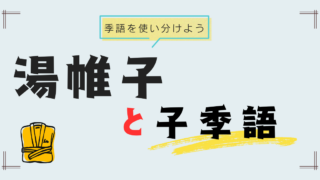 季語と子季語のそれぞれの意味
季語と子季語のそれぞれの意味  季語のいろいろ
季語のいろいろ  季語の世界
季語の世界  季語の世界
季語の世界  季語の世界
季語の世界  季語の世界
季語の世界  季語の世界
季語の世界