
俳句での送り仮名のルールを説明してます
俳句で漢字を使う際には、送り仮名の有無によって言葉の意味が大きく変わることがあります。このルールを正しく理解することで、より深く俳句の世界を楽しむことができるでしょう。
名詞と動詞の区別
- 名詞: 事物や概念を表す言葉で、送り仮名は付けません。
- 動詞: 行為や動作を表す言葉で、送り仮名を付けます。
シンプルなルールですが、これにより名詞と動詞が明確に区別され、作者の意図がより正確に読者に伝わります。
逆に言うと、送り仮名を不要に省略すると、言葉の意味が変わったり、誤読の原因にもなりやすくなります。
| 省略後の表記 | 読み方が分からなくなる |
| 違 | 「ちがう」(動詞)か「ちがい」(名詞)か区別しにくい。 |
| 話 | 「はなす」(動詞)か「はなし」(名詞)か区別しにくい。 |
| 残 | 「のこる」(動詞)か「のこり」(名詞)か区別しにくい。 |
俳句を例に見てみる
実際に俳句を使って、送り仮名を省略したものと、送り仮名があるものとで、意味がどのように変化するのかを見てみましょう。
「秋祭」と「秋祭り」
- 秋祭: 送り仮名がないので名詞です。「秋祭りが行われている」という状態を表します。
- 秋祭り: 送り仮名があるので動詞です。「秋を祭る」という行為を表します。
では、この名詞か動詞かの違いによって、どのように意味が変わるのかを、実際の俳句で見ていきたいと思います
次のような俳句があります
秋祭 今宵は母も 化粧して
秋祭り 今宵は母も 化粧して
上の「秋祭」は名詞なので、俳句の意味は「秋祭が行われている、今宵は母も化粧をして参加する」となります
下の「秋祭り」は動詞なので、俳句の意味は「(豊作を感謝して)秋を祭る 今宵は母も化粧をしている」となります
このように、名詞か動詞かによって内容が変わってきます
言い換えると、送り仮名の一文字で、内容が変わってしまう可能性があるということです
他にも見てみましょう
「神祭」と「神祭り」
- 神祭: 送り仮名がないので名詞です。「神祭(行事)」というものを表します。
- 神祭り: 送り仮名があるので動詞です。「神様を祭る」という行為を表します。
夏の夜の 村の外れに 神祭
夏の夜の 村の外れに 神祭り
上の「神祭」は名詞なので、俳句の意味は「夏の夜に村の外れで神祭(行事)が行われている」となります
下の「神祭り」は動詞なので、俳句の意味は「夏の夜に村の外れで神様を祭った」となります
「金魚売」と「金魚売り」
- 金魚売: 送り仮名がないので名詞です。「金魚を売る」という行為を行う場所(金魚屋)または、人を指します。
- 金魚売り: 送り仮名があるので動詞です。「金魚を売る」という行為を指します。
金魚売 金魚に少し 餌をやり
金魚売り 金魚に少し 餌をやり
上の「金魚売」は名詞なので、俳句の意味は「金魚屋の主人が、金魚に餌をやっている」となります
下の「金魚売り」は動詞なので、俳句の意味は「金魚を売った。(残った)金魚に餌をやる」となります
今見てきたように、たった一文字の送り仮名ですが、言葉の意味を大きく変えてしまいます。
特に俳句のように短い言葉で表現する世界では、この違いは非常に重要です。
長文であれば、間違って送り仮名がついていたとしても、文脈からある程度意味を推測して、修正して鑑賞できますが、俳句ではそれができません。
間違った意味で、作品を鑑賞されてしまう可能性も出てしまうということです。
動詞の送り仮名のルール
動詞には送り仮名を付けますが、送り仮名のつけ方にはルールがあります。
原則は「活用語尾を送る」です。
つまり、動詞が活用する際の
変化する部分は、ひらがな(送り仮名)
変化しない部分は漢字です。
例: 書く、読む、生きる、考える、憤る
この原則を踏まえたうえで、派生的なルールも紹介します。
①他の語を含む語の送り方
活用しない部分に、他の動詞の活用形やそれに準ずるものが含まれる動詞は、含まれている動詞の送り仮名の付け方によって送ります。
例:
動かす(もとは「動く」)
照らす(もとは「照る」)
浮かぶ(もとは「浮く」)
②例外・慣用的なもの
一部の語では、慣用として活用語尾の前の音節から送ることが許容されています。
例:
表わす(「表す」も可)
現われる(「現れる」も可)
行なう(「行う」も可)
断わる(「断る」も可)
③複合語
二つ以上の語が結びついた複合語(例:「書き抜く」「申し込む」)は、それぞれの単独の語の送り仮名の付け方によります。
ただし、読み間違えるおそれのない場合は、送り仮名を省くことが許容されているものもあります(例:書き抜く→書抜く、申し込む→申込むなど)。
先にも説明しましたが、ルールを無視して送り仮名を省略すると、名詞と動詞の区別がつかなくなったり、作品の意味も変わってしまう可能性が高まります。
まとめ
俳句における送り仮名のルールは、名詞と動詞を見分けるための重要な手がかりというだけでなく、正確に作品の意味を読者に伝える意味でも重要です。
俳句を始める上で最初に押さえておきたい基本事項の一つです。
このルールを正しく理解することで、より深く俳句の世界を楽しむことができるはずです。
ポイント
- 名詞は送り仮名なし、動詞は送り仮名あり
- 動詞の送り仮名にもルールはある
- 送り仮名一つで意味が大きく変わる
- 俳句では、特に送り仮名が注意して使われている
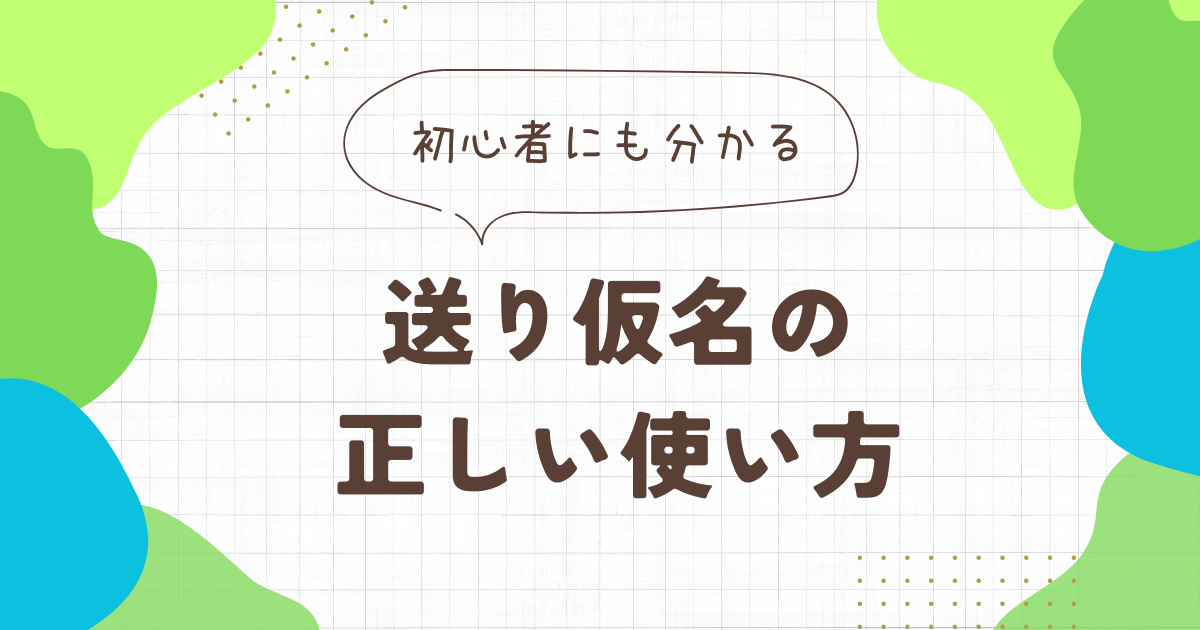
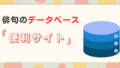

コメント