ショウブ、アヤメ、カキツバタは、いずれもアヤメ科アヤメ属の植物で、初夏の水辺を彩る美しい花々です。
しかし、俳句の世界では、これらの花を詠み分けることで、情景や季節感をより細やかに表現します。ここでは、それぞれの違いと、俳句における特徴を解説します。
写真で見比べる
葉や花の違い
| | 葉の違い | 花弁の違い |
| ショウブ | 葉脈がくっきり | 根元に黄色い模様 |
| アヤメ | 細長い | 根元に網目模様 |
| カキツバタ | 幅広
葉脈は目立たない | 根元に白い筋 |
季節の違い
| | 咲く時期 | 季語の季節 |
| ショウブ | 六月上旬 | 夏 |
| アヤメ | 五月上旬 | 夏 |
| カキツバタ | 五月中旬 | 夏 |
咲く場所
「あやめ」という季語の注意点
俳句では、「しょうぶ」と「あやめ」という2つの季語が使われますが、少し注意が必要です。
「あやめ・あやめ草」と書いた場合、ショウブ科の多年草である菖蒲(しょうぶ)の古名を指します。
現在「あやめ」として認識されているアヤメ科の多年草を指す場合は、「花あやめ」もしくは、漢字で「渓蓀」と書きます。
こうすることによって、二つの違いを明確にしています。
ショウブ科の「しょうぶ」の表記
- しょうぶ: ショウブ科の多年草。漢字で「菖蒲」と書く。
- 菖蒲: ショウブ科の多年草。「しょうぶ」と読む。
- 花菖蒲: ショウブ科の多年草。「はなしょうぶ」と読む。
- あやめ: ショウブ科の多年草である「菖蒲(しょうぶ)」の古名。
- あやめ草: ショウブ科の多年草である「菖蒲(しょうぶ)」の古名。
アヤメ科の「あやめ」の表記
- 花あやめ: アヤメ科の多年草。漢字では「花渓蓀」と書く。
- 渓蓀: アヤメ科の多年草。菖蒲の古名である「あやめ」と区別するために漢字で表記する。
上の表記を見てもわかるように、俳句の世界では、「あやめ」と書く際には注意が必要です。
今も古名の「あやめ」が使われる理由は、古くから使われている季語に「あやめ兜」「あやめ人形」「あやめの衣」「あやめ酒」などがあり、これらの言葉が昔の作品によく見られるからです。
ちなみに、アヤメ科の「あやめ」の漢字表記は、現在の辞典には「菖蒲、文目、綾目」が使われています。「菖蒲」は混同して使えないですし、「花あやめ」と書いても混乱を招きそうです。
そうなると、歳時記には表記されていませんが、アヤメ科の「あやめ」を詠む場合は「文目、綾目」の漢字を使うと、誤読されなくなるのではないでしょうか。
季語「ショウブ、アヤメ、カキツバタ」の違い
| 季語 | 時期 | 意味 |
ショウブ
(菖蒲) | 夏 | ショウブ科の多年草。池や沼などの湿地に自生し、草高50~120センチ。葉は芳香があり剣状で、5~7月にかけて葉の間から約5センチの円柱型の花穂をつける。端午の節句の菖蒲湯に用いられる。 |
アヤメ
(渓蓀) | 夏 | アヤメ科の多年草。草高約50センチで、日当たりのよい乾いた草地に自生。葉は細長く剣状で、夏に紫または白色の花が咲く。花びらの付け根は黄色で網目模様がある。園芸目的に栽培される。 |
カキツバタ
(燕子花) | 夏 | アヤメ科の多年草。草高30~80センチ。5~6月ごろ池や沼などの水辺に濃紫の大きな花を咲かせる。園芸種では白やしぼりもある。ハナショウブに似るが、カキツバタは花びらの付け根から中央にかけて白い筋が一本走るので見分けがつく。燕の姿を思わせる姿から「燕子花」と書く。日本原産。 |
ショウブに関連する季語
| 季語 | 季節 | 意味 |
| 菖蒲の根分 | 春 | 菖蒲を根分けすること。菖蒲は春に新芽を出すが、根が込み合うと弱ってしまうため株分けをする。 |
| 菖蒲葺く | 夏 | 端午の節句の前日の夜に家の軒に菖蒲を挿して飾ること。災厄や邪気を払う目的で行われた。古く宮廷で始まったが、その後武士や庶民にも伝わった。 |
| 菖蒲湯 | 夏 | 5月5日の節句の日、菖蒲の根や葉を入れて沸かした風呂のこと。邪気を払う意味があった。 |
ショウブの俳句
「菖蒲」の例句
「あやめ」の例句
「あやめ草」の例句
「花菖蒲」の例句
「野花菖蒲」の例句
「白菖蒲」の例句
「菖蒲園」の例句
「菖蒲見」の例句
アヤメの俳句
「渓蓀」の例句
「花渓蓀」の例句
カキツバタの俳句
「燕子花」の例句
関連記事



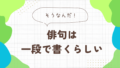

コメント