「吟行」という言葉をご存知でしょうか?
俳句を作っている方にはおなじみですが、あまり聞きなれないかもしれませんね。
ここでは、「吟行」の意味ややり方などを説明します。
吟行の読み方
吟行(ぎんこう)と読みます。
吟行とは
「吟行」とは、俳句を作るために外に出て、あちこちを歩き回ることです。
一人で、あるいは仲間たちと一緒に、自然や街の風景に触れながら言葉を探す、それが吟行です。
複数人で行ったときは、吟行の後に公民館の一室などで句会を開催して、その時に作った俳句を披講します。
吟行をする場所
行く場所は、名所・旧跡などに出かけることもありますし、近くの公園に行くこともあります。
参加者の生きやすい場所が選ばれます。
吟行をする意味
私たちは日々の生活の中で、俳句の題材を探しがちです。しかし、どうしても似たような発想や表現になりがちで、作品がマンネリ化してしまうことがあります。そんなときに、吟行をすると新鮮な俳句が生まれることがあります。
普段は通り過ぎてしまうような景色も、俳句の題材を探すという目的を持つことで、いつもとは違ったものに見えてきます。
吟行のやり方
1.行き先を決めます。
2.吟行を行う場所に集合します。
3.参加者それぞれが数時間付近を散策して俳句を作ります。
4.そこで作った作品を発表します。
5.その後に、吟行句会をすることもあります。
吟行句の作り方
吟行では、せっかくなので、その場所でしか見ることができないもので俳句を作りましょう。
また、作るときは題材を絞り込むのがおすすめです。
例えば「桜」をテーマにする、と決めた場合をみましょう。いつもなら数分で通り過ぎる桜の木の前で、20分、30分とじっくり時間をかけて観察してみてください。
すると、今まで気づかなかった発見があるはずです。風に揺れる花びらの音、幹に刻まれた年月の痕跡、その桜の木に集まる鳥や昆虫たちの姿…。そうした細やかな発見こそが、瑞々しい俳句を生み出すヒントになります。
あれこれと欲張ってたくさんの題材を詠もうとすると、どの作品も中途半端になりがちです。
吟行では、心惹かれた題材を1つか2つに絞り、じっくりと向き合うのが成功の秘訣です。もし、他にも気になるものがあれば、スマートフォンのカメラで撮影しておいて、後でゆっくりと俳句にすることもできますよ。
吟行の持ち物
絶対に持っていきたいもの
- ノートとペン: 見つけた題材や、心に浮かんだ言葉をすぐに書き留めましょう。
- 歳時記: 季語を調べるのに欠かせません。
あると便利なもの
- 電子辞書: 季語の意味や漢字を調べるのに役立ちます。
- カメラ: 後で俳句を作るための題材を記録できます。
吟行の後は「句会」で交流
一人で楽しむのもいいですが、仲間たちと吟行に出かけるのもおすすめです。
吟行の後に、その場で詠んだ俳句をみんなで持ち寄り、句会を開くことがあります。
お互いの作品を鑑賞し、感想を言い合うことで、自分の視点とは違う発見があったり、新しい発想に出会えたりします。
俳句の疑問に関する記事
- 俳句の『漢字』の疑問
- 俳句の『切れ字』とは
- 俳句の『取り合わせ』とは
- 俳句の『句切れ』とは
- 俳句の『自由律俳句』とは
- 俳句の『有季定型』とは
- 昔の俳句で見られる「く」「ぐ」とは
- 昔の俳句で見られる「ゝ」「ゞ」「ヽ」「ヾ」とは
- 「俳句結社」の内容から探し方まで
- 俳句の『季重なり』とは
- 俳句の『季語』とは
- 俳句の『字余り・字足らず』とは
- 俳句の『吟行』とは
- 「俳句・川柳・短歌」の違い
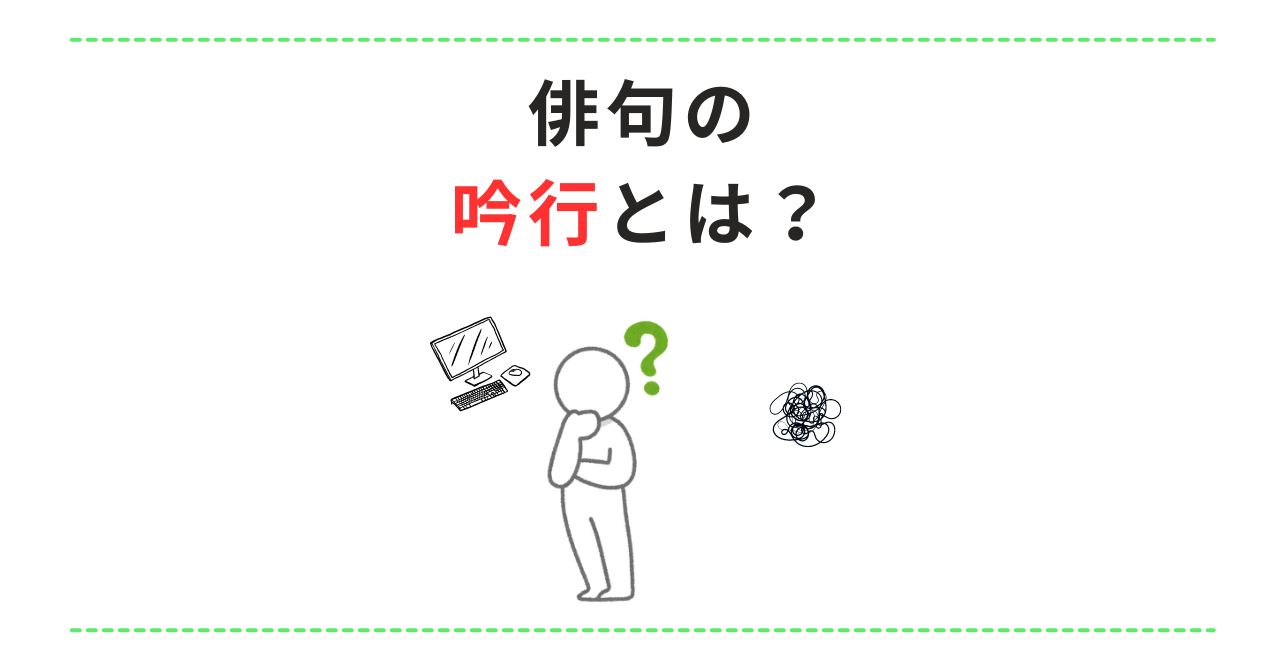

コメント