「字余り・字足らず」の違いが判らない。
どこまでの「字余り・字足らず」が許されるの?
など、俳句を作る際に不安を覚える方は多くいると思います。
ここでは、「字余り・字足らず」の意味や、俳句での効果などについて解説します。
「字余り・字足らず」とは
俳句は、一般的に「五・七・五」の十七音でつくられます。これは、心地よいリズムを生み出すための大切なルールです。
しかし、この型をあえて崩す表現方法が「字余り」や「字足らず」です。
- 字余り(じあまり)
五・七・五のどこかの音数が多くなること。
例)六・七・五 や 五・八・五など - 字足らず(じたらず)
五・七・五のどこかの音数が少なくなること。
例)四・七・五 や 五・六・五など
これを見ると、字余りの逆が「字足らず」、字足らずの逆が「字余り」とも言えます。
字余り・字足らずの数え方
字余りの数え方に決まったルールはありませんが、多くの場合、通常の五・七・五から何音増えているかで考えます。
字足らずは五・七・五から何音減っているかで考えます。
【例】
- 冬夕焼 電気匂って 市電来る
(ふゆゆうやけ でんきにおって しでんくる)
→ 「ふ・ゆ・ゆ・う・や・け」が六音となっています。
この場合は六・七・五の、字余りの俳句です。 - 夕焼けや 電気が匂って 市電来る
(ゆうやけや でんきがにおって しでんくる)
→ 「で・ん・き・が・に・お・っ・て」で八音となっています。
この場合は五・八・五の、字余りの俳句です。 - 夕焼け 電気匂って 市電来る
(ゆうやけ でんきにおって しでんくる)
→ 「ゆ・う・や・け」が四音となっています。
この場合は四・七・五の、字足らずの俳句です。
音数の数え方は、こちらでも詳しく解説しています。
字余り・字足らずは、何文字まで許される?
一般的には、五・七・五のどこか一箇所が一音か二音増えるくらいが、俳句のリズムを壊しすぎず、効果的に字余りの効果を出すとされています。
字余り・字足らずの効果
なぜ、わざわざ型を崩して俳句を作るのでしょうか?
それは、リズムに変化をつけることで、読み手により強い感情や印象を伝えるためです。
例えば、通常のリズムで読んでいるところに、字余りの句が来ると、少し長く読まざるを得なくなります。この「リズムの変化」に読者の意識が向き、作者の伝えたい言葉を際立たせるのです。
【例】
- 五・七・五
夏草や 兵どもが 夢の跡 松尾芭蕉
(なつくさや つわものどもが ゆめのあと)
→ スムーズに流れるような、心地よいリズムです。 - 字余り
旅に病んで 夢は枯れ野を かけ廻る 松尾芭蕉
(たびにやんで ゆめはかれのを かけめぐる)
→ 上五の「旅に病んで」が六音になっています。この「字余り」が、芭蕉の無念さを、句全体に行きわたらせています。 - 字足らず
兎も 片耳垂るる 大暑かな 芥川龍之介
(うさぎも かたみみたるる たいしょかな)
→ 上五の「兎も」が四音です。
この「字足らず」によって上五に間が生じます、これが、大暑によりぐったりとした兎の疲労感を感じさせます。
字余りと「句またがり」の違い
句またがりとは、五・七・五の区切りを無視して、言葉が次の句まで続いてしまう表現です。字余りと混同されがちですが、意味は大きく異なります。
【例】
- 字余り
旅に病んで 夢は枯れ野を かけ廻る 松尾芭蕉
(たびにやんで ゆめはかれのを かけめぐる)
→ 「たびにやんで」は六音で字余りですが、本来の上五と中七の区切りは守られています。 - 句またがり
虹のぼり ゆき中天を くだりゆき 山口誓子
(にじのぼり ゆきちゅうてんを くだりゆき)
→ 「にじのぼりゆき」というひとブロックの言葉が、上五と中七の区切りをまたいでいます。
字余りは音数が多いだけのことが多いですが、句またがりは言葉の区切りが曖昧になり、より自由で革新的な表現になります。初心者の方はまず、字余りの句をつくることから挑戦してみるのがおすすめです。
字余りが使いやすい場所
字余りは、句のどの部分でも使えますが、上五(最初の五音)で使うと、比較的リズムが崩れにくく、自然な俳句になります。
上五で字余り
- 冬夕焼 汽笛ならして 市電来る
(ふゆゆうやけ きてきならして しでんくる)
上五に六音の「冬夕焼(ふゆゆうやけ)」を置いても、上五と中七の区切りの場所まで「ふゆゆうやけ」と一気に読むため、違和感は少ない俳句になります。 - 散松葉の 緑はらはら 風のたび
(ちりまつばの みどりはらはら かぜのたび)
助詞(「の」「が」「に」など)をつけないと意味が通じないときは、助詞をつけて上五を字余りにすることがあります。
このような場合は、「散松葉の」で区切って読みます。
下五で字余り
下五(最後の五音)で字余りを使う場合もあります。
- わかたれて 湯気のつながる のっぺい汁
(わかたれて ゆげのつながる のっぺいじる)
上五に五音以上の名詞を置いて、名詞で句を締めくくる場合、五音以上でも問題のないことが多いです。
ただし、中七(真ん中の七音)や下五での字余りは、句全体が間延びしたり、重たい印象になったりすることがあります。
したがって、字余りを使う際は、上五から試してみるのがおすすめです。
初心者が意識したいこと
初心者のうちは、無理に字余りや字足らずを使わなくても大丈夫です。
まずは、五・七・五の型を守って句を詠むことに慣れていきましょう。
そのうえで、どうしても五・七・五におさまらない言葉がある場合や、リズムを変えてより強く表現したいと感じたときに、字余りや字足らずを試してみるのが良いでしょう。
その際は、「なぜここで字余りを使うのか」、「この字余りによってどんな効果を出したいのか」を考えてみると、より深みのある句が作れます。
字余りや字足らずは、俳句の表現の幅を広げてくれる技法です。ぜひ、恐れずに挑戦してみてください。
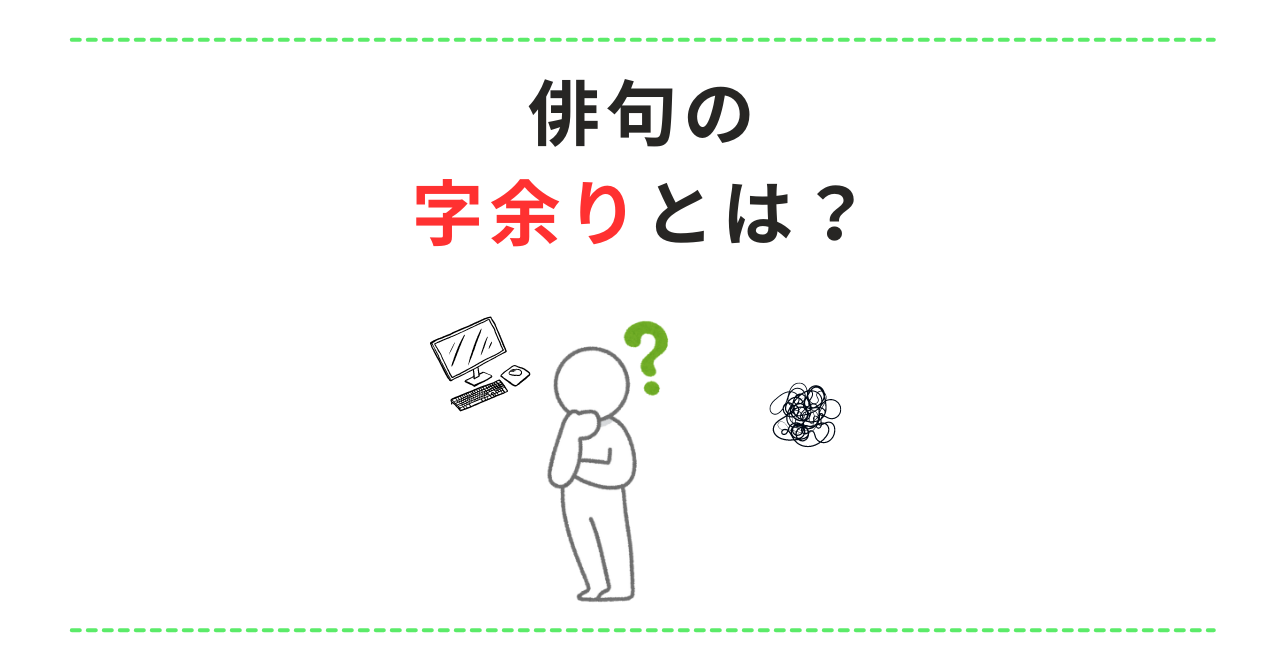



コメント