前回
俳句の重要ルールは「季語」と「5・7・5」の2つと説明しました >>>
ここでは、「季語」とは何かについて説明します。
季語とは?
俳句には必ず季語を入れるというルールがあります。
季語とは、四季や季節の移り変わりを表す言葉のことです。
たとえば、「桜」と聞けば春を、「入道雲」と聞けば夏を、「紅葉」と聞けば秋を、「雪」と聞けば冬を連想しますよね。
このように、季語はたった一言で、句の中に季節の空気感を吹き込む、いわば「俳句の要」の存在となっています。
俳句での季語の意味
季語は、単に季節がいつかを示すためだけにあるのではありません。
俳句において、次のような大切な役割を担っています。
- 情景を伝える 「古池や 蛙飛びこむ 水の音」という句は、「蛙」という季語があることで、のどかな春の風景が目に浮かびます。季語一つで、作者がどんな場所で、何を見て、何を感じたのかが、読み手に伝わります。
- 詩情を深める 季語には、長い歴史の中で育まれた文化や感情が詰まっています。「桜」という季語には、美しさだけでなく「はかなさ」や「別れ」といった日本人の心が込められています。季語を使うことで、句はより深い味わいや情緒を帯びます。
季節の5つの区分
季節の言葉である季語は、春・夏・秋・冬の四季だけでなく、「新年」という独立したカテゴリーがあります。
- 春:2月、3月、4月
- 夏:5月、6月、7月
- 秋:8月、9月、10月
- 冬:11月、12月、1月
- 新年:1月
このように、1月は「冬」と「新年」の両方にまたがっていますが、それぞれの季語は全く違うものです。
「冬」と「新年」の季語の違い
- 冬の1月:冬の寒さや、一年で最も寒い時期の様子を表す季語が多くあります。 例)枯野、寒椿、冬の月、氷、雪など
- 新年の1月:新しい年を迎えることにまつわる、おめでたい事柄や風物詩を表す季語が多くあります。 例)元旦、初詣、お年玉、門松、七草など
俳句を詠む際は、同じ1月でも、季節感をどう表現したいかによって季語を使い分ける必要があります。
季語の分類
季語は、その意味合いによって細かく分類されています。
このように分類されていることで、「春の植物」に何があるかを探したいときに、簡単に探すことができます。
- 時候:新年、立夏、秋分など、時期を表す言葉。
- 天文:日永(ひなが)、月、流れ星など、空に関わる言葉。
- 地理:雪、初凪(はつなぎ)、滝など、自然現象や地形を表す言葉。
- 生活:おせち、花見、浴衣など、人間の暮らしや行事に関わる言葉。
- 動物:猫の恋、蜩(ひぐらし)、鴨(かも)など、生き物に関する言葉。
- 植物:梅、桜、ひまわりなど、植物に関する言葉。
こちらに、四季+新年の季語一覧があります。参考になさってください。
季語の意味も知りたい方は、「季語検索」で平仮名で検索をすると意味がわかります。
季語の探し方3選
俳句を詠む中で、「この季語はどの季節かな?」「どんな季語があるんだろう?」と疑問に思うことがありますよね。そんな時に役立つ、季語の調べ方を3つご紹介します。
- 季語の一覧ページを見る
インターネット上には、季節ごとに季語がまとめられた一覧ページがあります。知らない季語があっても、そのまま検索すれば意味を調べられるので便利です。
「これは季語?」と思ったときは、ここで調べられます。(ひらがなで検索します)>> - 歳時記(さいじき)を買う
歳時記とは、季語とその季語が使われた俳句作品を集めた、いわば「季語の辞書」です。平均5,000語ほどの季語が掲載されています。初心者の方は、写真が多く、分かりやすい作品が載っているものから選ぶと良いでしょう。
Amazonで歳時記が売っています >> - 特定の書籍・電子書籍を活用する
膨大な数の季語を調べたい場合は、収録語数の多い専門書や電子書籍を活用するのも有効です。電子書籍の「四季を語る季語」は24,000語以上の季語が掲載されていて、Kindle Unlimitedなどの読み放題サービスを利用すれば、無料で読めます。
Kindle Unlimitedの登録ページはこちら >>>
「季語の辞書」と呼ばれる歳時記に関する記事も書いています。
俳句に季語を入れるメリット
「俳句には季語を必ず入れるべき」と言われますが、厳密には絶対ではありません。
しかし、季語を入れることには大きなメリットがあります。
メリット1
言葉を省略できる
季語は、たった数文字の単語の中に、非常に多くの情報を含んでいます。
例えば、季語である「川鵜(かわう)」を俳句の中で使うと、「いつ(夏)」「どこで(川で)」「なにが(鵜が)」という情報を、言葉を尽くさずに伝えることができます。俳句は17音しかないので、言葉を省略できる季語は非常に便利です。
メリット2
多くのことを伝えられる
季語の中には、日本人が共有している思い出やイメージが詰まっています。
例えば、「桜」という言葉を見たとき、日本人は多くの人が共通して春の風景や思い出を連想します。しかし「石」や「車」のような言葉からは、多くの情報や共通の思い出は引き出されません。
季語は、読み手の想像力を引き出し、たった17音では表現しきれない深い世界観を、読み手と共有する役割を担っています。
「四季を語る季語」─電子書籍─
豊富な季語が収録されていて、全ての季語に丁寧な解説が書かれている電子書籍。
アマゾンプライム会員は、「春版」が無料で読めます(期間限定)
Kindle Unlimited会員は、「春夏秋冬+新年」の全てが無料で読めます
無季俳句とは
無季俳句という言葉があります。季語を使わずに詠まれた俳句のことです。
俳句は「季語を入れる」というルールが一般的ですが、あえて季語を使わないことで、季節にとらわれない普遍的な情景や、作者の個人的な感情を表現することができます。
無季俳句は、明治時代に俳人の河東碧梧桐(かわひがし へきごとう)が提唱した「新傾向俳句」の流れから生まれました。それまでの伝統的な俳句とは一線を画し、より自由な表現を追求した結果、無季の作品が作られるようになりました。
季語を使いこなすためのヒント
俳句を作る上で、季語を上手に使うためのポイントをいくつかご紹介します。
- 一つの句に季語は一つが基本
季語を複数入れると、季節感がぶつかり合ってしまい、伝えたいことがぼやけてしまいます。まずは一つの季語から情景を広げてみましょう。
複数の季語を使うことを「季重なり」といいます。「季重なり」についての記事はこちらに書いています。 - 必ずしも「季節=季語」ではない
俳句の世界では、実際の季節と季語の季節がずれる場合があります。例えば「七夕」は夏の行事ですが、俳句の世界では「秋の季語」とされています。季語を集めた「歳時記(さいじき)」という本で確認すると良いでしょう。
歳時記に関する記事もあります >>
季語は、俳句のルールであると同時に、作者と読み手をつなぐ大切な道しるべです。まずはあなたが好きな季語を一つ見つけて、そこから俳句の世界を広げてみてください。
俳句の疑問に関する記事
- 俳句の『漢字』の疑問
- 俳句の『切れ字』とは
- 俳句の『取り合わせ』とは
- 俳句の『句切れ』とは
- 俳句の『自由律俳句』とは
- 俳句の『有季定型』とは
- 昔の俳句で見られる「く」「ぐ」とは
- 昔の俳句で見られる「ゝ」「ゞ」「ヽ」「ヾ」とは
- 「俳句結社」の内容から探し方まで
- 俳句の『季重なり』とは
- 俳句の『季語』とは
- 俳句の『字余り・字足らず』とは
- 俳句の『吟行』とは
- 「俳句・川柳・短歌」の違い
「四季を語る季語」─電子書籍─
豊富な季語が収録されていて、全ての季語に丁寧な解説が書かれている電子書籍。
アマゾンプライム会員は、「春版」が無料で読めます(期間限定)
Kindle Unlimited会員は、「春夏秋冬+新年」の全てが無料で読めます

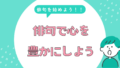

コメント