前回、『季語』の詳しい説明をしました。
ここでは、季語を俳句で使うときに生じる『季重なり』について解説します。
難しそうな言葉に聞こえますが、簡単に言うと、一つの俳句の中に季語を複数入れて作ること。
普通は、一つの俳句の中には一つの季語が良いとされますが、俳句作品の中には「季重なり」のものが多くあります。
ここでは「季重なり」の簡単な知識だけでなく、もう少し踏み込んで「問題のある季重なり」「問題のない季重なり」「季重なりの是非」などについても解説していきたいと思います。
「季重なり」の読み方
俳句で見られる「季重なり」という言葉ですが、読み方は「きかさなり」です。
濁音をつけて「きがさなり」と読んでも大丈夫です。
季重なりとは
一つの俳句の中に季語が2つ以上あることを「季重なり」と言います。
中には季語が3つある俳句や、4つある俳句もありますが、そのような俳句は稀です。
俳句は17音しかないので、普通に作っていて季語が3つや4つも入ることは少ないでしょう。
季重なりの問題点
季重なりが避けられる主な理由は、句の主題がぼやけたり、言葉が重複したりするからです。
- 主題がぼやける
俳句はたった17音の中に、作者の感動や情景を凝縮させます。
季語は、その中心となる季節感やテーマを伝える重要な役割を果たします。
季語が複数あると、読み手は「どの季節を詠んでいるのだろう?」と混乱し、伝えたい主題がぼやけてしまうことがあります。 - 言葉の無駄遣い
限られた文字数の中で、同じ季節を表す季語を複数入れるのは「言葉の無駄遣い」と見なされることがあります。
季重なりの失敗例
夏暑し 汗かきながら 氷菓食ふ
この句には、「夏」「暑し」「汗」「氷菓」と夏の季語が4つ含まれています。
「氷菓(アイスクリームなど)」という季語だけで、夏であることや、暑くて汗をかいていることが想像できます。
この場合、他の季語は重複しており、なくても意味が通じます。
このように、複数の季語が単なる情報の羅列になり、一句に込められた作者の意図が伝わりにくくなる場合に「季重なりはよくない」と言われます。
季重なりの成功例
一方で、俳句の歴史を振り返ると、多くの名句に季重なりが見られます。特に、以下のような場合には、季重なりが効果的に作用し、句の魅力を高めています。
同じ季節の季語が重なる俳句
複数の季語を並べることで、その季節の豊かな情景をより鮮明に描き出すことができます。
朝顔の映り熱帯魚は沈む 高浜虚子
「朝顔」と「熱帯魚」が夏の季語です
稲刈りの進めば進む蝗かな 鷹羽狩行
「稲刈り」と「蝗」が秋の季語です
鮟鱇の骨まで凍ててぶちきらる 加藤楸邨
「鮟鱇」と「凍てて」が冬の季語です
これらの句は、どちらも同じ季節の季語を使っていますが、重複しているというよりは、それぞれの季語が異なるイメージを喚起し、句全体に奥行きを与えています。
異なる季節の季語が重なる俳句
異なる季節の季語を組み合わせることで、時間の流れや対比、あるいは作者の心象風景を表現することができます。
菜の花や月は東に日は西に 与謝蕪村
「菜の花」が春、「月」が秋の季語です
運動会の旗あちこちす春の山 正岡子規
「運動会」が秋、「春の山」が春の季語です
とんぼうの腹の黄光り大暑かな 室生犀星
「とんぼう」が秋、「大暑」が夏の季語です
蕪村の句は、春の「菜の花」と秋の「月」が同居することで、非日常的な美しさを生み出しています。芭蕉の句は、春の季語「蛤」が過去の別れを象徴し、「秋」が現在の寂しさを表現しています。
このように、季語同士が響き合い、一句の中でより深い意味を持つ場合、季重なりは問題になりません。
「四季を語る季語」─電子書籍─
豊富な季語が収録されていて、全ての季語に丁寧な解説が書かれている電子書籍。
アマゾンプライム会員は、「春版」が無料で読めます(期間限定)
Kindle Unlimited会員は、「春夏秋冬+新年」の全てが無料で読めます
著名俳人の季重なりへの考え
俳聖と呼ばれる松尾芭蕉も、生涯に作った句の約15%が季重なりだったと言われています。
蕪村も季重なりの句を多く作っています。蕪村の句を鑑賞してみると、季重なりを避けようと言う意識は感じられず、むしろ両者のかもし出す詩的情緒を楽しんでいるようにも思えます。おそらく、俳句の創造性の一つとして積極的に取り入れようとしていたのではないでしょうか。
子規は歳時記に囚われず、実際の季節を大切にしなさいと言っていましたし、高浜虚子などの近代俳句の礎を築いた人々も、季重なりを避けることにこだわってはいませんでした。
飯田龍太は「自然の方が季重なりであるのだから、句が季重なりになるのは当たり前だ」と述べています。
このことから、季重なりは俳句の絶対的なタブーではなく、むしろ表現の可能性を広げるテクニックの一つとして捉えられていたことがわかります。
季重なりの名句
先輩方の季重なり句を鑑賞してみましょう
一家に遊女もねたり萩と月 松尾芭蕉
目には青葉山ほととぎす初がつを 山口素堂
四五人に月落ちかかるをどりかな 与謝蕪村
梅雨ながら且つ夏至ながら暮れてゆく 相生垣瓜人
蝶の舌ゼンマイに似る暑さかな 芥川龍之介
みじか夜や毛むしの上の露の玉 与謝蕪村
ゆく春や逡巡として遅ざくら 与謝蕪村
どれも、味わいのある作品ではないでしょうか。
もし重なっている季語を捨てて一つにしてしまったら、それぞれの作品の味わいは薄れてしまうのではないでしょうか。
大切なのは季重なりの「成功」と「失敗」
季重なりというだけで、その句の良し悪しを判断することはできません。
大切なのは、「言葉の重複」になっていないか、そして「複数の季語が互いに高め合い、新しい世界を生み出しているか」です。
季重なりを避けることは、俳句の基本として押さえておくべき大切なルールです。しかし、そのルールを理解した上で、あえて季語を重ねることで生まれる表現の面白さや奥深さもあります。
季重なりを恐れず、さまざまな句作に挑戦してみることで、あなた自身の俳句の世界を広げることができるでしょう。
俳句の疑問に関する記事
- 俳句の『漢字』の疑問
- 俳句の『切れ字』とは
- 俳句の『取り合わせ』とは
- 俳句の『句切れ』とは
- 俳句の『自由律俳句』とは
- 俳句の『有季定型』とは
- 昔の俳句で見られる「く」「ぐ」とは
- 昔の俳句で見られる「ゝ」「ゞ」「ヽ」「ヾ」とは
- 「俳句結社」の内容から探し方まで
- 俳句の『季重なり』とは
- 俳句の『季語』とは
- 俳句の『字余り・字足らず』とは
- 俳句の『吟行』とは
- 「俳句・川柳・短歌」の違い
「四季を語る季語」─電子書籍─
豊富な季語が収録されていて、全ての季語に丁寧な解説が書かれている電子書籍。
アマゾンプライム会員は、「春版」が無料で読めます(期間限定)
Kindle Unlimited会員は、「春夏秋冬+新年」の全てが無料で読めます
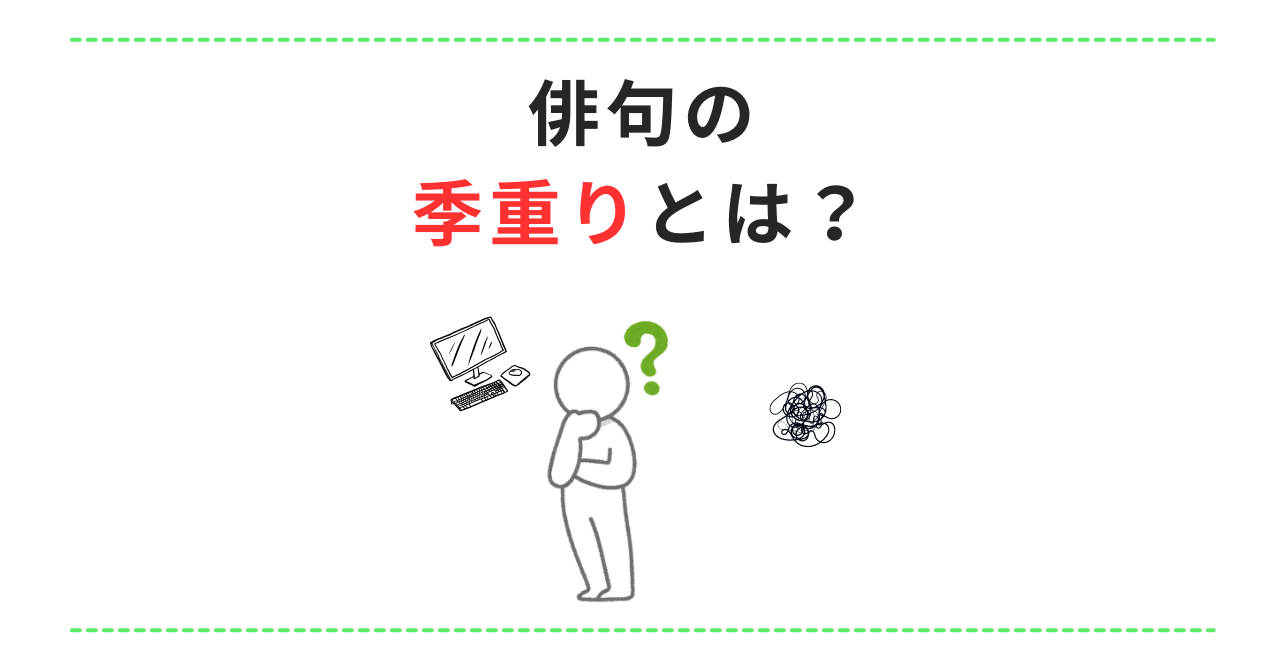

コメント