俳句や短歌を読んでいると、同じ「来ぬ」という表記なのに、読み方によって意味が違うことに気づきます。
「来(こ)ぬ」と「来(き)ぬ」は、一見同じに見えますが、それぞれ異なる意味を持つ古語です。この違いを知ることで、作品の情景をより深く読み取ることができます。
「来(こ)ぬ」
「来ぬ」の意味
「来(こ)ぬ」は、まだ来ていない状態を表します。現代語の「来ない」と同じ意味です。
これは、「来る」という動詞の未然形「来(こ)」に、打消しの助動詞「ず」の連体形「ぬ」が接続してできた形です。
- 構造: 「来(こ)(未然形)」+「ぬ(打消しの「ず」の連体形)」
- 意味: 来ない
- 使い方:
- 名詞を修飾する:「来ぬ人」のように、直後の名詞を打ち消す形で使われることが多いです。
- 文の終わりで使う:文の結びとして使うときは「手紙が咲かず。」のように、打消しの助動詞「ず」をそのまま使います。
「来ぬ」を使った俳句
| 百日紅この叔父死せば来ぬ家か 大野林火 | 大野林火の句集(Amazon) >> |
| みえていて来ぬ夏鴨の青あたま 澁谷道 | 澁谷道の句集 (Amazon) >> |
| 誰も来ぬ日の山中に茸(たけ)あそぶ 青柳志解樹 | 青柳志解樹の句集(Amazon) >> |
これらの句では、「今後は来ない家」や「見えているのに来ない夏鴨」「誰も来ない」といった、物事がまだ起きていない状況が表現されています。
俳句作品は、『歳時記』という本に多く掲載されています。作品を学びたい方は、ぜひ購入を検討してみてください。
Amazonで歳時記を見る >>
「来(き)ぬ」
「来ぬ」の意味
一方、「来(き)ぬ」は、やってきた完了の状態を表します。現代語の「来た」と同じ意味です。
これは、「来る」の連用形「来(き)」に、完了の助動詞「ぬ」が接続してできた形です。
- 構造: 「来(き)(連用形)」+「ぬ(完了)」
- 意味: 来た
- 使い方:
- 主に文の結びで使われます。「春が来ぬ。」のように、ある出来事が起こったことを強調します。
「来ぬ」を使った俳句
| ジーンズの尻美しき五月来ぬ 野田哲夫 | 野田哲夫の句集 (Amazon) >> |
| プラタナス夜もみどりなる夏は来ぬ 石田波郷 | 石田波郷の句集 (Amazon) >> |
これらの句では、「五月が来た」ことや「夏が来た」ことが表現されており、季節の到来に対する作者の感動が伝わってきます。
俳句作品は、『歳時記』という本に多く掲載されています。作品を学びたい方は、ぜひ購入を検討してみてください。
Amazonで歳時記を見る >>
まとめと注意点
「来(こ)ぬ」と「来(き)ぬ」は、振り仮名がないと区別がつきません。そのため、前後の文脈からどちらの意味で使われているかを判断する必要があります。
- 来(こ)ぬ → 来ない(打消し)
「来ぬ鳥」「来ぬ夏」というように名詞につながる場合は「来(こ)ぬ」 - 来(き)ぬ → 来た(完了)
「鳥が来ぬ」「夏が来ぬ」というように、文が終わる場合は「来(き)ぬ」
もし、作者が読み間違いを防ぎたいと考えるなら、「こぬ」「きぬ」のように平仮名で表記することも一つの方法です。実際にそのようにしている俳句もあります。
- ついに落ちてこぬ石を待つ神無月 塩野谷仁
- 夜の更けて盛り上りきぬ盆踊り 八木澄子
読み方が「こ」か「き」の違いで、俳句は全く逆の意味になります。作品を鑑賞する際やご自身で俳句を作る際に意識してみてください。
関連記事
この記事で言葉の違いを学んだように、俳句には他にも似て非なる言葉が数多くあります。
あなたの句をさらに磨き上げるために、他の言葉の使い分けをぜひチェックしてみてください。
- 俳句における「ある・おる・いる」の使い分け
- 俳句における「とき」「時」の使い分けから、「時間」の言葉まで
- 俳句における「上る・上がる・上げる」の使い分け
- 俳句における「出る・出来る」の使い方
- 俳句における「初」「始」の使い分け
- 俳句における「去ぬ」「去る」について
- 俳句における「合う・会う・逢う・遭う」の使い分け
- 俳句における「変わる・変える」の使い分け
- 俳句における「川・河・江」の使い分け
- 俳句における「影・陰・蔭・翳」の使い分け
- 俳句における「日・陽」の使い分け
- 俳句における「暖かい・温かい」の使い分け
- 俳句における「氷る・凍る」の使い分け
- 俳句における「答える・応える」の使い分け
- 俳句における「聞く・聴く・訊く」の使い分け
- 俳句にみる「咲かぬ」「咲きぬ」の違い
- 俳句にみる「来ぬ(こぬ)」と「来ぬ(きぬ)」の違い
間違えやすい言葉について書かれた本
俳句の奥深さは、言葉のわずかな違いが表現を大きく変える点にありますよね。
そんな言葉の探求を助けてくれる本が、『同じ読みで意味の違う言葉の辞典』です。
一冊手元にあるだけで、より豊かな俳句創りができるはずです。
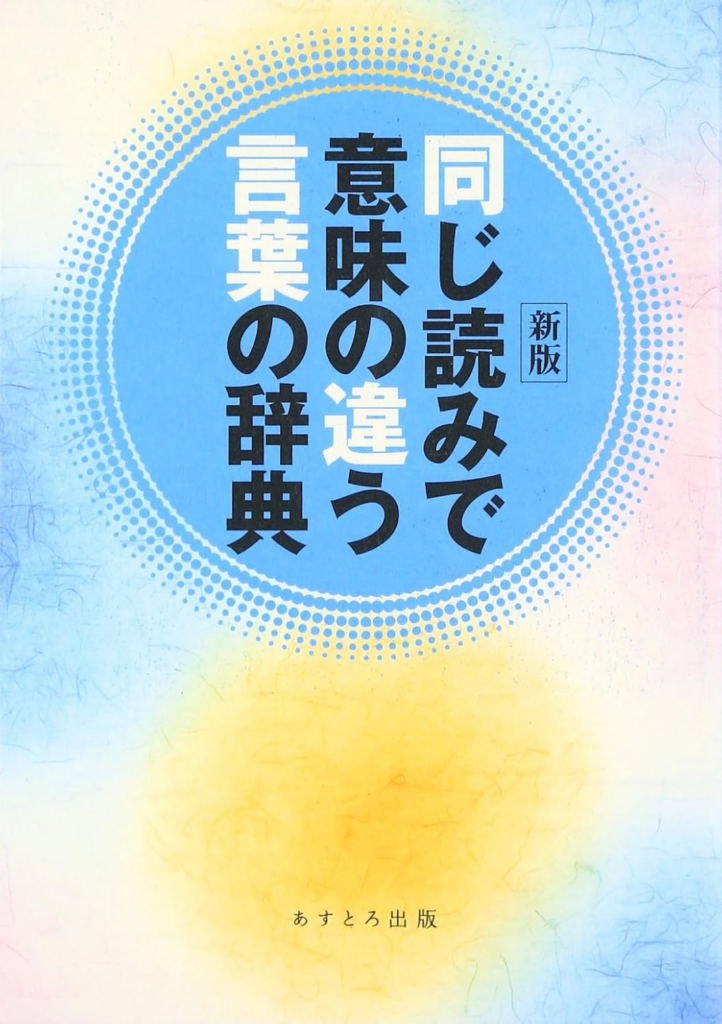



コメント