 俳句を作る
俳句を作る 俳句では「はっ」とした特徴を詠もう
季語の普通の出来事と、季語を見て「はっ」とした特徴を合わせると俳句になる 朝顔が咲く (季語の普通の出来事) 朝顔の一輪だけ深い淵の色 (季語を見て「はっ」とした特徴) ↓ 朝顔や一輪深き淵の色 与謝蕪村 朝顔が咲...
 俳句を作る
俳句を作る  俳句を作る
俳句を作る 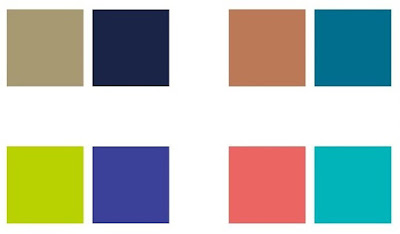 俳句を作る
俳句を作る  俳句を作る
俳句を作る  俳句を作る
俳句を作る  俳句を作る
俳句を作る  俳句を作る
俳句を作る  俳句を作る
俳句を作る  俳句を作る
俳句を作る  俳句を作る
俳句を作る