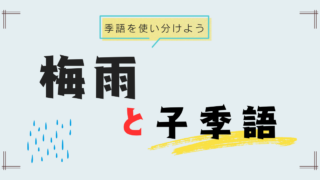 季語と子季語のそれぞれの意味
季語と子季語のそれぞれの意味 「梅雨」と子季語の意味
歳時記で『梅雨』を調べていると、『梅霖』や『黴雨』といった、少し聞き慣れない言葉が出てくることがあります。これらの季語は、梅雨を表す別の言葉です。梅雨を表すいろいろな季語をしたの表にまとめています。初めて目にする言葉でも、表を参考に、俳句作...
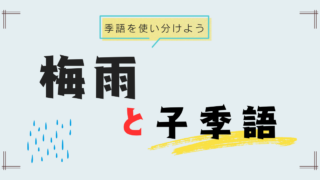 季語と子季語のそれぞれの意味
季語と子季語のそれぞれの意味  俳句を作る
俳句を作る 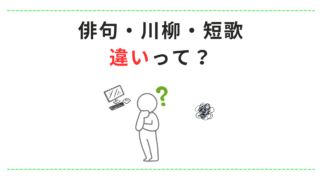 俳句の疑問
俳句の疑問  俳句を作る
俳句を作る  俳句の疑問(作り方)
俳句の疑問(作り方)  良い俳句
良い俳句  俳句を作る
俳句を作る 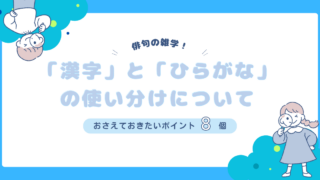 俳句の疑問(作り方)
俳句の疑問(作り方)  俳句を作る
俳句を作る  俳句の疑問(作り方)
俳句の疑問(作り方)