 季語のいろいろ
季語のいろいろ 俳句の季語「たかみそぎ」って何?
俳句の季語を調べていると、普段あまり耳にしない言葉に出会うことがあります。今回は、そんな季語の中から、ちょっと珍しい「たかみそぎ」について一緒に探求してみましょう。「たかみそぎ」の正体を探る 「たかみそぎ」は、夏の季語である「名越の祓(なご...
 季語のいろいろ
季語のいろいろ  季語の世界
季語の世界  季語のいろいろ
季語のいろいろ  文語文法
文語文法 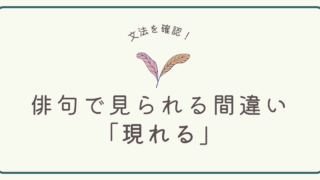 文語文法
文語文法 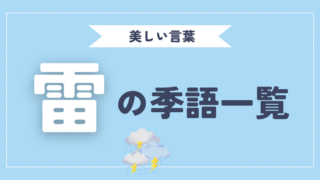 四季で見られる季語
四季で見られる季語 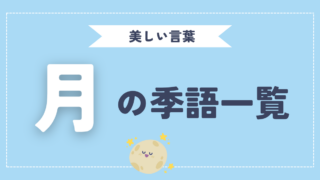 四季で見られる季語
四季で見られる季語 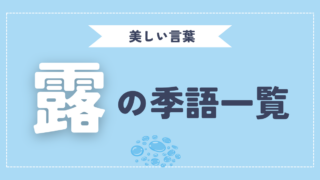 四季で見られる季語
四季で見られる季語 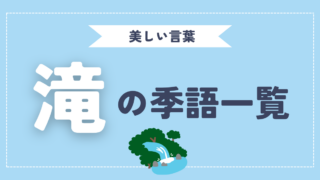 四季で見られる季語
四季で見られる季語 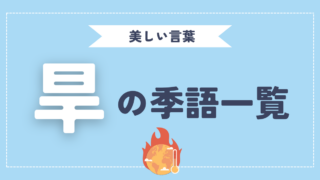 四季で見られる季語
四季で見られる季語