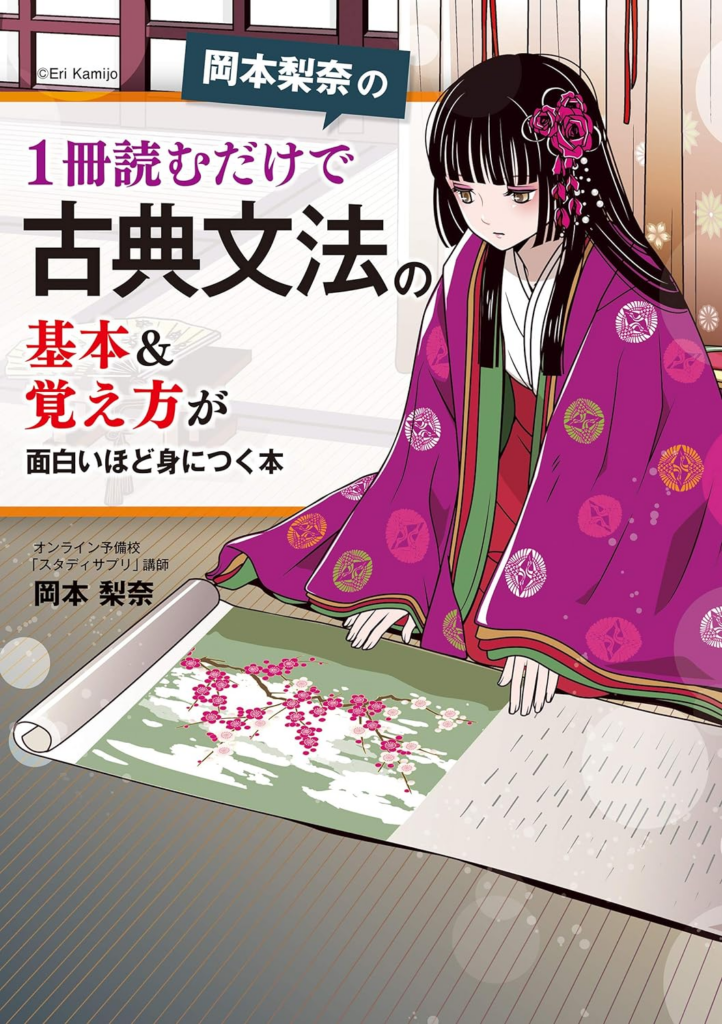電子辞書で、俳句作りに役立つ様々な本を刊行しています。
24,000語以上の季語を集めた本、季語を音数ごとに分けた本など、俳句創作のヒントになるような本となっています。
俳句作りをされている方はもちろん、これから始めたい方も、ぜひ一度手にとってみてください。
四季を語る季語(季語辞典)
四季を語る季語「秋」 : 5,600季語収録
四季を語る季語「冬」 : 4,300季語収録
四季を語る季語「新年」 : 2,400季語収録
四季を語る季語「春」 : 5,100季語収録
四季を語る季語「夏」 : 6,800季語収録
基本季語から関連季語まで24,000語以上が収録されています。
すべての季語には解説が書かれているため、俳句の初心者はもちろんベテランの方まで十分に活用していただける内容です。
また、純粋に日本の四季の言葉をいろいろ知りたい、という方にも楽しんでいただける内容です。
◎季語が選びやすいような構成
知っておきたい重要な基本季語と、その関連季語が並べて掲載されていますので、関連語を簡単に探すことができます。
基本季語の解説だけでなく、関連季語の解説も書かれていますので、適切な季語を選ぶことができます。
すべての季語を文字検索できますので、検索が簡単です。
文字検索では、特定の文字を含む季語を検索することもできるので、完全な単語を思い出せなくても、希望の季語を探すことができます。
◎口語・文語、新仮名・旧仮名を正しく使えるような構成
季語の中には口語と文語で表記の違うものがあります。正しい表記で使えるように、文語の解説には公ごとの表記の違いを書いています。
季語の中には新仮名と旧仮名で表記の違うものがあります。表記の違うものは新仮名・旧仮名の2つの読み仮名を記載してますので、正しく仮名を使うことができます。
◎キンドルでの使い方
音数からの「季語」検索本

音数からの「季語」検索本
Amazonで販売中 >>>
12,500語の季語を音数順に並べた決定版!
3音の季語、4音の季語、5音の季語など、簡単に探すことができます
3音の季語+「けり」を最後に使いたい
4音の季語+「や」を最初に使いたい
5音の季語で名詞止をしたい
「あぁ、2音の季語があれば俳句が完成するのに」など・・・
こんなときに、役に立つ本です
季語が音数ごとに並んでいることで、何も考えずに求める音数の季語にたどりつけます
俳句の音数がうまくまとまらない、という人にも結果を出せる1冊です
小さな花(句集)

Amazonで販売中 >>>
加藤楸邨、中嶋秀子の流れを汲み生まれた句会「小さな花」
18年続いた句会の中で生まれた俳句360句を収録しています
─1人自薦45句、合計360句─
季節ごとに丁寧にそれぞれの作者らしい言葉とリズムで鮮やかに表現され、その人柄も感じられるはずです。
収録されている8つのタイトル
「梅びより」「蚊遣火」「花万朶」「すずろ歩き」「淡雪」「雪化粧」「春の星」「遍路道」
これらのタイトルから一体どのような作品が生まれるのか、ぜひ本を手に取って確かめてみてください。
【収録俳句より】
明日ひらく辛夷は力ゆるめたる
道化師の顔に散りゆく桜かな
やはらかき大和ことばや梅ふふむ
石鹸玉生まれてすぐに出会ふ風
一人居の雛を飾りて時たぐる
山茶花の散りて根元を優しくす
朱の上皆が主役のひな祭り
雲までも赤く染めゆくななかまど
すずろ歩き(句集)

Amazonで販売中 >>>
俳句大会・新聞俳壇などに5年間で190回大会以上に入選
入選句11作品のほかに、新作34作品を含めた句集
日本の四季の自然を詠み、ときには自然に心情を重ねながら一文字一文字ていねいに作っています
ルビ・解説がついているので、俳句に慣れていない方にも気軽にお読みいただける本になっています。
【収録俳句より】
大空に岐路のありしや燕の子
(おおぞらにきろのありしやつばめのこ)
一音の色を咲かせるヒヤシンス
(いちおんのいろをさかせるひやしんす)
石鹸玉生まれてすぐに出会ふ風
(しゃぼんだまうまれてすぐにであうかぜ)
1週間でマスター!俳人のための旧仮名・文語入門【PDFファイル】
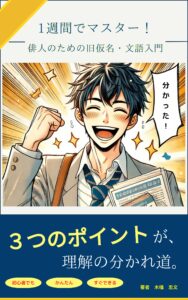
BASEで販売中 >>>
「旧仮名?文法?難しそう…」と、尻込みしていませんか?
この本は、俳句・短歌初心者で、文語や文法に苦手意識があるあなたでも、たった1週間で旧仮名・文語を使いこなせるようになるための、超実践的なガイドです。
無料で本書を読む方法
紹介した本は全て、KindleUnlimited会員であれば無料で読むことができます。
会員でない方は、30日のお試し期間に登録すると読むことができます。
もし気に入らなければ、30日以内に解約をすればお金はかかりませんので、登録してみてください。
登録ページはこちらです >>>
俳句では「紅葉」は秋の季語になっています
紅葉に関連する季語は沢山あり、歳時記を見ても、意味の分からないものも中にはあるため、ここでは紅葉に関連する季語を、意味と共にまとめています
俳句を作る際の参考になさってください
(仲秋の季語の)紅葉
初紅葉(はつもみじ)
いち早く紅葉し山野に秋の訪れを告げるものをいう。櫨、七竈、ぬるでなどがある。紅葉で最も有名な楓は、これより遅く紅葉する。
薄紅葉(うすもみじ)
緑の残る淡い色の紅葉をいう。紅葉の走りではあるが、深い紅の紅葉とは違った趣を持つ。
桜紅葉(さくらもみじ)
桜の葉が色づくこと。桜は、比較的早く色づく木である。あざやかな朱色にならないのであまり注目されることがないが、素朴な味わいがある。
(晩秋の季語の)紅葉
紅葉(もみじ)
落葉樹の葉が赤や黄色に色づき、野山の秋を飾ること
紅葉といえば主に楓のことをいう
紅葉を愛でる習慣は平安の頃から始まったとされる
もみぢ葉(もみじば)、色葉(いろは)
赤や黄色に変わった、落葉木の葉っぱ
「もみぢ葉」は旧仮名表記、「もみじ葉」は新仮名表記。俳句では旧仮名を使っている人は、間違わないように注意しましょう
紅葉の錦(もみじのにしき)
紅葉の美しさを錦に見立てていう語
谷紅葉(たにもみじ)
紅葉で色どられた谷をいう
川紅葉(かわもみじ)
紅葉で色どられた川
山紅葉(やまもみじ)
紅葉で色どられた山
梢の錦(こずえにしき)
紅葉のことで、枝の美しさを錦に見立てたもの
草紅葉(くさもみじ)、草の紅葉(くさのもみじ)、草の錦(くさのにしき)
山野の草々が色づいくこと
古くは草の錦とも呼んだ
草の色(くさのいろ)、色づく草(いろづくくさ)
秋になり色づいた草をいう
「草の色」ではなく「色草」と書くと、秋の野や庭園を彩るいろいろな草を総称した言葉となるので、間違わないでください
柿紅葉(かきもみじ)
柿の葉が紅葉すること
柿の葉の本来の緑に赤や黄や茶などさまざまな色が入り混じって美しい
紅葉の賀(もみじのが)
紅葉の美しい頃に催す祝宴、または紅葉を観賞する宴をいう
奈良時代に始まったとされ、「源氏物語」には当時の華やかな宴の様子が描かれている
柞紅葉(ははそもみじ)
ブナ科コナラ属の落葉高木の紅葉を総称していう
高さ十五~二十メートル程の雑木で、小楢、くぬぎ、大楢などを指す
楢紅葉(ならもみじ)
楢の葉の紅葉したもの
漆紅葉(うるしもみじ)
漆が紅葉すること
最初は黄色く、しだいに美しい朱色に色づく
山漆は特に美しい
櫟紅葉(くぬぎもみじ)
櫟の葉が色づくこと
櫟は山地の雑木林などに自生する落葉高木で、葉は黄褐色に色づく
その実は団栗として親しまれる
白膠木紅葉(ぬるでもみじ)
ぬるでの木が色づくこと
いくらか黄味がかった朱色の葉はあざやかで美しく、紅葉山の中においても鮮やかである
櫨紅葉(はぜもみじ)
櫨の木が紅葉すること
実も葉も真紅に色づく
山野に自生するが、その紅葉の美しさから、庭木や花材にも好まれる
梅紅葉(うめもみじ)
梅の葉が色づくこと
色づいてもほとんど目立たず、すぐに散ってしまう
葡萄紅葉(ぶどうもみじ)
葡萄の葉が紅葉すること
いくらかくすんだ感じに色つくが、広大な葡萄畑のそれは壮観である
山葡萄の紅葉は栽培種よりも鮮やかで美しい
雑木紅葉(ぞうきもみじ)
雑木林が紅葉したものを言う
楢、ぶな、くぬぎ、楓といったさまざまな木々の色合いが重なり合う
満天星紅葉(どうだんもみじ)
満天星躑躅の葉が紅葉すること
生垣や公園など身近なところで目にする紅葉
合歓紅葉(ねむもみじ)
合歓の木が色づくこと
黄色く色づいても過ぐに落葉する
銀杏や楓のような鮮やかさはない
紅葉かつ散る(もみじかつちる)、色ながら散る(いろながらちる)
紅葉しながら、ちりゆく紅葉のこと
水草紅葉(みずくさもみじ)、萍紅葉(うきくさもみじ)
萍(うきくさ)、睡蓮、菱(ひし)など水草が紅葉すること
水面に映える紅葉は、地上の紅葉とはまた違った趣を持つ
紅葉の観賞に関する季語
紅葉狩(もみじがり)、紅葉見(もみじみ)
紅葉を観賞するため、山野などを訪ねる歩くこと
紅葉をめでながら酒を酌み交わすこともある
晴れた日に家族そろって眺める紅葉は格別
観楓(かんぷう)
もみじを観賞すること
紅葉踏む(もみじふむ)
おちた紅葉をふんで歩くこと
紅葉酒(もみじざけ)
紅葉の葉を浮かべた酒
紅葉茶屋(もみじじゃや)
紅葉見の客のために設けられた休み茶
紅葉舟(もみじぶね)
川や湖上に舟を浮かべて、岸の紅葉をたのしむ遊山舟
(冬の季語の)紅葉
散紅葉(ちりもみじ)、色葉散る(いろはちる)
冬の訪れとともに紅葉が色褪せ、しだいに散っていくこと
水分が少なくなり軽くなった葉は、軽々と風に飛ばされる
冬紅葉(ふゆもみじ)
周辺が枯れを深めるなかの紅葉
冬になってから色 が際立ってくる庭園や寺社などの紅葉もある
残る紅葉(のこるもみじ)
冬になって枝に残っている紅葉
「紅葉」の言葉が入った季語
紅葉鮒(もみじぶな)
秋になって鰭や鱗に朱をおびた鮒をいう
おもに琵琶湖で獲れる鮒をいい、鮒鮓もこの頃の味のよい鮒を用いる
紅葉たなご(もみじたなご)
秋になって腹部を紅葉色にそめたたなごをいう
紅葉鮒にならってこう呼ばれる
紅葉衣(もみじごろも)
もみじ襲の色目一つ
表は紅または赤、裏は濃蘇芳又は青、又は濃い赤
陰暦九月九日より着用したとされる
秋の季語になっている
紅葉焚く(もみじたく)
散った紅葉を集めて焚くこと
晩秋の季語
紅葉鍋(もみじなべ)
鹿の肉を用いた鍋のことで冬の季語
血行が良くなり体が温まる
「もみじ」は鹿の肉の隠語で、花札の十月の紅葉の意匠から来たもの
紅葉の有名な俳句
紅葉の有名な俳句はいろいろありますが、個人的に好きなものは次の2つです
障子しめて四方の紅葉を感じをり 星野立子
全山のもみぢ促す滝の音 山内遊糸
紅葉は季語としても有名なため、多くの俳句がありますが、この2つはその中でも特に際立って良い俳句だと感じます
四季でみられる季語の関連記事
- 「蟷螂」の季節ごとの季語
- 「蝶」の季節ごとの季語
- 「雲雀」の季節ごとの季語
- 「夕立」の季節ごとの季語
- 「菊」の季節ごとの季語
- 「夕焼け」の季節ごとの季語
- 「牡丹」の季節ごとの季語
- 「椿」の季節ごとの季語
- 「蛙」の季節ごとの季語
- 「雪」の季節ごとの季語
- 「紅葉」の季節ごとの季語
- 「梅」の季節ごとの季語
- 「桜」の季節ごとの季語
- 「天の川」の季節ごとの季語
- 「朝顔」の季節ごとの季語
- 「百合」の季節ごとの季語
- 「鴨」の季節ごとの季語
- 「燕」の季節ごとの季語
- 「薔薇」の季節ごとの季語
- 「旱」の季節ごとの季語
- 「滝」の季節ごとの季語
- 「露」の季節ごとの季語
- 「月」の季節ごとの季語
- 「雷」の季節ごとの季語
俳句を詠むとき、「拗音」「促音」「長音」ってどう数えるの?と悩んだことはありませんか?
これらを正しく理解することで、あなたの俳句はぐっと深みを増します
この記事では、「拗音・促音・長音」の読み方、音数の数え方、俳句での表記方法などをわかりやすく解説します
記事を読んで、俳句の世界をもっと深く探求しましょう!
拗音・促音・長音の読み方
「拗音・促音・長音」は、それぞれ次のように読みます
拗音(ようおん)
促音(そくおん)
長音(ちょうおん)
拗音・促音・長音とは
| 拗音 | 「きゃ・きゅ・きょ」などのように、他の言葉の横に記す小さな「ゃ・ゅ・ょ」のこと |
| 促音 | 「かっ・きっ・くっ」などのように、他の言葉の横に記す小さな「っ」のこと |
| 長音 | 「かー・きー・くー」などのように、言葉の横に記す横棒「ー」のこと |
拗音・促音・長音の数え方
拗音の「きゃ」「きゅ」「きょ」などは、俳句では1音として数えます
つまり、小文字の「ゃ・ゅ・ょ」は音数に数えません
促音の「かっ」「きっ」「くっ」などは、俳句では2音として数えます
つまり、小文字の「っ」は1音として数えます
長音の「かー」「きー」「くー」などは、俳句では2音として数えます
つまり、横棒の「ー」は1音として数えます
表にすると次のようになります
| 拗音 | 「きゃ」「きゅ」「きょ」 | ←1音で数える |
| 促音 | 「かっ」「きっ」「くっ」 | ←2音で数える |
| 長音 | 「かー」「きー」「くー」 | ←2音で数える |
俳句での拗音・促音の書き方
俳句では拗音・促音を書くとき、カタカナは小文字で、平仮名は大文字で表記することが多く見られます
次のような感じですね
| カタカナの拗音は小文字 | キャンドル |
| カタカナの促音は小文字 | キットカット |
| 平仮名の拗音は大文字 | きようかしよ(教科書) |
| 平仮名の促音は大文字 | りつか(立夏) |
平仮名で拗音・促音を書くとき、大文字で書かなければいけないというルールはありませんが、多くの俳人が大文字で書いているため、みなそれに倣って大文字で書いています
わたしは、大文字表記だと読者が見ずらいので(わたし自身も見ずらいので)小文字で表記しています
拗音・促音のカタカナは小文字で、平仮名は大文字表記の理由はなぜ?
拗音(ゃ・ゅ・ょ)・促音(っ)などは、室町時代末期から発音としてはありましたが、「小文字」での表記方法がなかったため、大文字で「や・ゆ・よ・つ」と書いていました
このころは、どのように拗音・促音を表記すればよいのか試行錯誤していた段階でした
鎌倉時代に入ると、拗音・促音を小文字で表記する方法が少しずつ見られるようになってきました
昭和初期に、昔の仮名遣いが新しい仮名遣いに変わったのですが、このとき、外来語や地名などはカタカナで書きましょう。そして、発音を間違わないように、なるべく拗音・促音は小文字で表記しましょう、というルールのようなものができました
このルールと一緒に、平仮名の拗音・促音も小文字で表記できればよかったのですが、公文書の中には大文字で書かれている拗音・促音があったため、すぐにはできませんでした
古い法律文章は大文字、新しい法律文章は小文字、というように、大文字と小文字が混ざってしまうからです
結局、ひらがなの拗音・促音を小文字で書くことができるようになったのは、平成に入ってからです
このような経緯が、どういうわけか、昔のカタカナは拗音・促音を小文字で書いていて、平仮名は大文字で書いていた、という話となり、いまでも俳句を作るときは、カタカナの拗音・促音は小文字でよいけれど、平仮名の拗音・促音は大文字で書かなければいけない、という話になっています
拗音・促音を大文字で書くと、音数はどうなるの?
「きょうかしょ(教科書)」の拗音を大文字で「きようかしよ(教科書)」と書いても、音数は4音です。6音ではありません
発音した時の音数で数えます
大文字表記の拗音・促音を読むコツ
読者の立場からすると、拗音・促音が大文字で書かれがていると読みずらいものです
「きようかしよ(教科書)」「ちようちん(提灯)」「きやくま(客間)」
どれも読みずらいですね
俳句の中で「や・ゆ・よ」が出てきて、「あれ?これはどうやって読むんだ」と思ったら
それは小文字の「ゃ・ゅ・ょ」の可能性があります
「ゃ・ゅ・ょ」が使われるとき、「ゃ・ゅ・ょ」の前に付く文字は全て、母音が「イ」です
(きゃ、きゅ、きょ、しゃ、しゅ、しょ、ちゃ、ちゅ、ちょ・・・など、どれも母音が「イ」ですよね)
母音が「イ」の文字の後に「や・ゆ・よ」が続く場合、「ゃ・ゅ・ょ」かもしれない、と覚えておきましょう
「っ」は「ん」以外には全て付き付きます
拗音・促音を使った俳句
あたたかや木のおもちゃ屋に一人いて 石橋芙美
あちこちにひとりぽっちが盆供養 髙橋悦子
拗音・促音を使った俳句には、このようなものがあります
ちなみに、拗音・促音を大文字で書くと、次のようになります
あたたかや木のおもちや屋に一人いて
石橋芙美あちこちにひとりぽつちが盆供養 髙橋悦子
拗音・促音は大文字で表記するべき?
拗音や促音を大文字で書くべきか小文字で書くべきか、一度は考えたことがあるかもしれません
私自身は、拗音や促音を小文字で表記しています。小文字で書いても大文字で書いても、単語の意味が変わることはないためです
また、何よりも、読み手にとって読みにくい表記をあえて選ぶ必要があるのか、私には分からないからです
こちらの記事も読まれています
旧仮名の「わゐうゑを」についての記事 >>>
俳句の音数の数え方はこちらで記事にしています >>>
俳句作りにお勧めの本
俳句作りで文法の基礎を勉強するのに、おすすめの本です
基礎をしっかりと学べるので、間違った言葉の使い方がなくなりますし
表現したい言葉を、古語に直して使えるようになります