季語の中には、歳時記には掲載されているものの、意味が不明確な子季語も多く存在します。この記事では、より良い季語が選べるように、今回はよく使われる主季語と子季語のそれぞれの意味を解説しています。
「蛍」の季語
下の表では、一番上の「蛍」が主季語、その下に並んでいるものが子季語になります。
子季語は、主季語の関連語、という考えで大丈夫です。
《 晩夏 》
| 蛍【ほたる】 | 甲虫目ホタル科の昆虫の総称。ゲンジボタル・ヘイケボタル・ヒメボタルなど。一般に体は楕円形で軟弱、全体に黒色で胸の部分が赤い。腹部に発光器をもち、暗い所では青白い光を放つことで知られる。 |
| 初蛍(はつぼたる) | その年初めて見られる蛍。 |
| 蛍火(ほたるび) | 蛍の出す光。また、そのようなわずかに残った火。 |
| 源氏蛍 (げんじぼたる) | ほたるの一種で、大形のもの。体長約一五ミリ。成虫ばかりでなく、さなぎも幼虫も卵も光る。幼虫は清流に住み、巻貝を食べる。 |
| 夕蛍 (ゆうぼたる) | 夕方から光だす蛍。 |
| 蛍合戦 (ほたるがっせん) | 交尾のために多くの蛍が入り乱れて飛ぶこと。 |
蛍
「蛍」「初蛍」「蛍火」「蛍合戦」といった蛍にまつわる季語は、それぞれが持つニュアンスが異なります。
「初蛍」は、一年で初めて目にする蛍を指し、そのときの感動や驚きを表現したい際に用いられます。単に「蛍」と書くよりも、作者の心の動きをより鮮やかに描き出すことができます。
「蛍火」は、蛍の一つの光に焦点を当て、その儚さや美しさを表現したい場合に用いられます。静寂の中で静かに光る蛍の姿が目に浮かびます。
一方、「蛍合戦」は、多くの蛍が乱舞する様子をダイナミックに表現したい場合に用いられます。夏の夜空を彩る幻想的な光景が目に浮かぶでしょう。
このように、それぞれの季語は、表現したい情景や感情によって使い分けられます。俳句を作る際には、詠みたい情景を思い浮かべ、最もふさわしい季語を選ぶことが大切です。
「蛍」関連の俳句
「蛍」を使った俳句にはこのようなものがあります。俳句作りの参考になさってください。
「蛍」の例句
| いよよ増す蛍に別れ惜しみけり 髙畑澄子 | - |
| どの窓も無名の蛍待つてをり 松﨑麻美 | 松﨑麻美の句集(Amazon) >> |
| ゆるやかに着てひとと逢ふ蛍の夜 桂信子 | 桂信子の句集(Amazon) >> |
| ニトログリセリンの甘さ蛍の夜 髙橋公子 | - |
「初蛍」の例句
| 妻の掌のわれより熱し初螢 古沢太穂 | 古沢太穂の句集(Amazon) >> |
| 水甕の真闇に一灯初蛍 勝部孚萩 | - |
| 誰彼に知らせたくなり初蛍 住田征夫 | - |
| 闇の手のつぎつぎ攫う初蛍 大須賀善和 | - |
「蛍火」の例句
| 蛍火に人集まりて静かなり 漆崎とし子 | - |
| 蛍火に逢いし一夜の不整脈 村田まさる | - |
| 蛍火の奥で扉の開く音 坂本敏子 | - |
| 蛍火や介護の日誌読返す 中山秀子 | 中山秀子の句集(Amazon) >> |
| 蛍火を生む川川を生む地球 木幡忠文 | 木幡忠文の句集(Amazon) >> |
「源氏蛍」の例句
| 摂津峡源氏螢が飛び交はす 奥田妙子 | - |
「夕蛍」の例句
| 夕蛍古墳かかえし山裾に 平野きぬ子 | - |
| 母の手の冷たき記憶夕蛍 長井順子 | - |
「蛍合戦」の例句
| 蛍合戦憂き世の隅を照らしけり 久留米脩二 | 久留米脩二の句集(Amazon) >> |
関連記事
- 「サフラン」と子季語の意味
- 「七夕祭」と子季語の意味
- 「伊勢参」と子季語の意味
- 「川床」と子季語の意味
- 「新酒」と子季語の意味
- 「時鳥」と子季語の意味
- 「木の実」と子季語の意味
- 「梅雨」と子季語の意味
- 「海女」と子季語の意味
- 「清水」と子季語の意味
- 「湯帷子」と子季語の意味
- 「爽やか」と子季語の意味
- 「甘茶」と子季語の意味
- 「皀角子」と子季語の意味
- 「秋」と子季語の意味
- 「簗」と子季語の意味
- 「紫陽花」と子季語の意味
- 「繭」と子季語の意味
- 「胡麻」と子季語の意味
- 「芒」と子季語の意味
- 「芝神明祭」と子季語の意味
- 「苜蓿」と子季語の意味
- 「葭簀」と子季語の意味
- 「蛍」と子季語の意味
- 「霞」と子季語の意味
- 「風光る」と子季語の意味
- 「風薫る」と子季語の意味
- 「鮭」と子季語の意味
- 「鷽」と子季語の意味
- 「鹿」と子季語の意味
- 「麗らか」と子季語の意味
季語探しの強い味方『四季を語る季語』
季語を選ぶ際には、様々な要素を考慮する必要がありますが、従来の歳時記には子季語の意味が詳しく記載されていないため、適切な季語を選ぶのが難しいという課題がありました。
『四季を語る季語』は、全ての子季語の意味を網羅することで、この課題を解決し、よりスムーズな季語選択を可能にします。
↓↓下の本がそうです。
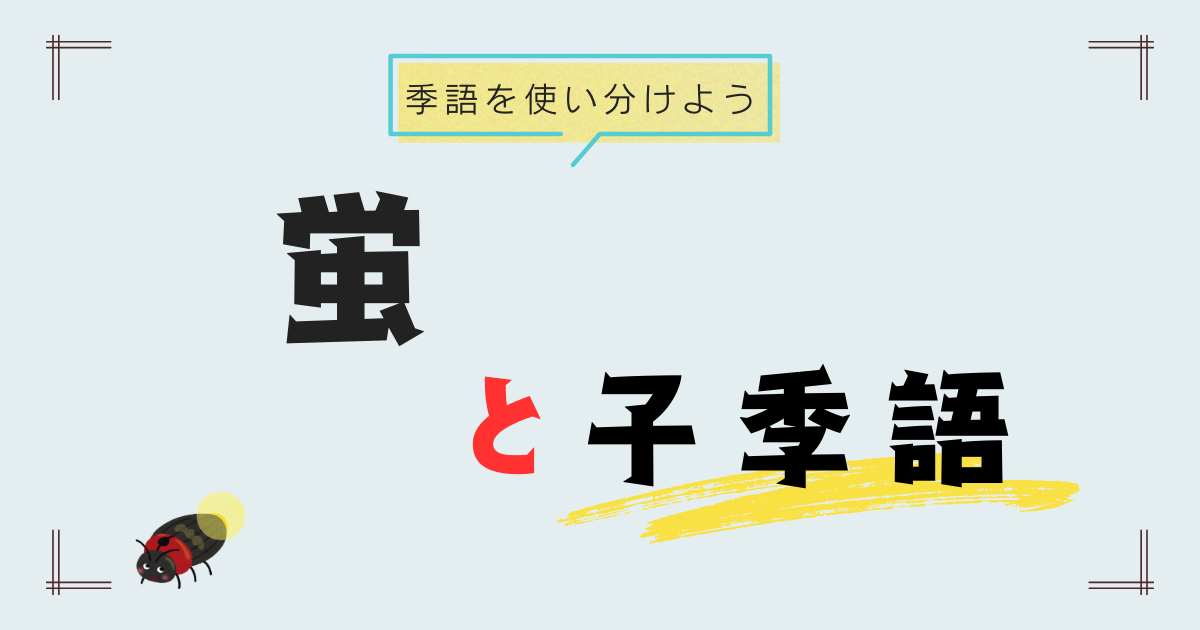


コメント