俳句を詠むためには季語の理解が欠かせませんが、歳時記には主に主季語しか説明されていません。そのため、子季語の意味を知らずに使ってしまうことも。このページでは、子季語もしっかり説明し、初心者の方が自信を持って俳句を詠めるようサポートしています。
「木の実」の季語
下の表では、一番上の「木の実」が主季語、その下に並んでいるものが子季語になります。
子季語は、主季語の関連語、という考えで大丈夫です。
《 晩秋 》
| 木の実【このみ】 | 木になる果実。 |
| 木の実落つ(このみおつ) | 実が木より落ちること。「落つ」は「落ちる」の古語形 |
| 木の実降る(このみふる) | 実が木より降ること。 |
| 木の実雨(このみあめ) | 実が木より落ちることを雨にたとえたさま。 |
| 木の実独楽(このみごま) | 木の実で作ったコマ。 |
「木の実落つ」について
「木の実落つ」という言葉を初めて歳時記で見かけた時、「落つ」とは一体何だろう?と疑問に思う人もいるかもしれません。
「落つ」は「落ちる」の古い言葉、つまり古語です。俳句は古くからの伝統を持つ文学なので、古語が使われることが多く、「木の実落つ」のように表現されています。
現代の言葉で俳句を作る場合は、「木の実落ちる」のように「落ちる」を使っても全く問題ありません。
「木の実雨」について
「木の実雨」とは、木の実が次々と落ちる様子を、まるで雨が降り続くようにたとえた言葉です。木の実が木から離れ、地面に落ちてくる様子を、雨粒が空から落ちてくる様子に重ねて表現しています。そのため、「木の実落つ」や「木の実降る」よりも、より多くの木の実が連続して落ちる様子を強調したいときに使われます。
俳句で「木の実が降る」と表現することはできるのですが、これでは少し説明的で、読者に直接的な情景を伝える力が弱くなってしまいます。代わりに、名詞である「木の実雨」を使うことで、わずか三文字で「木の実が降ってくる音や情景」を鮮やかに描き出すことができます。
季語の一つの選択でも、限られた音数の中に深い情景を凝縮させ、より読者の心に響く句を詠むことができます。
「木の実」関連の俳句
木の実を使った俳句を紹介します。俳句作りの参考になさってください。
「木の実」の例句
| よろこべばしきりに落つる木の実かな 富安風生 | 富安風生の句集(Amazon) >> |
| ポケットのなき子の木の実預かりぬ 平賀節代 | - |
「木の実落つ」の例句
| またひとつ木の実を落とす耳の奥 岡みずき | - |
| 口あけし羅漢のひとり木の実落つ 管邦代 | - |
| 木の実落つ今がどん底土踏ず 松村筐花 | - |
| 木の実落つ居心地の良き所まで 野村洋子 | - |
「木の実降る」の例句
| はじまりし三十路の迷路木の実降る 上田五千石 | 上田五千石の句集(Amazon) >> |
| 坂それて六波羅密寺木の実降る 澁谷道 | 澁谷道の句集(Amazon) >> |
| 天上に人のふえゆき木の実降る 片山淳子 | 片山淳子の句集(Amazon) >> |
「木の実独楽」の例句
| あるときは山の音する木の実独楽 村田まさる | - |
| つくるよりはや愛憎や木の実独楽 橋本多佳子 | 橋本多佳子の句集(Amazon) >> |
| はじめから山へ傾き木の実独楽 山崎聰 | 山崎聰の句集(Amazon) >> |
関連記事
- 「サフラン」と子季語の意味
- 「七夕祭」と子季語の意味
- 「伊勢参」と子季語の意味
- 「川床」と子季語の意味
- 「新酒」と子季語の意味
- 「時鳥」と子季語の意味
- 「木の実」と子季語の意味
- 「梅雨」と子季語の意味
- 「海女」と子季語の意味
- 「清水」と子季語の意味
- 「湯帷子」と子季語の意味
- 「爽やか」と子季語の意味
- 「甘茶」と子季語の意味
- 「皀角子」と子季語の意味
- 「秋」と子季語の意味
- 「簗」と子季語の意味
- 「紫陽花」と子季語の意味
- 「繭」と子季語の意味
- 「胡麻」と子季語の意味
- 「芒」と子季語の意味
- 「芝神明祭」と子季語の意味
- 「苜蓿」と子季語の意味
- 「葭簀」と子季語の意味
- 「蛍」と子季語の意味
- 「霞」と子季語の意味
- 「風光る」と子季語の意味
- 「風薫る」と子季語の意味
- 「鮭」と子季語の意味
- 「鷽」と子季語の意味
- 「鹿」と子季語の意味
- 「麗らか」と子季語の意味
季語探しの強い味方『四季を語る季語』
季語を選ぶ際には、様々な要素を考慮する必要がありますが、従来の歳時記には子季語の意味が詳しく記載されていないため、適切な季語を選ぶのが難しいという課題がありました。
『四季を語る季語』は、全ての子季語の意味を網羅することで、この課題を解決し、よりスムーズな季語選択を可能にします。
↓↓下の本がそうです。
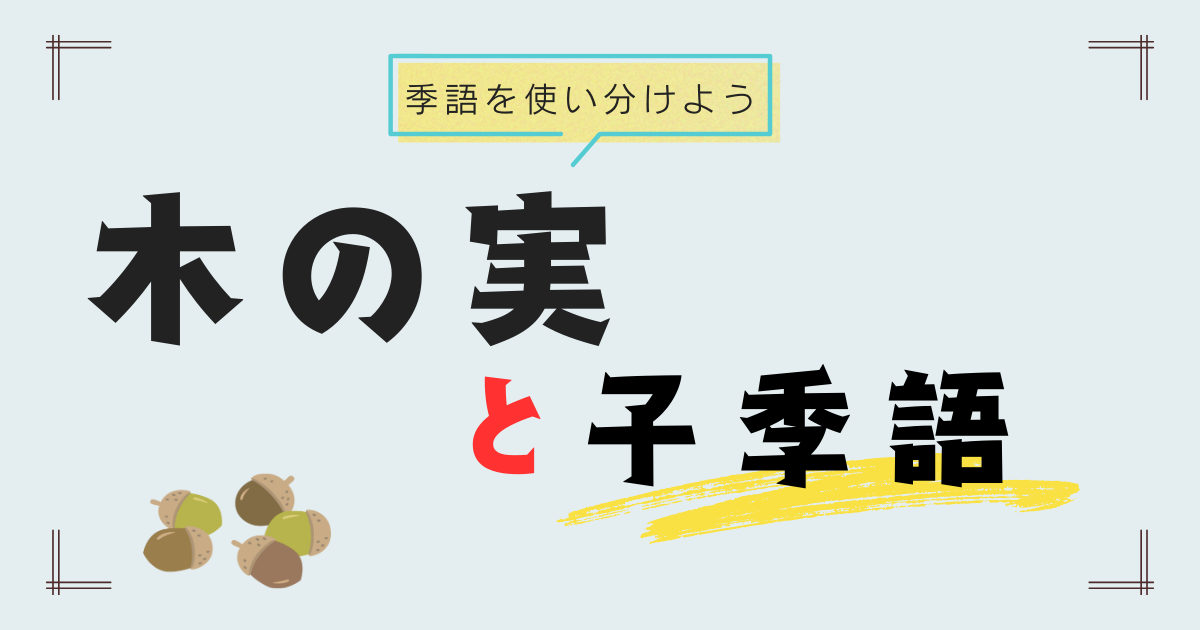


コメント