- 【綴りの比較】現代仮名遣い ⇔ 歴史的仮名遣い
- 「あらば」と「あれば」の違いを徹底解説
- 俳句における「去ぬ」「去る」について
- 古文の助動詞一覧(活用表)
- 古文の助詞一覧
- 俳句の推敲:句の中心を守って「伝わる一句」に
- 俳句における「初」「始」の使い分け
- 俳句における「聞く・聴く・訊く」の使い分け
- 俳句における「変わる・変える」の使い分け
- 俳句では「ゃ・ゅ・ょ・っ」を小書きにしてはいけない?
- 俳句における「答える・応える」の使い分け
- 俳句における「出る・出来る」の使い方
- 俳句にみる「咲かぬ」「咲きぬ」の違い
- 俳句にみる「来ぬ(こぬ)」と「来ぬ(きぬ)」の違い
- 「反対語」を使って俳句を直す方法!
- 俳句における「とき」「時」の使い分けから、「時間」の言葉まで
- 俳句における「暖かい・温かい」の使い分け
- 古文の動詞・形容詞一覧(活用表)
- 俳句における「上る・上がる・上げる」の使い分け
- 俳句における「合う・会う・逢う・遭う」の使い分け
- 俳句における「ある・おる・いる」の使い分け
- 俳句における「川・河・江」の使い分け
- なるほど!俳句の「二物取り合わせ」は、映像の「カット割り」と同じ
- 俳句の推敲:「を」と「が」を変える効果
- 俳句における「影・陰・蔭・翳」の使い分け
- 俳句では「はっ」とした特徴を詠もう
- 俳句は名句を参考に作ると良い
- 俳句で「色を組み合わせて」作る方法
- 俳句では、深く観察すると良い俳句が作れる
- 吟行でうまく作るには
- マンネリ俳句から抜け出す3つの方法
- 遠近法は大景を詠うときに大変に役に立つ
- 俳句の上達は模範が一番
- 【体験談】俳句を注意された後に確認したこと!
- 俳句に多い、文法の間違い「寂しけり」
- 俳句に多い、文法の間違い「涼しかり」
- 俳句で字余りは上五が良いと言われる理由は?
- 俳句の間違いに多い「現れる」
- 「切り口の独創性」は「新しい発見」のこと
- 「連体形止め」を使う6つの効果
- 俳句の世界を広げるオノマトペ
- 俳句で「漢語」を使うか「和語」を使うか
- 俳句における「日・陽」の使い分け
- 俳句で言葉を省略する方法!
- 「時間」を意識すると、俳句が上達する?
- 9音の季語は、ここに置くと作りやすい
- 8音の季語は、ここに置くと作りやすい
- 7音の季語は、ここに置くと作りやすい
- 6音の季語は、ここに置くと作りやすい
- 5音の季語は、ここに置くと作りやすい
- 4音の季語は、ここに置くと作りやすい
- 3音の季語は、ここに置くと作りやすい
- 2音の季語は、ここに置くと作りやすい
- 1音の季語は、ここに置くと作りやすい
- 簡単に「俳句で情景を詠む」方法を紹介!
- 俳句は「情報」ではなくは「体験」を書く
- 「俳句は具体的に詠む」の意味
- 俳句で多作をするコツ
- 俳句で気持ちを伝えよう!挨拶句について
- 俳句は読者に追体験をさせるように作る
- 「俳句で形容詞を消す」8つテクニック
- 「・・・だから」俳句を直す方法
- 俳句では皆「漢字」と「ひらがな」どう使い分けてるの?
- 俳句の語順で迷うのは、一二音を分解するから
- 俳句における「氷る・凍る」の使い分け
- 「参る・詣る・参詣・参拝」などの違い
- 動物の特徴で俳句を作ると良い
- 「普通のできごと」+「時間」で簡単に俳句を作る方法!
- 植物と自分を比較して、俳句を作ろう
- 初心者でもできる「予想外の出来事」を俳句にする方法
- 季語(植物)に2つの問いかけをして俳句を作る方法
- 俳句作りでは「音の響き」を意識すること
- 「伝わらない俳句」の3つの原因
- 初心者は俳句に季語を入れた方が良い理由
- 俳句で正しく旧仮名を使う方法
- 俳句で使われる「音便」をマスターしよう
- 俳句表現のひとつ「倒置法」について
- 「俳句は頭で考えないこと」の意味
- 俳句では「思い込みを裏切る」表現を意識しよう
- 「反対語」を使って不要な言葉を見つける方法
- 俳句では人と違う視点を持って、アレ(A.R.E.)を目指しましょう
- 俳句は、読み手に何かを「思い出させる」ように作ると良い
- 韻律(いんりつ)を知れば、1.5倍俳句が良くなる!(③音声の長さ)
- 韻律(いんりつ)を知れば、1.5倍俳句が良くなる!(①音声の強さ)
- 韻律(いんりつ)を知れば、1.5倍俳句が良くなる!(②音声の高さ)
- 俳句で「新しい発想」を出す方法
- 俳句上達の早道
- 悪い俳句になりやすい、9つのポイント
- 俳句初心者のための「多作多捨」入門:より深く、そして分かりやすく
- 俳句の連体形止めは良いか?悪いか?
- 俳句で読者の頭に景を浮かばせる3つのポイント
- 俳句作りでは、「5W1H」の中のこれを使え!!
- 俳句は「12音+5音」で作ると上手くいく
- 俳句作りで、あとひと単語が浮かばないときは、こうしよう
- 俳句の初心者は「一物仕立て」で作った方が良い?
- 『古語辞典』サイトの活用術
- 俳句の作り方「良い句をまねる方法」
- 「新仮名遣い・旧仮名遣い」「新字体・旧字体」の違い
- 「旧字・旧字体・旧仮名・旧仮名遣い・歴史的仮名遣い」など、同じ言葉を整理してみた!
- 俳句はシンプルが一番
 俳句の疑問(作り方)
俳句の疑問(作り方) 俳句では「ゃ・ゅ・ょ・っ」を小書きにしてはいけない?
俳句の世界では「ゃ・ゅ・ょ・っ」のような小文字は、大文字で書くべきだと言われることがあります。その理由として挙げられるのは、「旧仮名遣いでは小文字を大文字で表記していたから」というもの。新仮名が始まった1988年以前の旧仮名は小文字を大文字...
 俳句で注意をしたい言葉
俳句で注意をしたい言葉 俳句における「日・陽」の使い分け
俳句を作る際、太陽を指す言葉として「ひ」を使いたいとき、「日」と「陽」のどちらを使うべきか迷った経験はありませんか?この記事では、2つの漢字の意味の違いや、それぞれの言葉が持つ印象、俳句の例などを通して、「日」と「陽」の使い分けについて解説...
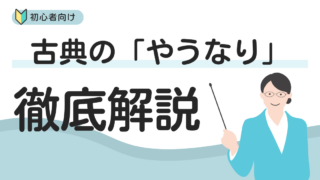 文語文法
文語文法 徹底解説!!「やうなり」の意味・接続・活用
古典の「やうなり」を徹底解説。意味・接続・活用・現代語訳など、分からなかった点がすぐに解消します。使い方の例文や例句も載せているため、俳句作りにも役立ちます。
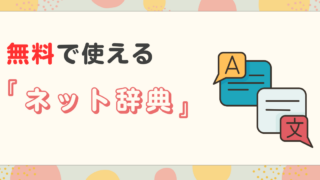 俳句を作る
俳句を作る 『より良い言葉』を探せるサイト
作品に合った言葉を探す俳句を作るときは、言葉の正しい意味や使い方を知らべることで、作者の意図が正確に読者に伝わる俳句になります。このサイトは、500種類もの辞書を横断検索して、言葉の意味や使い方を表示してくれます。関連する言葉を調べる類語辞...
 俳句を作る
俳句を作る 俳句は「自分らしさ」を追い求めた方がいい
個性的じゃなくていい、自分だけの俳句を追求しよう俳句を作るとき、「個性的な作品を作らなくちゃ」と悩んでいませんか?「誰も思いつかないような言葉を使ってみようか」「斬新な表現に挑戦してみようか」と考える人もいるかもしれません。しかし、個性やオ...
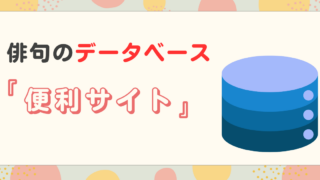 俳句を作る
俳句を作る 『俳句作品』を探せるサイト
俳句作品を探せるサイトを紹介します。季語や作者から作品検索「桜の俳句を探したい」「俳句の全文が分からない」「特定の俳人の作品を見たい」などの悩みを解決してくれるサイトです。以下のサイトでは、以下のような様々な検索方法が可能です。季語検索: ...
 俳句を作る
俳句を作る 季語が、季語にならないことがある
季語にならない季語?せっかく俳句で季語を使ったのに、実はその言葉が季語として機能していない、ということがあります。今回は、俳句初心者の方が見落としがちな、季語の「落とし穴」について探っていきましょう。季語が「季語にならない」理由俳句において...
 俳句の疑問(作り方)
俳句の疑問(作り方) 俳句では動植物をカタカナで書いてはいけないの?
俳句ではあまりカタカナを使わない俳句では、一般的にカタカナの使用は控えられます。その理由は、動植物の名前をカタカナにすると、学術的な意味合いが強くなり、俳句が持つ繊細な感情や情緒が失われてしまうからです。例えば、「兎」を「ウサギ」と表記する...
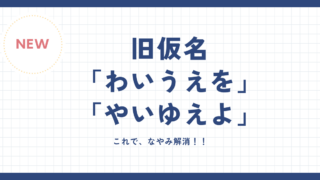 文語文法
文語文法 「わいうえを」「やいゆえよ」の旧仮名を徹底解説!
「わいうえを」「やいゆえよ」は特殊な言葉です。ここでは、カタカナ、旧字、発音、歴史的仮名遣い、パソコンでの打ち方、ローマ字など、徹底解説します。古文や古典でもよく見かける「わいうえを」「やいゆえよ」がしっかり理解できます。
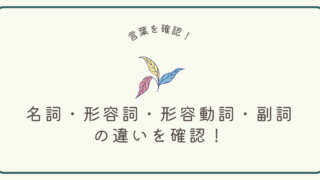 文語文法
文語文法 俳句での「名詞・形容詞・形容動詞・副詞」の使い分け
俳句では「名詞・形容詞・形容動詞・副詞」などの品詞の違いを理解することで、言葉の選び方の幅が広がり、より豊かな表現が可能になります。俳句を詠むためのヒントとして「名詞・形容詞・形容動詞・副詞」の役割と使い方を解説します。